Column
学校に行きたくないときの対処法は?
NG行動や親ができる対応を解説
2025年10月2日
800×450.jpg)
「学校に行きたくない」という子どもの言葉に、どう向き合えばよいのでしょうか。親として心配になる一方で、何をすればよいのか分からず戸惑ってしまう方も多いかもしれません。
本記事では、学校に行きたくない理由や適切な対処法、避けるべきNG行動について詳しく解説します。子どもの気持ちに寄り添いながら、親子で一緒に解決策を見つけていくためのヒントをお伝えします。
記事の最後では、メタバースを活用した新しい教育環境についても紹介します。ぜひご覧ください。
目次
学校に行きたくないと思っている人は多い
「学校に行きたくない」と感じている子どもは、実は珍しいことではありません。近年、この悩みを抱える子どもの数は増加傾向にあり、多くの家庭が直面している課題となっています。
国立成育医療研究センターが実施した「コロナ×こどもアンケート第6回調査」によると、小中高生の約38%が「学校に行きたくないことがある」と回答しており、コロナ禍を機に学校生活への不安や悩みを抱える子どもが増えていることが明らかになりました。
また、文部科学省の「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」では、不登校の児童生徒数は約24万5千人に上り、9年連続で増加していると報告されています。
このような現状の背景には、学習指導要領の改訂による学習内容の高度化、複雑化する人間関係、SNSの普及による新たなコミュニケーション課題、そして新型コロナウイルス感染症の影響による生活環境の変化などが挙げられます。
また、従来とは異なる価値観の多様化により「必ず学校に行かなければならない」という固定観念そのものに疑問を持つ家庭も増えています。
重要なのは「学校に行きたくない」という気持ちは決して特別なものではなく、多くの子どもが経験する自然な感情であるということです。この気持ちを否定したり軽視したりするのではなく、子どもが抱える背景を理解し、適切なサポートを提供することが求められています。
出典:国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート第6回調査 報告書」(https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/report/CxC6_repo_final.pdf)
出典:文部科学省「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」(https://www.mext.go.jp/content/20221021-mxt_jidou02-100002753_2.pdf)
学校に行きたくない理由は?
子どもが「学校に行きたくない」と感じる理由は実にさまざまで、複数の要因が絡み合っていることも少なくありません。文部科学省の調査データなどを参考に、主な理由を詳しく見ていきましょう。
理由1.なんとなく行きたくない
文部科学省の「令和2年度不登校児童生徒の実態調査結果」によると、不登校の要因として「きっかけが何か自分でもよくわからない」と回答する児童生徒が一定数存在します。この「なんとなく」という表現の背後には、複雑な心理状態が隠れていることが多いのです。
子ども自身が自分の気持ちを言語化できない場合や、複数の小さな不満や不安、無気力感が積み重なって漠然とした抵抗感となっている場合があります。また、思春期特有の心の変化や成長過程での混乱、将来への不安なども「なんとなく」という表現に集約されることがあります。
大人からすると曖昧に感じられるこの理由も、子どもにとっては非常にリアルで深刻な問題なのです。
出典:文部科学省「令和2年度不登校児童生徒の実態調査 結果の概要」(https://www.mext.go.jp/content/20211006-mxt_jidou02-000018318-2.pdf)
理由2.体調が悪い
「体調が悪い」という理由には、大きく分けてふたつのパターンがあります。
ひとつは、実際に身体的な不調がある場合です。睡眠不足や不規則な生活リズム、栄養バランスの偏り、運動不足などが原因で、朝起きられない、頭痛や腹痛がする、だるさを感じるといった症状が現れることがあります。
もうひとつは「学校に行こうとするとおなかが痛くなった」など、心理的なストレスが身体症状として現れる場合です。学校に行くことへの不安や緊張が、頭痛、腹痛、吐き気、めまいなどの身体症状を引き起こすことがあります。
これは「心身症」と呼ばれる状態で、決して仮病ではありません。子どもの心と体は密接に関連しており、精神的な負担が身体に影響を与えることは十分にあり得ることなのです。
どちらの場合も、症状を軽視せず、必要に応じて医療機関での相談や検査を受けることが大切です。
理由3.人間関係がうまくいっていない
人間関係の悩みは、学校に行きたくない理由として非常に多く挙げられます。同じく文部科学省の調査では「いじめ」「友人関係をめぐる問題」「教職員との関係をめぐる問題」などが上位にランクインしています。
友達とのトラブル、グループ内での孤立感、いじめや嫌がらせ、先生との相性の悪さなど、さまざまな人間関係の問題が学校生活への不安につながります。とくに思春期の子どもにとって、友人関係は非常に重要な位置を占めており、この部分でつまずくと学校全体が嫌な場所に感じられてしまうことがあります。
また、SNSの普及により、学校外でも人間関係のストレスが続くという新たな問題も生まれています。LINEの既読無視、グループチャットからの除外、ネット上での悪口など、24時間つながり続ける環境が子どもたちにプレッシャーを与えることもあります。
理由4.勉強ができない
学習面での困難も、学校に行きたくない大きな理由のひとつです。授業についていけない、テストの点数が悪い、宿題が終わらない、発表が苦手など、勉強に関する悩みは多岐にわたります。
とくに、学習内容が高度化する中学校以降では、小学校までの基礎が不十分だった場合に急激についていけなくなることがあります。また、学習障害や注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達特性により、一般的な学習方法では困難を感じる子どももいます。
勉強ができないことで自信を失い「どうせ自分はダメだ」という負のスパイラルに陥ってしまうと、学校自体を避けたくなってしまうのです。
理由5.ほかにしたいことがある
現代の子どもたちは、学校以外にも多くの興味深い選択肢に囲まれています。YouTubeやゲーム、アニメ、音楽、スポーツなど、自分が本当に好きなことや得意なことを見つけた時、学校の授業が退屈に感じられることがあります。
また、起業家精神を持つ子どもや、早期に将来の目標を見つけた子どものなかには、従来の学校教育では物足りなさを感じ、より実践的な学びや経験を求める場合もあります。インターネットの普及によって学校以外での学習機会も格段に増えており、学校が学びの場のすべてではないと考える子どもも少なくありません。
これらの理由は単独で存在することもあれば、複数が組み合わさって複雑な状況を作り出すこともあります。大切なのは、子ども一人ひとりの状況を丁寧に理解し、その子に合った対応を考えることです。
要因別・学校に行きたくないときの対処法
学校に行きたくない理由が分かったら、次はその要因に応じた適切な対処法を実践することが重要です。ここでは、子ども自身ができる対処法を中心に、親のサポートの視点も含めて解説します。
なんとなく学校に行きたくないときの対処法
「なんとなく」という曖昧な理由の場合、まずは自分の気持ちを整理することから始めましょう。日記を書いたり、信頼できる人に話したりして、自分の感情を言葉にしてみることが大切です。
具体的には「何が嫌なのか」「どんなときに嫌だと感じるのか」「どうなったら学校に行きたいと思えるのか」といった問いかけを自分にしてみましょう。紙に書き出すことで、漠然とした不安が具体的な課題として見えてくることがあります。
また、生活リズムを見直すことも効果的です。十分な睡眠時間を確保し、朝食をしっかりと摂り、適度な運動を取り入れることで、心身のコンディションを整えられます。小さな変化でも、気持ちに前向きな影響を与えることがあります。
親は子どもの話を否定せずに聞き、一緒に原因を探っていく姿勢を示すことが重要です。焦って解決策を押し付けるのではなく、子どものペースに合わせて寄り添うことで、子ども自身が答えを見つけやすくなります。
体調が悪くて学校に行きたくないときの対処法
身体的な不調がある場合は、まず基本的な生活習慣を見直しましょう。早寝早起きを心がけ、1日3食バランスの取れた食事を摂ることから始めます。とくに朝食は、脳と体のエネルギー源となるため重要です。
また、適度な運動習慣を身につけることで、血行が改善され、睡眠の質も向上します。散歩やストレッチなど、軽い運動から始めてみましょう。スマートフォンやゲームの使用時間を制限し、就寝前のブルーライトを避けることも、良質な睡眠のために大切です。
心理的ストレスが身体症状として現れている場合は、ストレスの原因を特定し、対処することが必要です。深呼吸やリラクゼーション法を身につけたり、好きな音楽を聴いたり、趣味の時間を作ったりして、心の緊張を和らげる方法を見つけましょう。
症状が続く場合や日常生活に支障をきたす場合は、小児科や心療内科での相談も検討しましょう。適切な医療サポートを受けることで、症状の改善が期待できます。
人間関係で学校に行きたくないときの対処法
人間関係の問題に直面したときは、まずひとりで抱え込まないことが重要です。信頼できる大人(親、教師、スクールカウンセラーなど)に相談し、客観的なアドバイスを求めましょう。
友達とのトラブルの場合は、可能であれば直接話し合いの機会を設けることを検討します。ただし、いじめや深刻な対立がある場合は、大人の仲介が必要です。学校に相談し、適切な対応を求めることが大切です。
新しい人間関係を築くために、自分の興味のある部活動やサークル、地域の活動に参加してみることも有効です。学校の中だけでなく、外の世界でも友達を作ることで、人間関係の幅が広がります。
また、コミュニケーション能力を向上させるために、相手の話をよく聞く、感謝の気持ちを表現する、相手のよいところを見つけるといった基本的なスキルを身につけることも重要です。
勉強が要因で学校に行きたくないときの対処法
学習面での困難を感じている場合は、まず自分の学習方法を見直してみましょう。一人ひとりに合った学習スタイルがあるため、さまざまな方法を試してみることが大切です。
分からない部分があれば、恥ずかしがらずに先生や友達に質問しましょう。また、学習塾や家庭教師、オンライン教育サービスなどを活用して、個別のサポートを受けることも有効です。
小さな目標を設定し、達成したら自分を褒めるという習慣を作ることで、学習に対する自信を回復できます。「今日は数学の問題を3つ解く」「英単語を5つ覚える」など、無理のない範囲で始めてみましょう。
学習障害や発達特性が疑われる場合は、専門機関での相談を検討し、子どもに合った学習支援を受けることが重要です。適切なサポートを受けることで、学習に対する意欲を取り戻すことができます。
ほかにしたいことがあって学校に行きたくないときの対処法
強い興味や才能を持つ分野がある場合は、それを伸ばしながら学校生活とのバランスを取ることを考えましょう。放課後や休日の時間を有効活用し、好きなことに打ち込む時間を確保します。
学校の勉強とは異なる学びの場として、専門的な教育機関やワークショップ、オンライン講座などを活用することも有効です。将来の目標に向けて必要なスキルや知識を身につけることで、学習に対するモチベーションも向上します。
ただし、学校教育の基礎的な部分も将来に役立つことを理解し、最低限の学習は継続することが大切です。好きなことと学校の勉強を完全に分離するのではなく、どちらも自分の成長に必要なものとして捉える視点を持ちましょう。また、同じような興味を持つ仲間とのつながりを作ることで、学校以外の居場所やコミュニティを見つけることも重要です。
これらの対処法はひとつだけでなく、複数を組み合わせて実践することで、より効果的な結果が期待できます。大切なのは、子ども自身が主体的に取り組み、周囲の大人が適切にサポートすることです。
学校に行きたくないときのNG行動は?
「学校に行きたくない」と感じたとき、つい取ってしまいがちな行動のなかには、状況を悪化させてしまうものがあります。まずは、子ども自身が避けるべきNG行動について詳しく解説します。
自己否定をする
「学校に行けない自分はダメな人間だ」「みんなはちゃんと学校に行っているのに自分だけおかしい」といった自己否定的な思考に陥ることは、最も避けたいNG行動のひとつです。このような考え方は、自己肯定感を著しく低下させ、問題解決から遠ざけてしまいます。
自己否定の思考パターンに気づいたら「今は学校に行くのが難しい時期なんだ」「これは一時的なものだ」「自分なりに頑張っている」といった、より客観的で優しい言葉に置き換えてみましょう。完璧でない自分も受け入れることが、回復への第一歩となります。
また、他人と比較することも避けましょう。一人ひとりの状況や成長のペースは異なります。他人の状況を基準に自分を評価するのではなく、自分自身の小さな進歩や変化に注目することが大切です。
反省しすぎる
「なぜ学校に行けないのか」「どうして自分はこうなってしまったのか」と過度に反省し続けることも、精神的な負担を増やしてしまいます。適度な振り返りは必要ですが、自分を責め続けるような反省は建設的ではありません。
過去の出来事や自分の行動について考えるときは、「次はどうしたらよいか」「どんな方法があるか」といった未来志向の視点を持つことが重要です。問題の原因を探ることよりも、解決策を見つけることに重点を置きましょう。
ひとりで抱え込む
「誰にも迷惑をかけたくない」「自分の問題は自分で解決しなければならない」と考えて、ひとりで悩みを抱え込むことは非常に危険です。孤立感が深まり、問題が複雑化してしまう可能性があります。
困ったときに助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、適切なタイミングで周囲のサポートを求めることは、問題解決のための重要なスキルです。
「話すこと」自体にも、気持ちを整理したり、ストレスを軽減したりする効果があります。完璧な解決策を求めなくても、誰かに話を聞いてもらうだけで心が軽くなることも多いのです。
無理して学校に行く
体調が悪い、強い不安がある、いじめられているなどの状況にもかかわらず「とにかく学校に行かなければならない」と無理を重ねることは、状況をさらに悪化させる可能性があります。
心身の限界を超えて無理を続けると、より深刻な体調不良や心の問題を引き起こすことがあります。また、根本的な問題が解決されないまま時間が過ぎてしまい、結果的により長期間の休学が必要になることもあります。
学校に行きたくない子どもへのNG行動は?【親視点】
子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、親としてどう対応すべきか迷うことは自然なことです。しかし、よかれと思ってとった行動が、かえって子どもを追い詰めてしまうこともあります。ここでは、親が避けるべきNG行動について詳しく解説します。
否定的な言葉を使う
「甘えている」「怠けている」「みんな我慢して学校に行っているのに」といった否定的な言葉は、子どもの心を深く傷つけてしまいます。このような言葉は、子どもの気持ちを否定し、自己肯定感を低下させるだけでなく、親子間の信頼関係にも悪影響を与えます。
子どもが「学校に行きたくない」と打ち明けることは、親を信頼している証拠でもあります。その勇気ある告白を否定的な言葉で返してしまうと、子どもは「もう親には話せない」と感じ、心を閉ざしてしまう可能性があります。
学校に行けない理由を詰問する
「なぜ学校に行きたくないの?」「理由をはっきり言いなさい」と厳しく詰問することは、子どもをさらに追い詰めてしまいます。とくに、子ども自身も理由がはっきりしない場合や、複雑な要因が絡み合っている場合は、プレッシャーを感じて口を閉ざしてしまう可能性があります。
また、いじめなどのデリケートな問題がある場合、無理に聞き出そうとすると子どもが話しにくくなることもあります。
無理に学校に行かせる
「とにかく学校に行きなさい」「行ってしまえばなんとかなる」と強制的に登校させることは、根本的な解決にはなりません。
むしろ、問題が解決していないまま登校を強いられた子どもは、恐怖心や苦しさを強めてしまいます。こうした負担は、子どもの体調不良やパニック症状を引き起こすほか、さらに学校から遠ざかってしまう可能性さえあるでしょう。
こうした強引な方法は、一時的に学校へ行かせることができたとしても、子どもと親の信頼関係を根底から崩壊させるリスクを持っています。親、ひいては家庭が安心できない場所だと認識した子どもは、それ以上他人から自分の心身が脅かされないよう周囲を拒絶したり、周囲を攻撃したりと、深刻な状況に発展することもあるのです。
真剣に受け止めない
「そのうち治る」「大したことではない」と軽視することも避けるべき行動です。大人から見れば些細に思える問題であっても、子どもにとっては非常に大きな問題なのです。
「思春期だから仕方ない」「一時的なもの」と決めつけてしまうことで、適切な対応のタイミングを逃してしまうこともあります。早期の対応が重要な場合もあるため、子どもの訴えを真剣に受け止める姿勢が必要です。
自分の価値観を押し付ける
「私たちの時代は我慢して学校に行った」「学校に行かないと将来困る」といった親世代の価値観や経験を押し付けることは、世代間のギャップを広げてしまいます。時代背景や教育環境、社会情勢は大きく変化しており、親世代の経験がそのまま当てはまるとは限りません。
現代の子どもたちは、SNSの普及、学習内容の高度化、進路選択の多様化など、親世代とは異なる課題に直面しています。このような変化を理解せずに、自分の経験や価値観だけで判断することは、子どもの現状を見誤る原因となります。
登校の復帰を意識しすぎる
「いつになったら学校に行けるの?」「早く普通に戻ってほしい」といった復帰への焦りを子どもに伝えることは、プレッシャーを与えてしまいます。親の不安な気持ちが子どもに伝わると、さらなるストレスの原因となるでしょう。
復帰を急ぐあまり、子どもの回復過程を軽視したり、十分な準備期間を設けなかったりすると、仮に登校を再開できたとしても再び不登校に戻ってしまうこともあります。
学校に行きたくない子どもに親ができることは?
子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、親として何ができるでしょうか。ここでは、親が主体的に取り組める具体的な対処法について詳しく解説します。
子どもの気持ちに寄り添う
最も重要なのは、子どもの気持ちを受け入れ、寄り添うことです。「学校に行きたくない」という気持ちを否定せず「つらい気持ちを話してくれてありがとう」「ひとりで抱え込まなくてよかった」といった言葉をかけてあげましょう。
子どもの話を聞くときは、解決策を急がず、まずは共感することから始めます。「そんなことがあったんだね」「それは大変だったね」といった反応を示すことで、子どもは理解されていると感じることができます。
また、子どもの感情を言語化してあげることも効果的です。「今は学校のことを考えると不安になるんだね」「疲れているんだね」といった言葉で、子どもが自分の感情を整理できるよう手助けします。
休んでいいと伝える
「今日は休んでもいいよ」「無理しなくていいよ」という言葉をかけることで、子どもの心理的な負担を軽減できます。登校への強制的なプレッシャーを取り除くことで、子どもは安心感を得ることができます。
ただし、ただ休ませるだけでなく、休む期間や条件について話し合うことも大切です。「今週は休んで、来週から少しずつ考えてみよう」「保健室登校から始めてみる?」といった具体的な選択肢を提示することで、子どもも将来への見通しを持つことができます。
休むことは逃避ではなく、心身の回復のための重要な時間であることを伝え、罪悪感を持たないよう配慮しましょう。
生活リズムを見直す
学校に行かない期間中も、基本的な生活リズムを維持することは重要です。朝起きる時間、食事の時間、就寝時間を規則正しく保つことで、心身のコンディションを整えることができます。
とくに朝の光を浴びることは、体内時計をリセットし、気分の改善にも効果があります。散歩や軽い運動を一緒に行うことで、親子のコミュニケーションの時間も作れます。
また、栄養バランスの取れた食事を心がけ、適度な運動習慣を身につけることで、身体的な健康を維持し、精神的な安定にもつながります。
家庭環境を見直す
家庭が子どもにとって安心できる場所になっているかを見直すことも重要です。家族間のコミュニケーションの質、家庭内のストレス要因、子どもの居場所の確保などを点検してみましょう。
兄弟間の比較や過度な期待、夫婦間の不和などが子どものストレスの原因となっていないか振り返ってみることが大切です。家庭が子どもにとって心の支えとなるよう、温かく受容的な雰囲気作りを心がけましょう。
また、子どもがひとりになれる時間や空間を確保することも重要です。プライバシーを尊重し、子どもが自分のペースで過ごせる環境を整えてあげましょう。
学校に相談する
担任の先生やスクールカウンセラー、養護教諭などと連携を取ることは非常に重要です。子どもの状況を正確に伝え、学校側の理解と協力を得ることで、より効果的な支援を受けることができます。
学校での様子、友人関係、学習面での課題などについて情報を共有し、家庭と学校が連携して子どもをサポートする体制を整えましょう。必要に応じて、個別の配慮や支援策について相談することも大切です。
また、保健室登校、別室登校、短時間登校などの段階的復帰の選択肢についても、学校側と相談して検討しましょう。
やりたいことを応援・支援する
近年は、学校とは異なる場所に「自分の居場所」を見つけやすい環境になってきています。たとえば、習い事、ボランティア活動、創作活動など、学校以外の場での成功体験は、子どもの心の支えとなります。
また、同じ興味を持つ仲間との出会いは、新たな人間関係を築くきっかけにもなります。子どもの「やりたい」という気持ちを大切にし、可能な限りサポートすることで、学校以外にも居場所があることを実感させてあげましょう。
地域の支援制度を見てみるのもおすすめ
自分が住んでいる地域でどのような支援制度が設けられているか、まずは確認してみることもおすすめです。こうした情報は、地方自治体やNPO法人の公式HPなどから確認できます。
最近では、一部の自治体において「教育メタバース」を活用した支援も始まっています。対面の支援施設に足を運ぶことが難しい子どもでも、自宅からメタバースに参加して授業を受けたり、仲間と交流したりできるようになりました。
その代表例が教育メタバース・FAMcampusです。FAMcampusは、自宅にいながら安全に「みんなを感じられる場所」を提供する教育空間として、一部自治体の不登校支援事業に採択されるなど注目を集めています。
まずは、自身の地域でどのような制度が利用できるのか、検索して調べてみましょう。
>>「メタバースって不登校支援で使えるの?」
FAMcampusを用いた文部科学省実証事業の結果をご紹介します。
学校以外の学習環境を設ける
学校に行けない期間中も、学習を継続できる環境を整えることは重要です。ただし、無理強いは禁物で、子どもの状態に合わせて段階的に取り組むことが大切です。
フリースクール
フリースクールは、学校に行けない子どもたちが安心して学べる場所のひとつです。一人ひとりの個性やペースを尊重し、柔軟な教育プログラムを提供しています。同じような経験を持つ仲間との出会いもあり、孤立感の解消にもつながります。
多くのフリースクールでは、従来の教科学習だけでなく、体験学習や創作活動、社会見学なども取り入れており、子どもの興味や関心に応じた学びの機会を提供しています。
通信制高校
高校生の場合、通信制高校への転校も選択肢のひとつです。自分のペースで学習を進めることができ、登校日数も従来の全日制高校より少なく設定されています。近年では、オンライン授業の充実やサポート体制の強化により、質の高い教育を受けることが可能になっています。
また、通信制高校から大学進学を果たす生徒も多く、将来の進路選択において不利になることはありません。
オンライン教育サービス
インターネットを活用したオンライン教育サービスも、学校以外の学習手段として注目されています。動画授業、オンラインゲーム、個別指導など、さまざまな形態のサービスが提供されており、子どもの学習スタイルに合わせて選択できます。
とくに、メタバース技術を活用した教育サービスでは、仮想空間内でアバターを使って学習することで、従来のオンライン学習の課題であった孤立感を解消し、ほかの生徒や先生とのコミュニケーションを図ることができます。
これらの支援方法は単独で実施するのではなく、子どもの状況に応じて組み合わせて活用することが効果的です。何より大切なのは、子ども自身の意思を尊重し、長期的な視点で成長を支援することです。
「FAMcampus」は、こうした新しい学びのスタイルを具体化した教育サービスのひとつです。子どもが安心して参加できるだけでなく、学習と交流の両面をバランスよく支援できる仕組みが整えられており、従来のオンライン教育にはなかった体験を提供しています。
>>「みんなを感じながら学べる」教育メタバース・FAMcampusの特徴はこちらから
学校を休む場合のよくあるQ&A
学校を休むことになった場合、多くの親子が抱く疑問や不安について、よくある質問と回答をご紹介します。
どれくらい休んだら不登校?
文部科学省による不登校の定義では「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」とされています。
つまり、年間30日以上の欠席がひとつの目安となりますが、重要なのは日数ではなく、子どもの心理状態や背景にある要因です。たとえ30日未満であっても、継続的に登校を渋る状況があれば、早期の対応が必要な場合もあります。
また、不登校という言葉に過度に敏感になる必要はありません。子どもにとって必要な休息期間と捉え、その期間を有効活用することが大切です。
出典:文部科学省「不登校の現状に関する認識」(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/futoukou/03070701/002.pdf)
どれくらい休んだら留年?
高校での留年は、主に単位制システムによって決まります。高校では、各学年で必要な単位数を修得する必要があり、出席日数が足りない場合は単位認定されない可能性があります。
一般的に、各科目の授業時数の3分の1以上を欠席すると、その科目の単位修得が困難になることが多いです。ただし、学校によって規定が異なるため、具体的な基準については在籍校に確認することが重要です。
留年を避けるためには、早期に学校と相談し、補習授業、レポート提出、代替学習などの方法で単位修得の可能性を探ることが大切です。また、通信制高校への転校なども選択肢として検討できます。
どれくらい休んだら大学入試に影響ある?
大学入試への影響は、入試方式によって異なります。一般入試(学力試験)の場合、出席日数が直接的に合否に影響することはほとんどありません。学力試験の結果が最も重要な判断材料となります。
しかし、学校推薦型選抜(旧推薦入試)や総合型選抜(旧AO入試)の場合は、調査書(内申書)の内容が重視されるため、欠席日数が影響する可能性があります。とくに指定校推薦では、校内選考の段階で出席状況が考慮されることが多く、欠席日数が多いと推薦を受けられない場合があります。
ただし、欠席の理由や期間中の取り組み、成長の過程などが適切に説明できれば、必ずしも不利になるとは限りません。重要なのは、休んだ期間をどのように過ごし、どのような学びや成長を得たかということです。
大学入試については早めに情報収集を行い、志望校の入試要項を確認することが重要です。また、進路指導教員やスクールカウンセラーとも相談しながら、最適な進路選択を検討しましょう。
まとめ
「学校に行きたくない」という子どもの気持ちは、決して特別なものではありません。大切なのは、その背景にある理由を理解し、子どもに寄り添いながら適切なサポートを提供することです。
従来の学校教育だけでなく、フリースクールやオンライン学習、メタバース空間を活用した新しい教育環境など、多様な学びの選択肢が広がっています。そのなかで、子どもたちが安心して「自分らしい学びのスタイル」を見つけられる場として注目されているサービスも登場しています。
なかでも「FAMcampus」は、学校に行きたくない・行けない子どもたちが、自宅から安心して参加できる、新たな学びと交流の場として注目されています。
FAMcampusでは、アバターを通じて仮想空間に参加し、授業に参加したり、先生に相談したり、仲間と気軽に話したりすることができます。プログラミングやAIによるイラスト制作など、創造力を刺激するイベントも実施しており、子どもたちは学習・交流を楽しみながら自然と自信をつけ、心のエネルギーを取り戻していきます。
実際に「外出できるようになった」「親子の会話が増えた」「再び学校に通い始めた」といった変化を感じているご家庭も多く、学びや交流を通じて子供たちの変化が期待できます。
メタバースというと3D空間をイメージする方も多いですが、FAMcampusはあえて2Dの仕組みを採用しています。3D空間には「没入感が高く、リアルな体験ができる」といったメリットもありますが、その反面、動作が重くなりやすい、操作が複雑になりがち、誰がどこにいるのか分かりづらいといったデメリットがあります。
それに対し、2D空間は全体を俯瞰的に見渡せるため、どこに誰がいるのか一目で把握でき、子どもたちに安心感を与えます。また、操作もシンプルで直感的なため、機械に不慣れな子どもでもすぐに使いこなすことができます。
子どもの未来は学校に行くか行かないかで決まるものではありません。一人ひとりに合った学びの環境を見つけ、子どもの可能性を信じて支援していくことが、何より重要です。
FAMcampusでは、子どもが自分らしく安心して第一歩を踏み出せるような、新しい選択肢のひとつとしての環境を整えていますので、お子様の状況や特性に応じて、メタバースに参加してみるのを検討してみてください。
>>FAMcampusは全国の不登校支援に活用されています。詳細はこちらからご覧ください。
>>参加したい方はお住まいの地域の教育委員会にお問い合わせください。
他の教育メタバースコラム
-
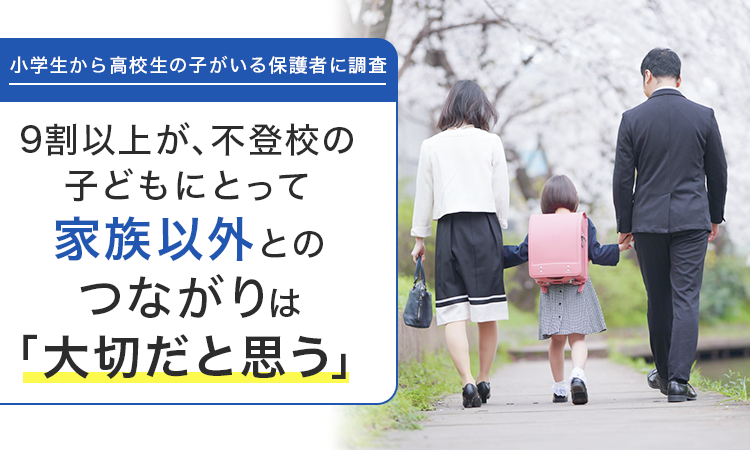
【小学生から高校生の子どもがいる保護者に調査】
9割以上が、不登校の子どもにとって家族以外とのつながりは「大切だと思う」2025年12月9日
-

メタバースとは?
VRとの違いや活用方法・課題まで分かりやすく解説2025年11月21日
-
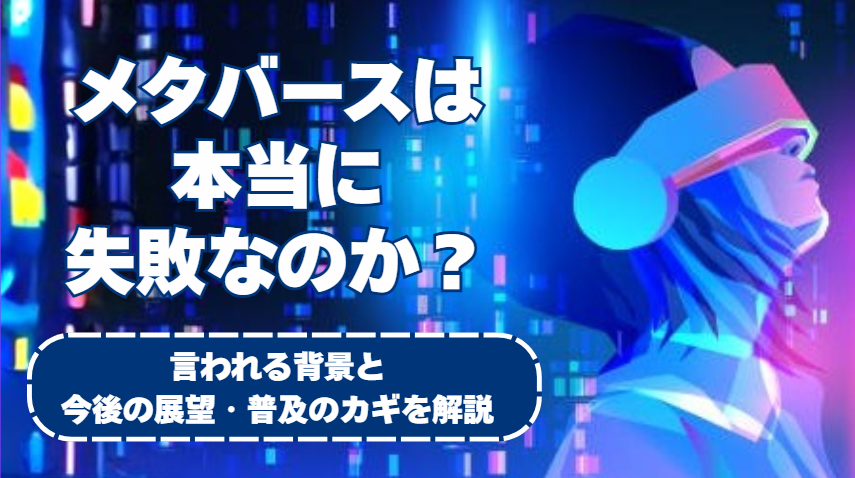
メタバースは本当に失敗なのか?
言われる背景と今後の展望・普及のカギを解説2025年11月21日
-

メタバースが「意味ない」と誤解されているのはなぜ?
その将来性を解説2025年11月21日
-

教育DXとは?教員・生徒・保護者それぞれのメリットと導入の進め方
2025年11月7日
-

【小学生から高校生の子がいる保護者に調査】
約2割の子どもが、「学校に行きづらさを感じている」
オンラインの活用に期待も2025年10月29日
-
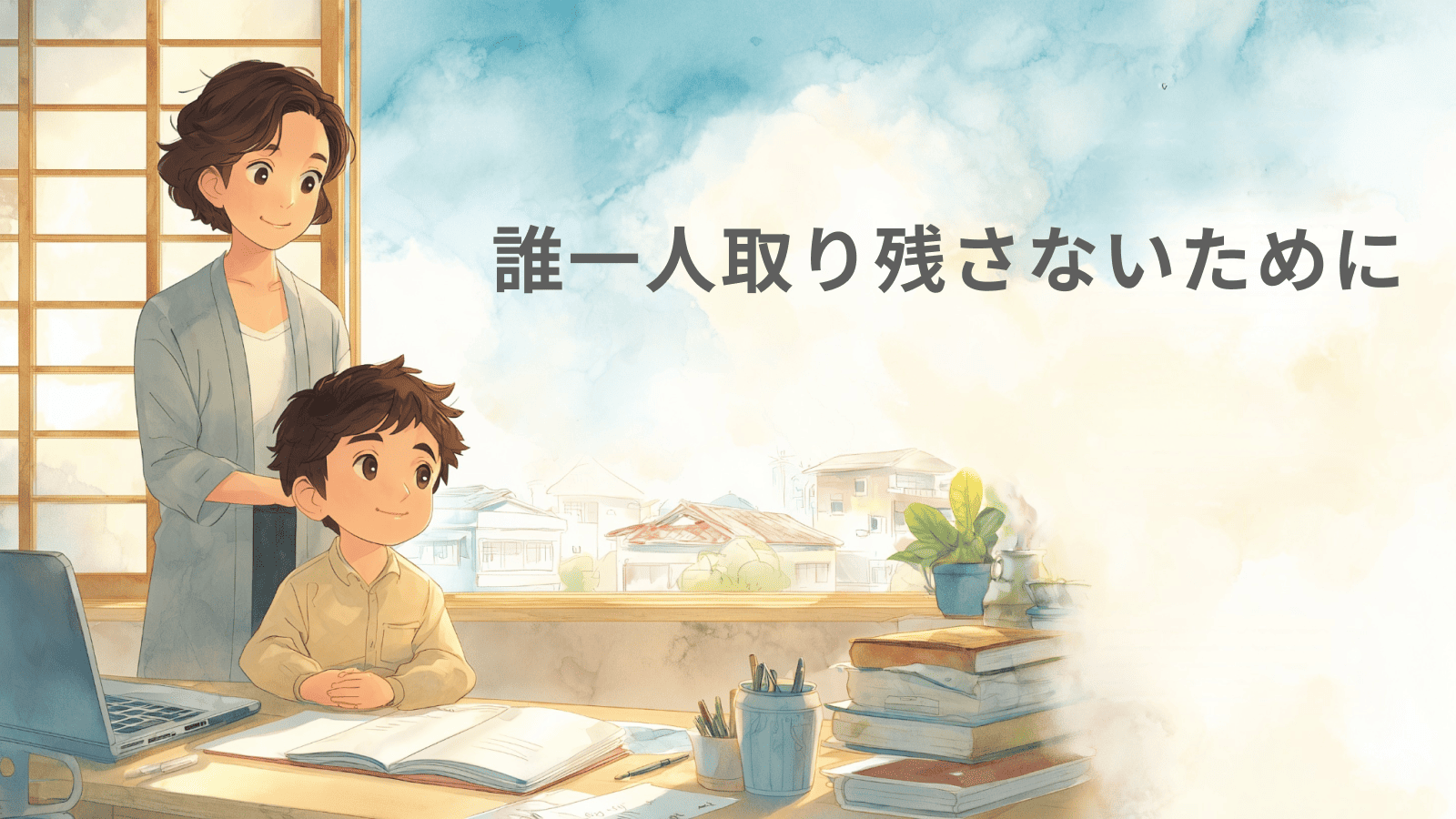
登校拒否とは?
不登校との違い、子どもへの効果的な対応・支援策を解説2025年10月24日
-
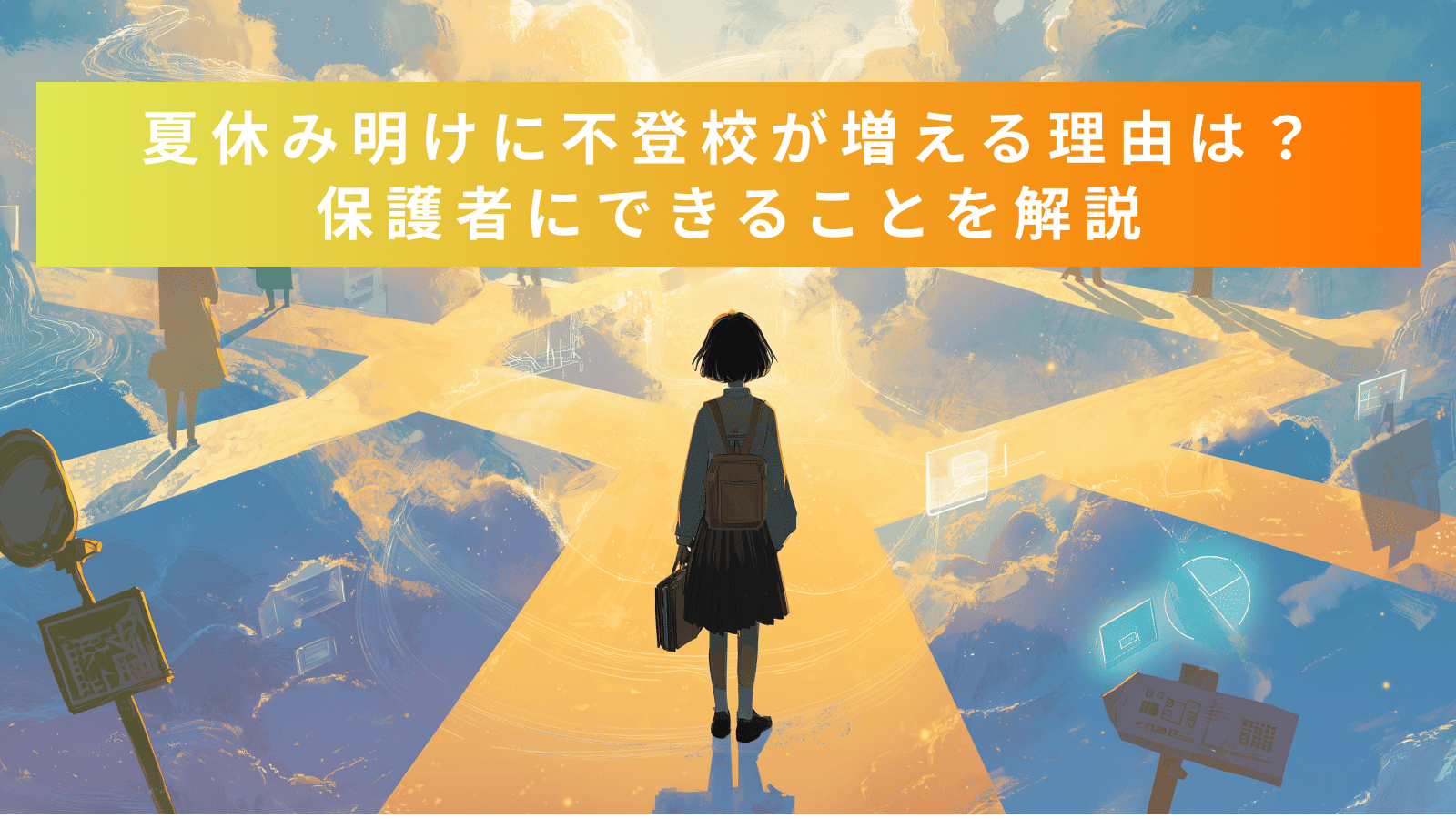
夏休み明け不登校はなぜ増えるのか。
その背景と実践的対応策2025年10月24日
-

メタバースって不登校支援で使えるの?文科省実証結果のご紹介
2024年5月9日
FAMcampusにご興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください




富士ソフトのFAMシリーズ
FAM(Fujisoft Augmented Meetup)とは、
コミュニケーションを拡張し新たなつながりを
創出するサービスです。




