Column
教育DXとは?教員・生徒・保護者それぞれのメリットと導入の進め方
2025年11月7日

近年、デジタル技術の急速な発展により、教育現場においても大きな変革が求められています。とくに新型コロナウイルスの影響を受け、遠隔授業やオンライン教材の活用が一気に加速しました。
教育DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるデジタル化を超えた教育の根本的な変革を指します。
本記事では、教育DXの定義から具体的なメリット、そして導入の進め方まで、自治体の教育担当者が知っておくべき情報を解説します。
目次
教育DXとは
教育DXとは、デジタル技術を活用して教育の仕組みや文化を変革する取り組みです。文部科学省では、教育DXを積極的に推進しています。
その目的は、児童・生徒の学力向上と現代社会で活躍できる力の習得にあります。教育DXの実現によって、一人ひとりの進度や理解度に応じた個別最適な学びが可能となり、従来の一斉授業では難しかった柔軟な教育が実現されます。
教育DXと教育のデジタル化の違い
教育のデジタル化は、大きく「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の3段階に分けられます。
最初の段階である「デジタイゼーション」は、紙の名簿やプリントをデジタルデータに置き換えるなど、アナログ情報をデジタル化する取り組みです。
次の「デジタライゼーション」では、デジタル化した情報を活用し、授業や校務を効率化・最適化します。
最終段階の「デジタルトランスフォーメーション(DX)」は、これらをさらに発展させ、教育の仕組みや価値を根本的に変革することを意味します。
たとえば、データを活用して一人ひとりに最適化した学習を提供したり、教師が経験だけに頼らずデータにもとづく指導を行ったりするなど、学校運営や教育モデルそのものを進化させる段階です。
教育DXが推進されている背景
教育DXが急速に推進されている背景には、現代社会が直面している複数の課題があります。これらの課題を解決するために、デジタル技術を活用した教育の変革が欠かせません。
デジタル社会に対応した人材の必要性
現代の子どもたちはデジタル環境に囲まれて育つ「デジタルネイティブ世代」であり、将来社会で活躍するためにはITリテラシーや情報モラル、セキュリティ対策などの基本スキルが欠かせません。
ITエンジニアに限らず、事務では表計算やプレゼンソフト、営業ではオンライン商談ツールが活用されており、あらゆる職種でデジタルスキルが求められています。
遠隔・オンライン教育の必要性
遠隔・オンライン教育は、感染症の流行や自然災害など、予期せぬ事態による学習機会の喪失を防ぐ重要な手段です。しかし、それだけでなく、平常時においても多様な学習ニーズに対応する有効な方法として注目されています。
とくに不登校児童・生徒にとっては、物理的に登校が難しい状況でもオンライン環境を通じて学習を継続できる重要な選択肢となります。
教員の負担軽減の必要性
教員の長時間労働は、日本の教育現場における深刻な問題です。授業準備や生徒指導だけでなく、成績管理、保護者対応、部活動指導、各種事務作業など、多岐にわたる業務が教員に集中しています。
教育DXによる校務の自動化・効率化は、この問題の解決に大きく貢献します。
文部科学省による教育DXの推進プラン
文部科学省は教育DXを国家的課題と位置づけ、体系的に推進しています。2020年の「デジタル化推進プラン」と、2022年にデジタル庁と連携して策定した「教育データ利活用ロードマップ」がその中心です。
これにより、データとデジタル技術を活用した教育改革を進め、「誰もが、いつでもどこからでも、自分らしく学べる社会」の実現を目指しています。
出典:「文部科学省におけるデジタル化推進プラン」
(https://www.mext.go.jp/content/20210412-mxt_jyohoka01-000014099_13.pdf)
出典:「教育データ利活用ロードマップ」
(https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000159621.pdf)
初等・中等教育におけるプラン
初等・中等教育では「GIGAスクール構想」が基盤となり、1人1台端末と高速ネットワーク整備を通じて個別最適な学びを実現します。
令和6年3月には普通教室の通信環境が約98%で環境整備が完了し、現在は端末とネットワークを活用する本格運用段階に入っています。
また、ICT支援員の配置や研修の充実を通じて、教員のICT活用能力向上も重点的に推進されています。
高等教育におけるプラン
高等教育では、国際競争力の強化が重点目標です。「大学・高専教育高度化プラン(Plus-DX)」を通じて補助金が交付され、デジタル技術を活用した教育環境の構築が推進されています。
加えて、高校で「情報Ⅰ」が必修化され、2025年1月から共通テストにも情報科目が導入されるなど、高等教育の入口段階から情報活用能力を重視する体制が整えられています。
教育DXによって得られるメリット
教育DXの推進により、教職員・児童・生徒・保護者の全てが具体的な利点を得られ、教育全体の質向上につながります。
教職員にとってのメリット
教職員にとって教育DXは、業務効率化と教育の質向上の両面で大きなメリットをもたらします。
労働時間を削減できる
教育DXにより、従来手作業で行っていた業務が自動化・効率化され、教員の労働時間を大幅に削減できます。
- 自動採点システム:テストや小テストの採点作業を自動化し、教師の負担を大幅に軽減
- 校務支援システム:出欠管理や成績処理、各種書類作成を効率化し、事務作業の時間を削減
- デジタル教材:個別最適化された学習や教材共有を可能にし、授業準備の手間を軽減
- 保護者連絡の効率化:欠席連絡や配布物の電子化により、電話・紙ベースのやり取りを減らし、教員と保護者双方の負担を削減
これらの効率化により生まれた時間を授業準備や生徒との対話、教材研究といった本来の教育活動に充てることができます。
児童・生徒の学習状況を把握しやすくなる
デジタル技術を活用することで、生徒一人ひとりの学習状況をリアルタイムかつ客観的に把握できるようになります。
従来のアナログ管理では、教師が一人ひとりと対話したりテスト結果を確認したりしながら、手作業で状況を把握する必要があり、時間がかかる上に情報の見落としも起こりがちでした。
学習データをツールで一元管理することで、各児童・生徒に合わせた指導方針を検討しやすくなり、より個々に寄り添った教育が実現します。
このように、経験や勘に頼らずデータにもとづいた指導が可能になり、生徒一人ひとりに応じた教育が実現します。
感染症まん延時の対応がしやすい
新型コロナウイルスの経験から、感染症拡大時に教育を途切れさせないことの重要性が明らかになりました。教育DXにより整備されたICT環境は、こうした緊急時の対応力を大幅に高めます。
- オンライン授業:休校時でも学習を継続でき、リアルタイム授業や録画配信など多様な形式で授業を提供できます。
- デジタル教材・クラウド活用:自宅から資料にアクセスでき、課題の配布・提出もオンラインで完結するため学習が途切れません。
- 教員の在宅勤務:オンライン会議や研修、保護者面談をリモートで実施でき、学校業務の継続性が確保されます。
このように、教育DXは非常時における教育活動の継続性を支える重要な基盤となります。
さらに、校内での感染症対策においても、密集を避けた学校運営が可能になります。たとえば「みらいスクールステーション」では、校内LANと大型提示装置を活用した校内ライブ放送機能により、全校朝礼や学校行事を各教室にリアルタイムで配信することが可能です。これにより、児童生徒を一か所に集める必要がなくなり、密集を避けた学校運営が実現します。従来のWeb会議ツールと異なり、インターネットを介さずに安定した高画質・高音質の配信が可能な点も、教育現場にとって大きな利点です
不登校児童・生徒への学習支援ができる
不登校児童・生徒は増加傾向にあります。教育DXは、こうした児童・生徒の「学びを止めない」ための重要な手段となります。
- ICT活用による支援:オンラインでのカウンセリングや学習支援が可能になり、画面越しやチャットを通じて相談しやすく、心理的ハードルが下がります。
- メタバースの活用:アバターとなって仮想空間に入り、仲間の存在を感じながら学習できることで、児童生徒の学習意欲を高められます。また、イベントや授業外の交流を通じて多様なコミュニケーションの機会を提供できます。
このような仕組みにより、不登校の生徒も学習機会を失わず、将来へつながる学びを継続できます。
教育メタバース「FAMcampus」では、学びと交流を両立する新しい学習体験を提供しています。
>>教育メタバースFAMcampusを活用した不登校支援についてはこちらをご覧ください。
児童・生徒にとってのメリット
児童・生徒にとって教育DXは、学習効果の向上と将来への準備の両面でメリットをもたらします。
ITに関する知識と技術を身に付けられる
デジタルネイティブ世代である児童・生徒にとって、ITスキルの習得は将来に欠かせない要素です。教育DXにより、早期からデジタル機器やツールに触れることで、自然にスキルを習得できます。
- 段階的なスキル習得:基本的なコンピュータ操作からプログラミング、データ分析まで段階的に学べます。
- 情報モラル・セキュリティ:実践的な学習を通じてリスク回避能力を養い、安全にデジタル社会を活用できます。
- キャリアへの応用:どの職業にも生かせる汎用的な能力として、将来の選択肢を広げます。
このように教育DXは、児童・生徒が将来の社会で活躍するための基盤づくりに貢献します。
個別最適化されたカリキュラムを受けられる
AIやデータ分析技術の活用により、生徒一人ひとりの学習状況に応じた個別最適化されたカリキュラムを提供できます。
- 従来の課題解消:一斉授業では進度差により理解が不十分になるケースがありましたが、個別最適化により各自に合った学習が可能になります。
- 理解度に応じた課題設定:システムが自動で適切な難易度の問題を選定し、効果的に学習できます。
- 苦手・得意分野への対応:苦手分野は基礎から丁寧に、得意分野は発展的内容まで進めることができます。
これにより、生徒は自分のペースで学習を進め、自己肯定感を持って取り組むことができます。
デジタル教科書でより効率的な学習ができる
デジタル教科書は紙の教科書にはない多様な機能を備え、より理解しやすく効率的な学習を実現します。
- アクセシビリティの向上:音声読み上げで視覚障害や読字困難の生徒も利用でき、拡大・縮小表示で見やすさを調整できます。
- 理解の促進:動画やアニメーション、インタラクティブ教材により、抽象的な概念や実験・歴史的場面を視覚的に理解できます。
- 学習記録の充実:マーカーやメモ機能で個別の学習記録を残せ、修正も容易なため常に整った教材を維持できます。
このように、デジタル教科書は学習効果を高めつつ、生徒一人ひとりに適した学びを支援します。
保護者にとってのメリット
保護者にとって教育DXは、子どもの学習状況の把握や学校との連携において大きな利点をもたらします。
- 学校との連絡効率化:アプリやメールでの情報共有により、紛失リスクが減少。欠席・遅刻連絡や保護者会案内、個別面談予約もオンラインで対応できます。
- 学習状況の可視化:デジタル教材や学習管理システムを通じて、学習時間や理解度を客観的に確認でき、家庭でのサポートが的確になります。
- 家庭学習の質向上:デジタル教材やオンラインコンテンツを活用することで、子どもが興味を持ち、自主的に学習へ取り組みやすくなります。
このように教育DXは、保護者にとっても安心感と利便性を高め、家庭と学校の連携を一層強化します。
教育DXの現状:ICT環境の整備状況は地域差が大きい
文部科学省の調査によると、教育DXの基盤となるICT環境は全国的に整備が進んでいるものの、地域間で大きな差が見られます。
【教育DXに関するICT環境整備の現状】
| 項目 | 数値 | 備考 |
| 学習者用コンピューター台数(平均) | 1.1台 | 共用端末を含むため必ずしも個人専用ではない |
| 無線LAN整備率(普通教室) | 98.3% | |
| 高速回線整備率(1Gbps以上) | 81.0% | |
| 教員ICT研修受講率(最低値) | 56.8% | 地域差が大きい |
| 教員ICT研修受講率(最高値) | 99.6% |
表から分かるように、学習者用コンピュータや通信環境は全国的に整備が進み、ハード面は概ね充実しています。
一方で、教員のICT研修受講率には大きな地域差があり、整備された環境を十分に活用できない可能性が指摘されます。このことが教育の質の格差につながる懸念があります。
これらの状況から、教育DXを効果的に推進するには、技術的整備に加えて教員研修の充実や地域格差の是正といった人的・社会的な取り組みが不可欠です。
出典:文部科学省「令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)(令和6年3月1日現在)」
(https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jogai02-000037398_01.pdf)
教育DXを推進するうえでの課題
教育DXの推進には多くのメリットがある一方で、解決すべき課題も存在します。これらの課題を適切に認識し、対策を講じることが、成功する教育DXの実現には不可欠です。
インフラの整備と費用負担
教育DXの実現には、端末導入に加えネットワークやソフトウェア、セキュリティなど多面的なコストが発生し、継続的な資金投入が欠かせません。
とくにGIGAスクール構想で配布された端末は4〜5年ごとに更新が必要で、故障やバッテリー劣化への対応も課題です。さらに、家庭には通信費などの負担が生じ、経済格差につながる懸念もあります。
こうした状況を踏まえ、国や自治体による財政支援の強化と、効率的なシステム運用が求められています。
個人情報などのセキュリティ対策
教育DXでは、児童・生徒や保護者の個人情報、学習履歴、健康情報など機密性の高いデータを扱うため、適切な管理と保護が不可欠です。
情報漏洩や不正アクセスを防ぐには、多段階認証や暗号化、権限設定などの技術的対策が求められます。
また、教職員にはパスワード管理やフィッシング対策などのセキュリティ教育が必要です。文部科学省のガイドラインにもとづいた包括的な体制構築が、教育DX推進の大前提となります。
ネットリテラシーの問題
1人1台端末の普及により、児童・生徒がネットいじめや個人情報の流出、有害サイト、SNSトラブルといったリスクにさらされる機会が増えています。さらに、偽情報の拡散や著作権侵害など、意図せず加害者になる可能性もあります。
これらを防ぐにはフィルタリングなどの技術的対策だけでなく、児童・生徒自身が情報モラルを身につけることが不可欠です。端末利用ルールを明確化し、継続的に指導するとともに、保護者への啓発も重要です。
教員のICTに関する知識や経験の不足
教育DXの成否は教員のICT活用力に大きく左右されますが、世代や経験による格差が存在し、すべての教員が十分なスキルを持っているわけではありません。新しい技術への対応には継続的な学習が必要ですが、多忙な業務の中で研修時間を確保するのは困難です。
そのため、階層的な研修体系やICT支援員の配置、外部専門家の活用など多角的なサポートが求められます。さらに、トラブル対応や授業での活用方法を支援する体制を整え、教員が安心してICTを取り入れられる環境を構築することが不可欠です。
教育DXの進め方|6つのステップで解説
教育DXを成功させるには、計画的かつ段階的な取り組みが欠かせません。ここでは、一般的なDX推進の6つのステップを教育現場に応用して解説します。
1:DX推進の目的を明確にする
教育DXの出発点は「なぜ行うのか」「どんな環境を実現したいのか」という目的とビジョンを定めることです。目標は抽象的でなく、数値を含めて具体化することが効果的です。
たとえば「個別最適化で学力を向上させる」「不登校生の学習機会を80%以上確保する」「教員の残業を30%削減する」といった形です。さらに、5年後・10年後の学校の姿を描き、関係者間で共有することで取り組みの優先順位を明確にできます。
児童・生徒、保護者、地域などすべての関係者にとってのメリットを示すことも不可欠です。
2:目的達成における課題を洗い出す
設定したビジョンと現状のギャップを精査し、解決すべき課題を特定します。IPAの「DX推進指標」などを参照し、技術だけでなく組織文化・人材育成・推進体制まで多面的に評価しましょう。
具体的には、ICT環境、教職員のスキル、児童・生徒のITリテラシー、保護者の理解、予算確保、セキュリティ体制を調査します。教職員・児童・生徒・保護者へのヒアリングで現場の声を反映し、先進自治体の事例をベンチマークして想定課題を事前に把握します。
3:実施する施策の計画を立てる
課題分析を踏まえ、DX戦略と実行計画を策定します。まずは出席管理やデジタル連絡帳、自動採点など導入しやすく効果が実感しやすい施策から始め、成功体験を積み重ねます。
次の段階ではオンライン授業や学習履歴データの活用、AIによる個別支援などへ発展させ、最終的にはメタバース授業やAI教師による支援など教育モデルの変革を目指します。
各段階で必要な予算・人材・技術・期間を明確にし、リスク対策を含めた計画を立てることが重要です。
4:DX推進チームを作る
教育DXの成功には、専門知識を持つ推進チームの設置が欠かせません。理想的には、リーダー、システム開発やUI/UXの専門家、データ分析担当、教育現場に精通した教員などで構成されます。
チームはビジョンの共有や課題の吸い上げ、部門間調整、技術支援、研修企画など幅広い役割を担います。さらに、プロジェクトマネージャーや技術責任者など役割を明確化し、専門性を活かした体制を整えることが重要です。
外部の専門家の活用も視野に入れよう
多くの自治体や学校では専門人材の確保が難しく、コンサルティング会社やシステム開発会社、教育関連企業と協業することが効果的です。
ただし、丸投げではなく、内部チームと外部専門家が連携して進める体制づくりが重要です。現場の知見と技術的専門性を組み合わせることで実効性が高まり、さらに教職員の育成を並行して行うことで将来的な内製化にもつながります。
5:施策を実行する
策定した計画を実行に移す段階では、段階的導入と継続的改善が重要です。
まずは特定の学年や教科で試行し、成果と課題を分析して全校展開へつなげます。教職員には研修や説明を行い、不安を軽減しながら小さな成功体験を積み重ねることで受容度を高めます。
さらに、生徒や保護者にも情報提供を行い、とくにセキュリティやプライバシーへの懸念には丁寧に対応し、安心して利用できる環境を整えることが欠かせません。
6:評価と改善を継続して行う
教育DXは導入して終わりではなく、継続的な評価と改善によって効果を高めます。評価指標は学習成果や業務効率化、システムの安定性、満足度など多面的に設定し、教職員・生徒・保護者からのフィードバックを反映させます。
また、新しい技術の登場に合わせてアップデートを行い、既存システムの統合や改善を進めます。こうしたPDCAサイクルを継続的に回すことで、教育DXは進化し続け、より高度な教育モデルの実現につながります。
まとめ
教育DXは、デジタル技術を活用して教育の仕組みや文化を変革し、個別最適な学びや教員の負担軽減、保護者との連携強化など多方面にメリットをもたらします。
一方で、インフラ費用、セキュリティ、教員のITリテラシー向上といった課題も存在し、教育DXを推進するには明確なビジョン、段階的な実施、継続的な改善が不可欠です。
とくに不登校児童・生徒が全国で増加傾向にある中、従来の支援方法には限界があります。こうした課題に対応する手段のひとつとして、教育メタバースの活用が注目されています。
富士ソフトが提供する教育メタバース「FAMcampus」は、学校に行きたくても行けない子どもたちが自宅から安心して参加できる、新たな学びと交流の場として高く評価されています。
アバターを通じて仮想空間に入り、学習や多様な交流を体験できることで、孤立感を和らげ、心理的なハードルを下げつつ学習機会を確保できます。
また、人的支援と独自のカリキュラムを組み合わせることで、学校や自治体の負担を軽減しつつ質の高い学習環境を提供できる点も特徴です。
さらにFAMcampusは、不登校支援にとどまらず、通信制高校や高大連携プログラムでの授業、離島や過疎地での合同授業など、幅広い教育現場で活用されています。
このように、FAMcampusは教育DXが目指す「誰一人取り残されない個別最適な学び」を実現するための有効な手段です。教育DXの推進を通じて、すべての児童・生徒が自分らしく学び、成長できる環境づくりに貢献しています。
>>こちらの記事では、メタバースを活用した不登校支援について解説しています。文科省実証結果も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
他の教育メタバースコラム
-
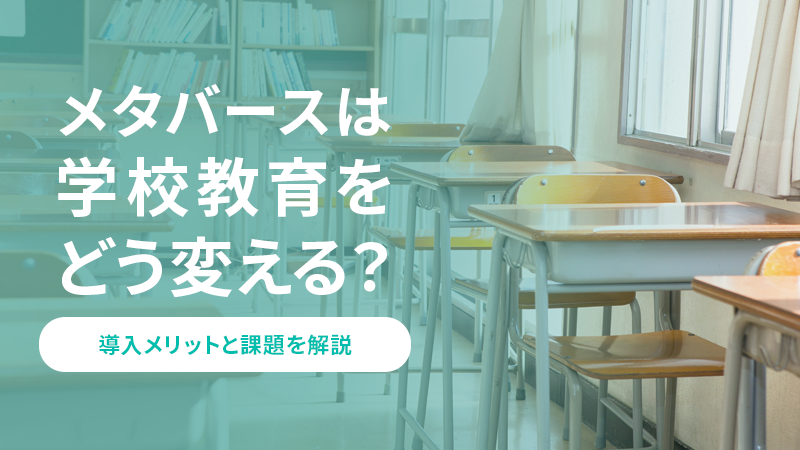
メタバースは学校教育をどう変える?
導入メリットと課題を解説2025年12月23日
-

自治体のメタバース活用事例11選
地方創生や教育支援での動向を解説2025年12月23日
-
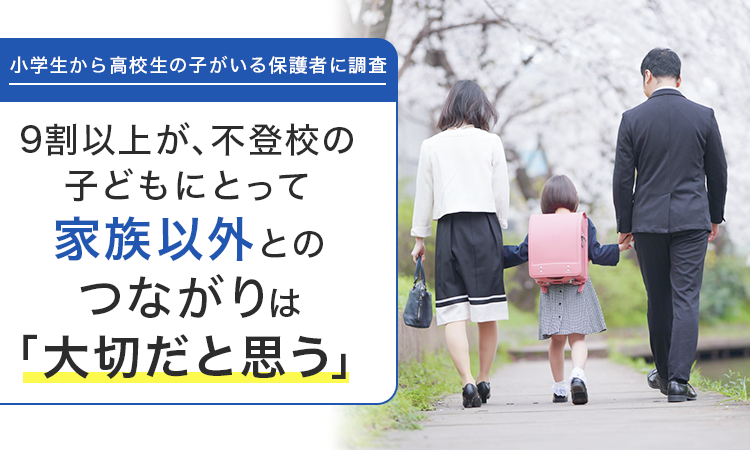
【小学生から高校生の子どもがいる保護者に調査】
9割以上が、不登校の子どもにとって家族以外とのつながりは「大切だと思う」2025年12月9日
-

メタバースとは?
VRとの違いや活用方法・課題まで分かりやすく解説2025年11月21日
-
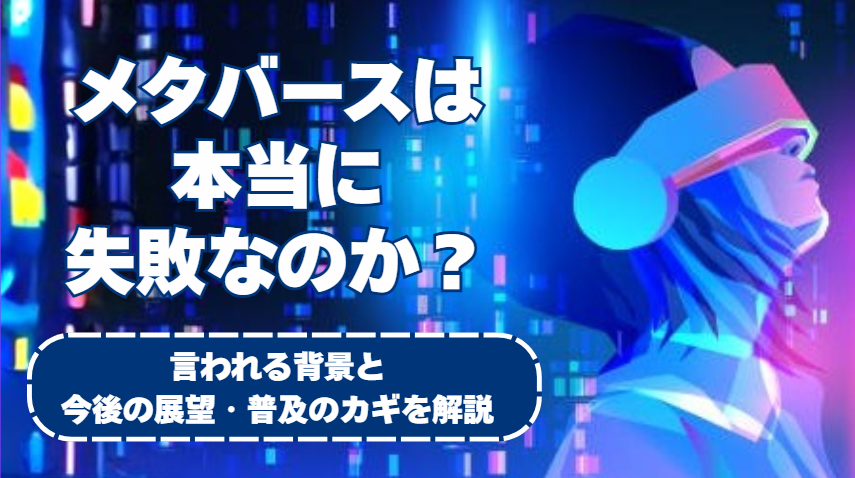
メタバースは本当に失敗なのか?
言われる背景と今後の展望・普及のカギを解説2025年11月21日
-

メタバースが「意味ない」と誤解されているのはなぜ?
その将来性を解説2025年11月21日
-

【小学生から高校生の子がいる保護者に調査】
約2割の子どもが、「学校に行きづらさを感じている」
オンラインの活用に期待も2025年10月29日
-
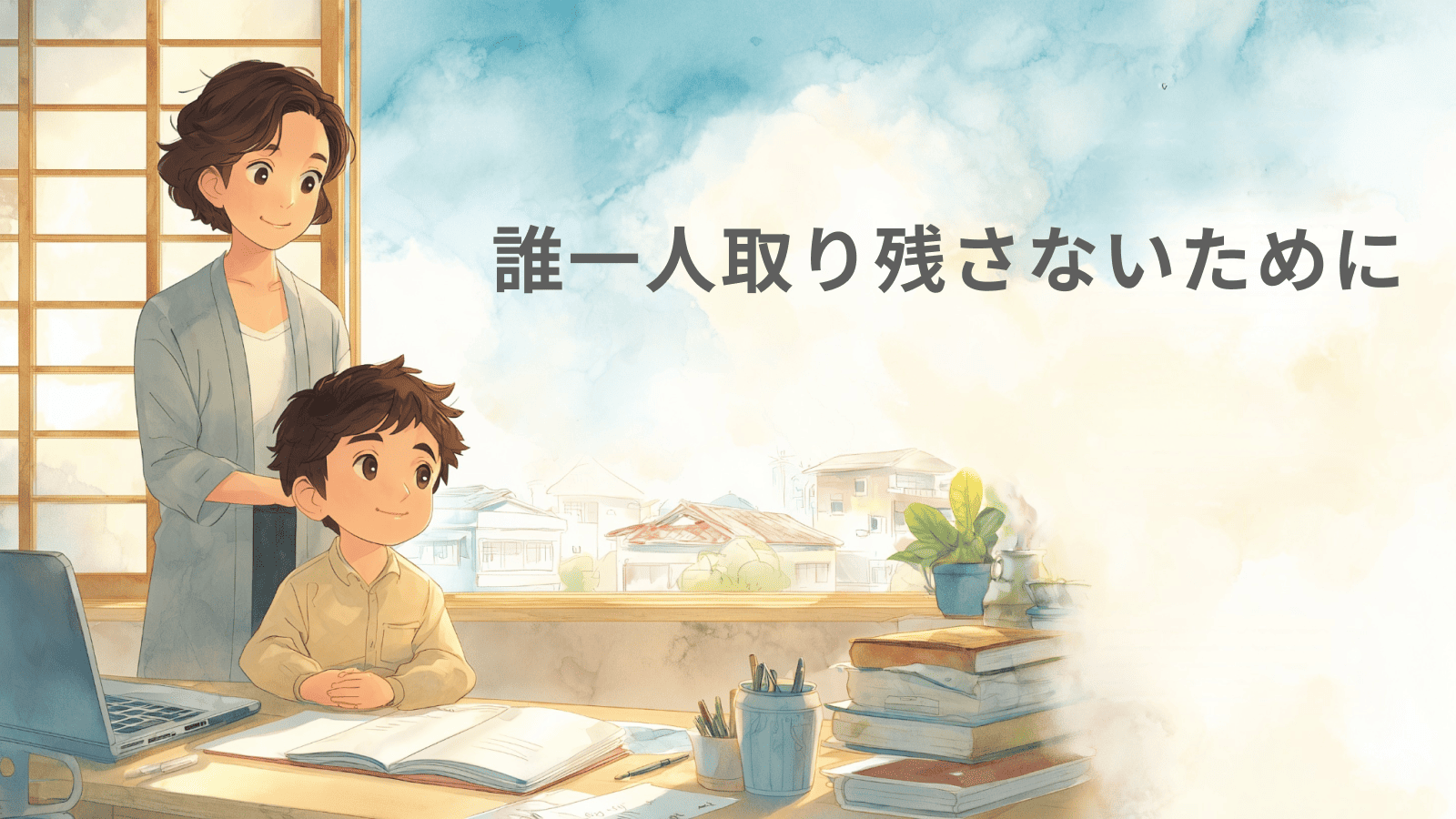
登校拒否とは?
不登校との違い、子どもへの効果的な対応・支援策を解説2025年10月24日
-
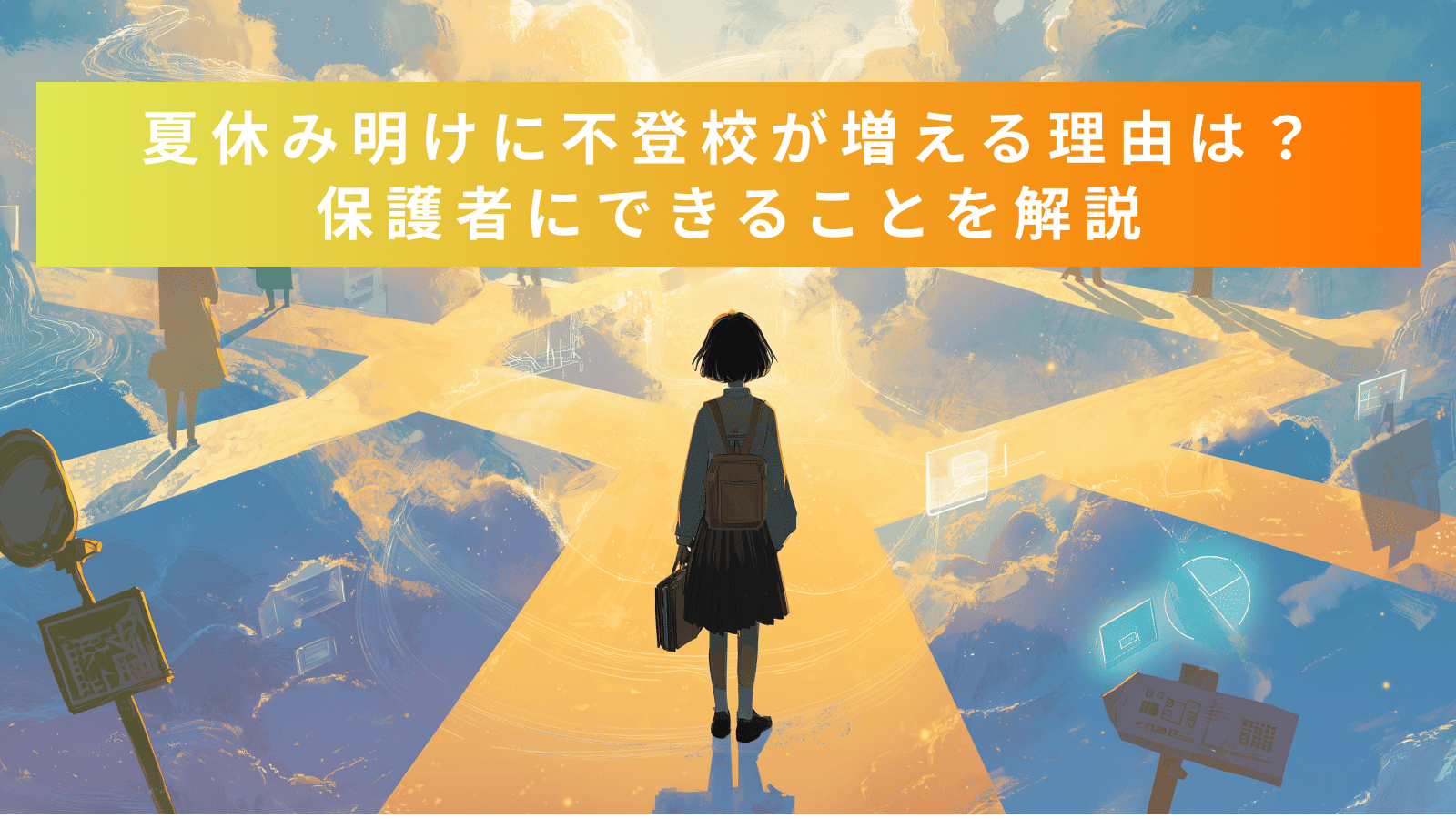
夏休み明け不登校はなぜ増えるのか。
その背景と実践的対応策2025年10月24日
FAMcampusにご興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください




富士ソフトのFAMシリーズ
FAM(Fujisoft Augmented Meetup)とは、
コミュニケーションを拡張し新たなつながりを
創出するサービスです。




