Column
メタバースとは?
VRとの違いや活用方法・課題まで分かりやすく解説
2025年11月21日

最近では、SNSやニュースを通じて「メタバース」という言葉を目にしたり耳にしたりする機会が増えています。しかし実際には、なんとなくイメージはあっても、詳しくは分からないという人も多いのではないでしょうか?
メタバースは、いまやゲームや娯楽だけに限られたものではありません。ビジネスや教育の現場で役立つだけでなく、不登校支援などの社会問題にも活かせる可能性を持っています。
この記事では、メタバースの基本的な意味や仕組みからVR等の他技術との違い、活用事例や課題までを解説します。
目次
メタバースとは?
メタバースとは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間を指します。「超越」を意味する「meta(メタ)」と「世界」を意味する「universe(ユニバース)」を組み合わせた造語です。
この仮想空間では「アバター」と呼ばれる、仮想世界での自分の姿を通して活動します。空間のなかでは、現実と同じように人と出会い、会話をしたり、さまざまな体験を楽しんだりすることができます。
メタバースの歴史
メタバースという概念は実は新しいものではありません。最初にこの言葉が登場したのは1992年、アメリカの作家ニール・スティーヴンスンが発表したSF小説「スノウ・クラッシュ」のなかでした。
その後、2003年に三次元の仮想空間「セカンドライフ」が公開され、メタバースの先駆けといえるサービスとして日本でも2006年頃に大きなブームを巻き起こしました。
しかし、当時は通信環境やパソコンの性能が十分でなく、一時的な流行で終わってしまいます。それでも、仮想空間での交流や活動の可能性が実際に試された貴重な時期でした。
やがてインターネット技術の進歩や5G通信の普及、VRデバイスの低価格化が進んだことで再びメタバースは注目されるようになります。
とくに2021年にはFacebook社が「Meta」へと社名を変更し、メタバース事業に本格的に参入すると発表しました。この出来事をきっかけに、世界的な注目が一気に高まったのです。
メタバースとVR・AR・MR・XRの違い
メタバースを正しく理解するためには、よく一緒に語られるVR・AR・MR・XRとの違いを押さえておくことが大切です。これらの技術は互いに深く関わっていますが、意味はそれぞれ異なります。
VR
VR(Virtual Reality:仮想現実)とは、専用のゴーグルを装着して360度の仮想世界に入り込む技術のことです。現実の景色を完全に遮断し、コンピュータで作られた空間のなかに没入する体験を可能にします。
VRは「仮想空間を体験するための技術・手段」として位置づけられます。たとえば航空会社では客室乗務員の訓練に使われ、医療現場では手術シミュレーションに活用されています。
一方で、メタバースは「インターネット上に構築された仮想空間そのもの」を指します。必ずしもVRゴーグルを必要とせず、パソコンやスマートフォンからでもアクセスできる点がVRとの大きな違いです。
とくに教育現場では、文部科学省が推進するGIGAスクール構想に対応しており、全国の小中学校で配布された1人1台のパソコンやタブレットをそのまま活用できます。
AR
AR(Augmented Reality:拡張現実)は、現実の世界に仮想の情報を重ね合わせて表示する技術です。スマートフォンのカメラを通して景色を見ると、その場にデジタル情報が追加されて映し出されます。
分かりやすい例が「ポケモンGO」です。街中を歩きながら画面をのぞくと、まるで現実空間にポケモンが現れたかのように見え、捕まえる体験ができます。
ARは「現実世界を拡張する技術」であるのに対し、メタバースは「仮想空間そのもの」を指します。
MR
MR(Mixed Reality:複合現実)は、現実空間と仮想空間をリアルタイムで融合させる技術で、仮想のオブジェクトが現実の環境に合わせて自然に配置されます。さらに、複数人が同じ視覚情報を共有できる点も大きな特徴です。
たとえば、製造業では設計図を三次元で表示し、技術者たちが同じオブジェクトを見ながら議論できます。医療分野では、患者の体内を立体的に可視化し、手術の精度を高める取り組みに活用されています。
MRは「現実と仮想を融合させる技術」であり、メタバースのように「仮想空間そのもの」を指すわけではありません。
XRとメタバースの違い
XR(Extended Reality:拡張現実)は、VR・AR・MRをまとめて指す言葉です。現実と仮想を組み合わせるあらゆる技術の総称として使われています。
イメージすると分かりやすいのは、メタバースが「仮想空間という場所」であるのに対し、XRは「その場所に入るための技術」です。
つまり、メタバースでの体験を実現する手段がXRであり、利用者はXRを通じてメタバースにアクセスし、さまざまな体験を得ることができます。
メタバースが注目されている背景
このように、VR・AR・MRを含むXRはメタバースを体験するための技術として進化してきました。ではなぜ、いま世界中でメタバースそのものが大きな注目を集めているのでしょうか?
VR技術の発展と普及
VRデバイスは技術革新によって、以前よりも軽く、価格も手頃になってきました。たとえば、2019年度のVR機器の出荷台数は約4,863万台でしたが、2020年には6,200万台を超えています。
さらに、Meta Quest 2やPlayStation VRといった比較的リーズナブルな製品の登場により、メタバースを体験するためのハードルは大きく下がりました。
出典:総務省「平成30年度版情報通信白書」
(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd111350.html)
オンラインコミュニケーションの進化
5G通信の普及により、大容量データを高速かつ安定してやり取りできるようになりました。その結果、複数人が同時に参加する三次元の仮想空間でも、遅延の少ないスムーズなコミュニケーションが可能になっています。
従来のWeb会議システムでは実現が難しかった「まるで同じ場所にいるような感覚」での交流も、メタバースなら体験できるようになっているのです。
コロナ禍によるコミュニケーション手段の変化
新型コロナウイルスの流行により、外出自粛やソーシャルディスタンスが求められました。この制約のなかでオンラインコミュニケーションは一気に広がり、より臨場感のある交流手段へのニーズが高まっていきました。
テレワークやオンライン授業、リモート会議が日常となった今、従来のビデオ通話だけでは得にくい「共通体験」や「偶然の雑談」を実現できる場として、メタバースが注目されるようになったのです。
NFTなどの関連技術の発達
NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)や仮想通貨の技術が実用化されたことで、メタバース内のデジタル資産に現実的な価値を持たせられるようになりました。
たとえば、仮想空間の土地や建物、アイテムを売買し、実際のお金と同じように経済活動を行うことができます。
この仕組みによって、メタバースは単なる娯楽の場を超え、ビジネスが展開される新しい経済圏へと進化しているのです。
大企業の参入と投資
Facebook社(現Meta)が社名を変更し、約1兆円規模の投資を打ち出したことをきっかけに、Microsoft、Google、Appleといった大手企業も次々とメタバース事業に参入しました。
矢野経済研究所によると、国内メタバース市場は2021年度の793億円から急拡大し、2028年度には1兆8,700億円に達すると予測されています。新たな成長産業としての期待は非常に大きいのです。
出典:矢野経済研究所「メタバースの国内市場動向調査を実施(2024年)」
(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3688?a8=4)
メタバースのメリット
メタバースが注目され続けているのは、それだけ多くのメリットがあるためです。メタバースがもたらす価値は多岐にわたり、私たちの生活や仕事の在り方に新しい可能性を広げています。
ここでは、代表的なメリットを紹介します。
オンラインコミュニケーションにおける没入感が向上する
従来のZoomやTeamsといったWeb会議システムには「発言のタイミングが取りづらい」「相手の表情が分かりにくい」といった課題がありました。
これに対してメタバースでは、アバターを通じて自然に会話の間合いをつかみやすく、相手の感情も伝わりやすい環境を実現できます。
アバターの身振り手振りや表情の変化によって、より自然なコミュニケーションが可能になります。また、複数のグループで同時に会話したり、雑談が生まれたりと、現実のオフィスに近い交流も再現できるのです。
上智大学言語教育研究センターの清水崇文教授によれば、こうした雑談はイノベーションや生産性の向上に大きく寄与するとされています。つまりメタバースは、リモートでもクリエイティブな活動を行う場をつくる有力な方法といえるでしょう。
出典:「仕事の生産性やイノベーションに影響を与える“雑談”コロナ禍で変化する、職場コミュニケーションのあるべき姿とは」
(https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/2934/)
現実では不可能な演出ができる
メタバース空間では、現実の物理法則に縛られない表現が可能です。
たとえば、理科の実験を安全にスローモーションで観察したり、歴史の授業で過去の街並みをそのまま再現して歩き回ったりと、現実の教室では体験できない学びを提供できます。
また、企業によってはメタバース上で新製品の発表会が行われています。そこでは重力を無視した大胆な演出や、実物では不可能な透明表示を取り入れることで、従来のオンライン発表会を大きく超える臨場感を実現しています。
住む場所やハンディキャップの制約がなくなる
メタバースは、インターネット環境さえあれば世界中のどこからでも空間に参加できます。地理的な制約はもちろん、身体的な制約も大幅に軽減されます。
アバターを通じて交流することで、性別や人種、年齢、障害の有無といった現実世界の枠にとらわれず、フラットな関係でコミュニケーションを取ることができます。
こうした特徴は、とくに不登校の児童・生徒にとって新しい学びの場となり、孤立感の解消にもつながります。
実際に、株式会社NEXERと富士ソフトの共同調査では、9割以上の保護者が「不登校の子どもにとって家族以外とのつながりは大切だと思う」と回答しています。「家族には話しにくい悩みも外なら話せる」「自分の居場所を広げることが大事」といった声も寄せられました。
さらに「オンラインで不登校の子ども同士がつながれる場」については、半数以上が肯定的で「孤独感がやわらぐ」「外に出られない子でも交流できる」といった期待が寄せられています。
メタバースは、こうしたニーズに応える新しい「つながりのプラットフォーム」として注目されています。
調査データ引用元:
メタバースが抱える課題
メタバースは多くの可能性を秘めていますが、その発展にはまだ解決すべき課題が残されています。ここでは、代表的な課題を整理して見ていきましょう。
なりすまし
メタバースではアバターを介して活動するため、他人になりすましたり、虚偽の身元で振る舞ったりするリスクがあります。安心して利用できる環境を実現するには、本人確認の仕組みを整備することが欠かせません。
改ざん
メタバースで使われるデータや取引記録は、不正に書き換えられてしまう危険があります。もしそんなことが起きれば、安心して利用できなくなってしまいます。そのため、ブロックチェーンのような技術を使って、記録を透明で安全に保つことが重要です。
否認
メタバース内での取引や合意について、後になって「そんな約束はしていない」と否認されるリスクがあります。こうしたトラブルを防ぐためには、信頼性の高い取引記録を保全する仕組みが必要です。
情報漏洩
アバターの行動履歴や会話内容、さらには個人情報が漏洩するリスクがあります。利用者が安心して活動するためには、強固なプライバシー保護の仕組みを整えることが必要です。
サービス拒否
サイバー攻撃を受けると、メタバースのサービス自体が止まってしまう危険があります。安心して使えるようにするために、セキュリティ対策・体制の構築が重要です。
権限昇格
システム管理者の権限を不正に奪われ、メタバース空間を不正に操作されるリスクがあります。こうした被害を防ぐには、厳格なアクセス管理と監視体制の整備が必要です。
デジタル所有権
メタバース内で作成・購入したアバターやアイテムの所有権は、サービスが終了すれば失われてしまう恐れがあります。利用者の資産を守るためには、デジタル資産を永続的に保護できる仕組みを確立することが必要です。
著作権
メタバースで生み出されたコンテンツの著作権の扱いや、既存の著作物を利用する際の許諾など、知的財産権に関する法整備はまだ十分ではありません。創作者の権利を守りつつ、利用者の利便性も確保するバランスが求められています。
メタバースの活用例11選
多くの課題を抱えながらも、メタバースはすでにさまざまな分野で実用化が進んでいます。ここでは、その具体的な活用事例を紹介します。
ゲーム
メタバースといえば、まず思い浮かぶのがゲームの世界ではないでしょうか?友達と一緒に冒険したり、バーチャルライブに参加したりと、遊びの楽しさがどんどん広がっています。
たとえば、人気ゲーム「フォートナイト」では、戦闘要素を外した「パーティーロイヤル」モードを使い、さまざまなアーティストがバーチャルライブを開催しました。このイベントには世界中から数千万人が参加し、大きな話題となりました。
また「あつまれ どうぶつの森」では、Anna Suiなどのファッションブランドがアバター用の衣装を提供し、現実とバーチャルの垣根を越えた新しいビジネスの形が展開されています。
ショッピング
Burberry、Beams Japan、GUCCI、NIKEといった有名ブランドは、すでにメタバース上にバーチャルショップを展開しています。利用者はアバターで店内を歩き回り、店員から接客を受けながら商品を購入することができます。
三越伊勢丹も「REV WORLDS」でバーチャル新宿を再現し、これまでにないショッピング体験を提供しています。
イベント・ライブ
バーチャルライブ、さらには企業のVR社員総会など、大規模イベントがメタバース上で次々と開催されています。
従来のオンラインイベントでは得にくかった臨場感や、参加者同士の一体感を味わえるのが大きな特徴で、まるで現実の会場に集まっているかのような体験が可能です。
観光
メタバースの活用は都市や地域、さらにはグローバル企業にも広がっています。
「バーチャル都市」として展開される取り組みでは、街全体をデジタル空間に再現し、人々がイベントや交流を楽しめる環境が整えられています。
地域レベルでは、商工団体や研究会が協力して地元特産品を扱う「バーチャル商店街」をオープンし、利用者は24時間いつでも訪れて買い物を楽しむことができます。
一方、国際的なホテルチェーンでは、メタバース上にホテルやカンファレンスセンターのデジタルツインを構築し、現実の施設を忠実に再現する事例も出ています。
これらの取り組みは、都市型から地域型、そして企業活用まで、メタバースが多様な分野で新たな価値を生み出す可能性を示しています。
教育
教育分野におけるメタバース活用は、いま注目を集める領域のひとつです。生徒の多くはデジタル環境に親しんでおり、従来の教室よりもスムーズにメタバース学習環境へ適応できるケースも少なくありません。
また、教育向けメタバースの可能性として注目されているのが不登校支援での活用です。これまで外出が困難で学校や対面施設の支援を受けられなかった児童生徒に対して、自宅から参加できる環境を提供することができます。
その背景には、全国的に増加する不登校児童の課題があります。株式会社NEXERと富士ソフトの共同調査によると、小学生から高校生の子どもを持つ保護者の約2割が「子どもが学校に行きづらさを感じている」と回答しました。
一方で、不登校児童・生徒に対する地域行政の取り組みについては約7割が「充実していない」と答えており、支援体制の不足が浮き彫りになっています。とくに保護者からは「オンライン学習や交流の支援を拡充してほしい」という声がもっとも多く寄せられました。
調査データ引用元:
こうしたニーズに応える取り組みの代表例が、富士ソフトが提供する教育メタバース「FAMcampus」です。「FAMcampus」は奈良県や神奈川県の不登校支援事業に正式採択され、子どもたちが家から安心して参加できるオンラインの学習・交流空間として活用されています。
FAMcampusの最大の特徴は「教育に特化している」点です。アバターを近づけるだけでビデオ通話が始まる直感的な操作性や、交流のための多彩なスペースが用意されており、教育現場での使いやすさを徹底的に考えた設計になっています。
さらに、不登校支援にとどまらず、通信制高校の授業や学校見学、高大連携プログラムなど幅広い教育現場で導入が進んでいます。
すでに早稲田スクールや学研グループといった大手教育機関が導入しており、その実績と信頼性は高く評価されています。
従来のWeb会議ツールを用いたオンライン学習では難しかった授業前後のコミュニケーションを補完し、「みんなを感じられる学習空間」を実現します。これにより、コミュニケーション課題や学習者の孤独感を解消し、学習モチベーション向上を支援します。
>>教育メタバースFAMcampusを活用した不登校支援についてはこちらをご覧ください。
バーチャルオフィス
近年では、アバターを使って仮想空間に出社できる「バーチャルオフィス」サービスが登場しています。
実際の職場にいるように同僚と会話したり、一緒に業務を進めたりできる環境が整いつつあり、リモートワークの課題とされてきた孤立感やコミュニケーション不足を補う効果が期待されています。
自然な雑談や偶然の会話が生まれることでチームワークが強化され、柔軟な働き方を可能にするとともに、組織全体の生産性や働きやすさの向上につながります。
その一例が、富士ソフトが提供する「FAMoffice」です。「FAMoffice」は、アバターを介して社員同士が自然に交流できる仮想オフィス空間で、実際のオフィスのようにフロア全体を見渡しながら、メンバーの在席状況や業務の様子を一目で確認できます。
テレワーク中でもWeb会議ツールを使わずにビデオ通話で気軽に会話や打合せができ、社員間の交流活性化や一体感の醸成につながる新しい職場環境として活用が進んでいます。
リモート会議
最新の仮想会議サービスを活用すれば、従来のビデオ会議を超える没入感のあるミーティングが可能です。参加者は仮想空間に集まり、まるで同じ場所にいるかのように会話や議論を進められます。
さらにホワイトボードに直接書き込んだり、三次元オブジェクトを使って説明したりできるため、情報が視覚的に伝わりやすく、共有の効率も向上します。これにより、リモート環境でも対面に近い体験が実現し、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
展示会・カンファレンス
バーチャル展示会では、来場者がアバターを操作して会場を自由に移動し、ブースを訪れて担当者と直接やり取りできます。地理的な制約がないため、世界中から参加者を集められる点も大きな利点です。
その一例が、富士ソフトが提供する「FAMevent」です。
「FAMevent」は、展示会・カンファレンス・セミナーなどを仮想空間で再現するプラットフォームで、ブース見学・資料閲覧・商談・セミナー視聴などをすべてオンライン上で完結できます。
フロア全体を俯瞰して見渡せ、参加者は自由にテーブルを移動しながら交流できます。イベントの目的に応じてレイアウトを柔軟に設計でき、最大1,000人までの同時配信にも対応しています。
さらに、Zoomアカウントと連携することで、社内イベントのような小規模開催から大規模カンファレンスまで幅広く運用可能です。
LAND(土地)の売買
「The Sandbox」や「Decentraland」といったメタバースプラットフォームでは、仮想空間の土地をNFTとして売買できます。手に入れた土地では、イベントを開催したり、ゲームを運営したりと、さまざまなビジネスを展開することが可能です。
婚活
メタバースを活用した婚活サービスも登場しています。アバターを介して出会うことで、従来の婚活のように外見に左右されず、性格や価値観を重視したマッチングが実現できます。新しい出会いのスタイルとして、現実にはない自由さや安心感を提供しています。
行政手続き
東京都江戸川区では「メタバース区役所」を開設し、住民がアバターで区役所を訪問して職員に相談できるサービスを提供しています。行政サービスのデジタル化における新たな取り組みとして、大きな注目を集めています。
参考:東京都江戸川区「メタバース区役所」
(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e003/kuseijoho/keikaku/kuseiunei/dx/metaverse.html)
まとめ
メタバースとは「超越」と「世界」を組み合わせた造語で、インターネット上に構築された三次元の仮想空間を指します。現在ではエンターテインメントを超え、ビジネスや教育、さらには社会課題の解決にまで活用の幅が広がっています。
富士ソフトでは、このメタバース技術を活用し「FAMcampus」「FAMoffice」「FAMevent」のサービスを提供しています。
特徴的なのは、3Dではなくあえて「2D形式」を採用している点です。3D空間は没入感が高い一方で、動作の重さや操作の複雑さ、参加者の位置把握の難しさといった課題がともないます。
その点、2Dであれば「全体を見渡せる」「誰がどこにいるか一目でわかる」といった安心感があり、直感的な操作性によって機械に不慣れな方でもストレスなく利用できます。
教育に特化したメタバース「FAMcampus」は、アバターで学習空間に参加できる仕組みや、仲間の存在を感じられる教育環境、多彩なコミュニケーションスペースなどが備わっており、教育現場の課題解決に大きく貢献しています。
働く場に特化した「FAMoffice」は、アバターを通して社員同士が自然に交流できる仮想オフィスです。出社状況や業務の様子を視覚的に把握でき、チームの生産性や心理的なつながりを支える新しいワークスタイルを提供します。
交流や情報発信に特化した「FAMevent」は、展示会・セミナー・カンファレンスなどを仮想空間で再現するプラットフォームです。来場者が自由にブースを回り、担当者と対話できる仕組みを備え、場所や距離の制約を超えた新しい出会いと情報発信を実現します。
富士ソフトは、メタバースの可能性を通じて、現実とデジタルの境界を越え、人と人がより自然につながる社会を実現しています。
他の教育メタバースコラム
-
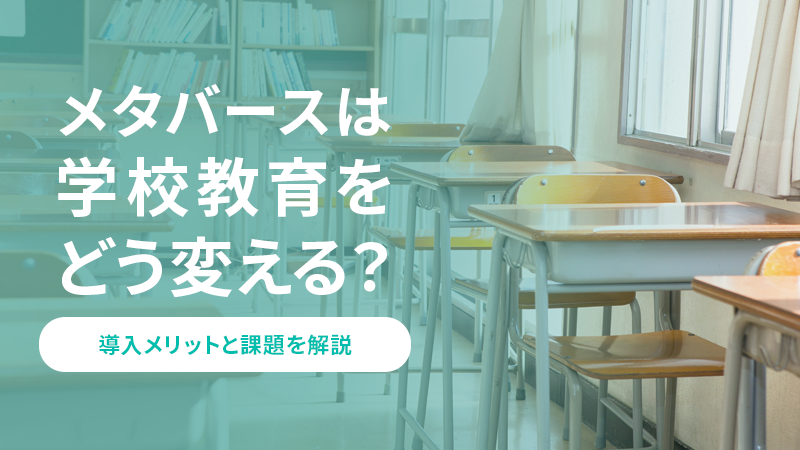
メタバースは学校教育をどう変える?
導入メリットと課題を解説2025年12月23日
-

自治体のメタバース活用事例11選
地方創生や教育支援での動向を解説2025年12月23日
-
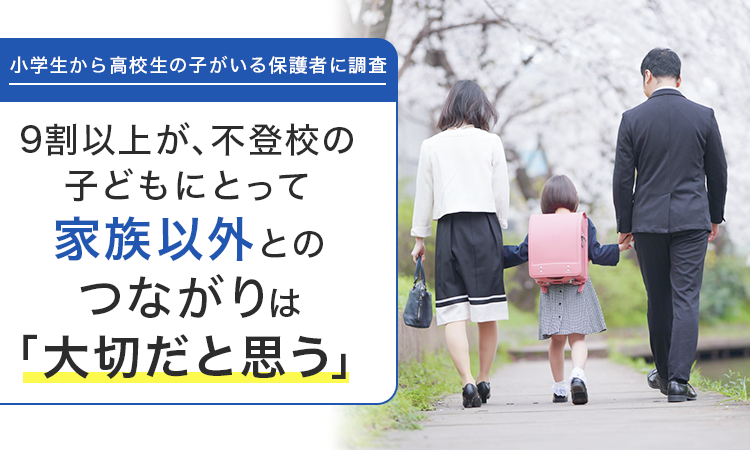
【小学生から高校生の子どもがいる保護者に調査】
9割以上が、不登校の子どもにとって家族以外とのつながりは「大切だと思う」2025年12月9日
-
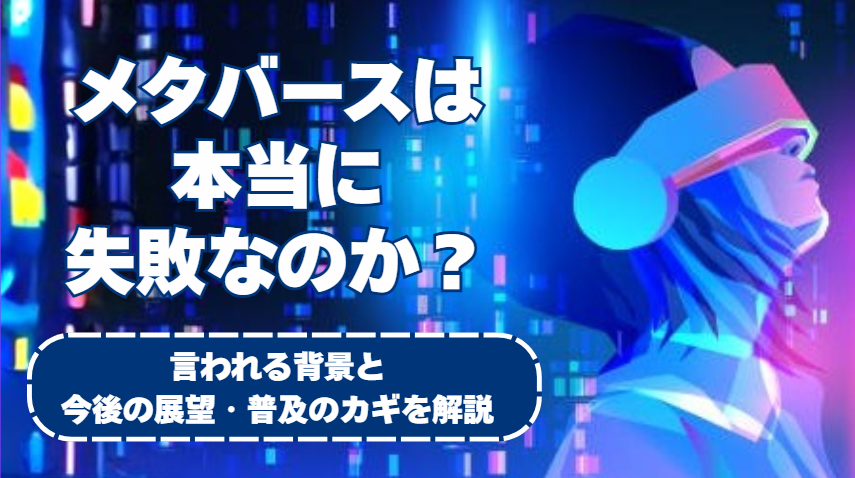
メタバースは本当に失敗なのか?
言われる背景と今後の展望・普及のカギを解説2025年11月21日
-

メタバースが「意味ない」と誤解されているのはなぜ?
その将来性を解説2025年11月21日
-

教育DXとは?教員・生徒・保護者それぞれのメリットと導入の進め方
2025年11月7日
-

【小学生から高校生の子がいる保護者に調査】
約2割の子どもが、「学校に行きづらさを感じている」
オンラインの活用に期待も2025年10月29日
-
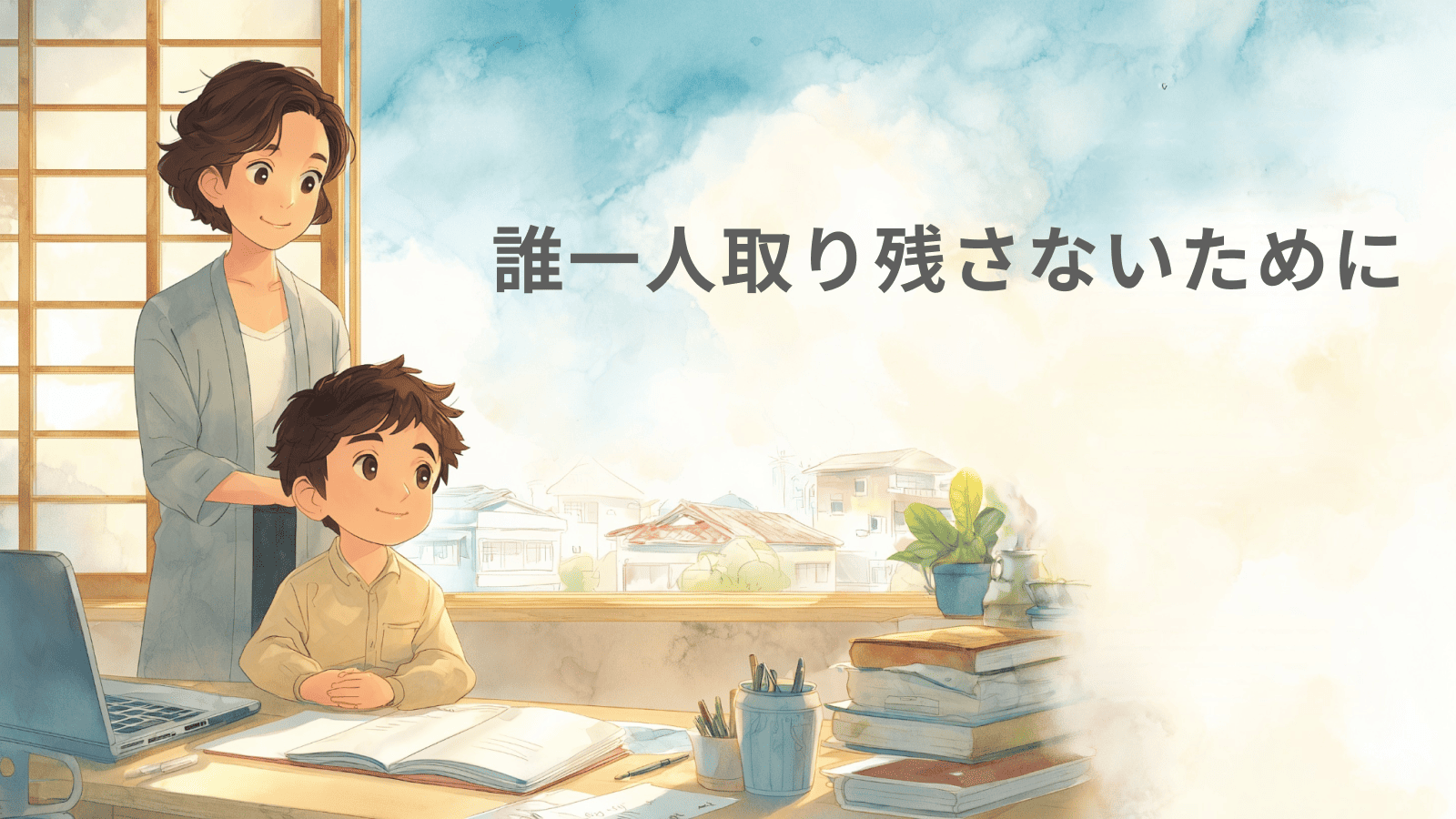
登校拒否とは?
不登校との違い、子どもへの効果的な対応・支援策を解説2025年10月24日
-
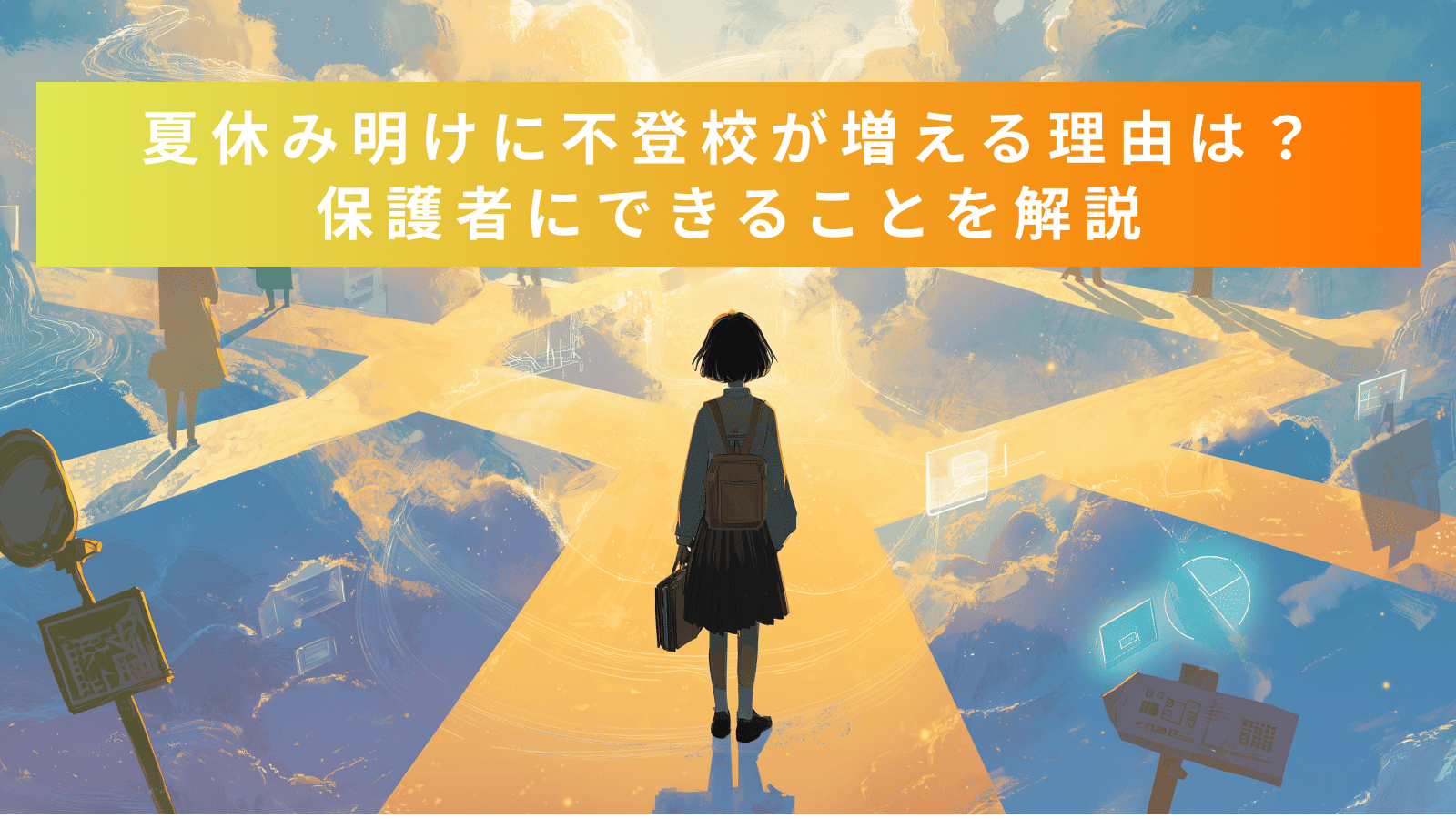
夏休み明け不登校はなぜ増えるのか。
その背景と実践的対応策2025年10月24日
FAMcampusにご興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください




富士ソフトのFAMシリーズ
FAM(Fujisoft Augmented Meetup)とは、
コミュニケーションを拡張し新たなつながりを
創出するサービスです。




