Column
夏休み明け不登校はなぜ増えるのか。
その背景と実践的対応策
2025年10月24日
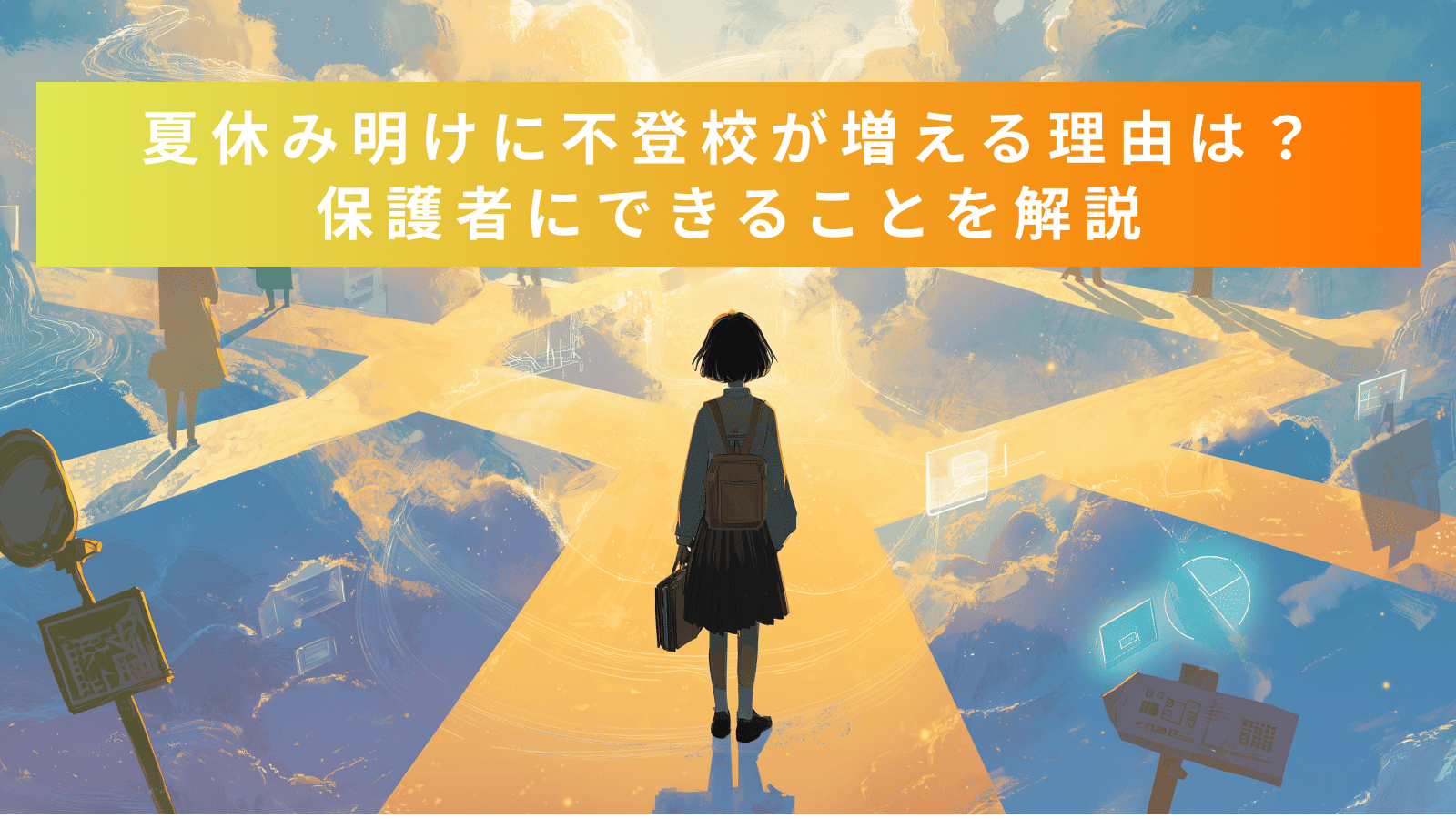
夏休み明けの不登校は、多くの家庭が直面する深刻な問題です。文部科学省の調査では、小・中学校の不登校児童生徒数は11年連続で増加し約34万6千人に達し、夏休み明けに「ほとんど学校に行っていない」子どもは約4割にのぼります。崩れた生活リズム、宿題への不安、人間関係の悩みなど、複数の要因が重なって起こるこの現象は、決して「甘え」ではなく心身が限界を訴えるSOSです。この記事では、不登校が増える背景から実践的な対応策まで詳しく解説します。
目次
夏休み明けに不登校が増加する実態
「9月1日問題」に象徴される長期休暇明けのリスク
夏休みが終わる9月1日前後は、子どもたちの心理的負担が年間で最も高まる時期として知られており、この現象は「9月1日問題」と呼ばれています。この時期は、不登校に関する相談が集中し、登校を渋る子どもたちが急増するデリケートな時期です。
長期休暇で朝型の生活リズムが崩れ、宿題や学習の遅れへの不安、人間関係の再構築への緊張が重なり、子どもは「行きたくない」「渋る」といったSOSを発し、不登校に関する相談が集中する時期です。
文部科学省が発表したデータによると、夏休み明けに「全く学校に行っていない」「ほとんど学校に行っていない」と回答した児童生徒は、小学生・中学生ともに全体の約4割(*1)に達しています。休み明けの登校渋りや欠席は、多くの子どもたちが抱える共通の課題なのです。
(*1)https://www.mext.go.jp/content/20211006-mxt_jidou02-000018318_03.pdf
令和5年度の調査では、小・中学校の不登校児童生徒数は11年連続で増加し約34万6千人に達し、高等学校の不登校生徒数も約6万9千人と過去最多となりました。この増加傾向は、夏休み明けの時期に特に顕著に表れます。
(*2) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00005.htm
9月1日が多くの学校で2学期が始まる日として設定されているため、子どもたちの「学校に行きたくない」という気持ちのピークがこの日に集中しやすくなります。長期休暇後は再び学校という場に戻らなければならないという現実に直面し、大きなストレスがのしかかるタイミングなのです。
春休み明けの4月や大型連休明けの5月にも不登校が増加する傾向があり、特定の日だけでなく「節目」の時期に子どもの心の変化を丁寧に見守る必要性が高まっています。長期休暇明けという環境の変化そのものが、子どもたちにとって大きなストレス要因となる可能性があります。
学校、教育委員会、そして保護者が9月1日問題を深刻に受け止め、夏休み明けという時期に特別な配慮と支援を行うことが求められています。早期のSOSサインの発見、相談しやすい環境づくり、そして「学校に行けない日があってもいい」という選択肢を示すことが、この時期における重要な対応策となります。
文部科学省が示す不登校の現状と定義
前述のように令和5年度の調査によると、小・中学校の不登校児童生徒数は11年連続で増加し約34万6千人に達し、高等学校の不登校生徒数も約6万9千人と過去最多となりました。在籍児童生徒に占める不登校児童生徒の割合は3.7%で、1000人当たりでは小学校で21.4人、中学校で67.1人(*3)に上っています。
(*3) https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
文部科学省は不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者」と定義しており、病気や経済的理由による欠席は含まれません。年間30日以上の欠席が不登校の基準とされています。
しかし、実態はこの統計以上に深刻です。定義上当てはまらないけれど同様の苦しさを抱える子どもたちもおり、「隠れ不登校」「不登校傾向」などと言われる児童生徒が存在します。保健室登校や遅刻・早退を繰り返す子ども、内心では「行きたくない」と感じながら登校している子どもなど、不登校予備軍とも言える児童生徒を含めると、実際の数はさらに多いと推測されます。
重要なのは、文部科学省が「不登校は、取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こり得るものとして捉え、不登校というだけで問題行動であると受け取られないような配慮が必要」と明言している点です。2019年の「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知では、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があるとしています。(*4)
(*4) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00005.htm
この方針転換は、不登校を単なる「怠け」や「甘え」と捉える従来の認識を改め、子どもたちの多様な学びの場を保障する姿勢を示すものです。学校現場や保護者にとって、不登校を「問題行動ではない」という認識を共有することが、子どもたちへの適切な支援の第一歩となるでしょう。
学年別・生徒タイプから見る不登校の特徴
小学生・中学生・高校生に共通する「休み明け」の心理
長期休暇中、子どもたちは学校という日常から解放され、自由な時間を過ごします。しかし、夏休み明けが近づくにつれて、共通して見られる心理変化があります。それは、学校生活への復帰に対する不安やプレッシャーの高まりです。
休み明けが近づくと、子どもたちは「また学校に行きたくない」「授業についていけるだろうか」という焦りを感じ始めます。文部科学省の調査でも、不登校児童生徒について「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった」が32.2%(*5)と最も多く、休み明けの登校への億劫さが顕著に表れています。
(*5) https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
特に1学期につらい経験をした子どもにとって、夏休みは心身の疲れを癒す期間である一方、2学期の始まりは再び苦痛と向き合う時期となります。人間関係の悩み、学習の遅れ、先生との関係など、休み前に抱えていた問題が解決されないまま残っていると、登校へのプレッシャーはさらに強まるのです。
特に注意が必要な小学一年生の「小1プロブレム」
小学一年生は「小1プロブレム」という言葉があるほど不安定な時期です。「小1プロブレム」とは、初めて経験する学校生活に上手く適応できず、心や身体のバランスを崩したり、問題行動を起こしたりすることを指します。
保育園・幼稚園では遊びが中心であった生活から、小学校では勉強中心への生活へと変化し、集団行動や時間割に基づいた規律を守ることが求められます。この急激な変化に対応できない子どもは、小1プロブレムを引き起こすリスクが高まります。
1学期の間に徐々に蓄積されたストレスは夏休みの間に一度和らぎますが、夏休み明けが近づくにつれて不安へと変化します。子どもにとって学校はしんどい場所だという認識になっていると、夏休み明けの登校が億劫になるのは自然なことです。授業中じっと座っていられない、先生の話を聞けないといった問題行動が、夏休み明けに再燃しやすく、不登校につながる可能性が高い時期なのです。
小学生の不登校の特徴
小学生の不登校は、心身の不調として表れやすいのが特徴です。「不安・抑うつの相談があった」が22.7%、「生活リズムの不調に関する相談があった」が24.5%と、心理的・身体的なSOSが顕著に見られます。(*6)
(*6) https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
腹痛や頭痛などの身体症状を訴えるケースが多く、本人も親も「病気かもしれない」と考えがちですが、実際には学校へ行くことへの不安が身体症状として現れています。担任の先生や友人関係、授業についていけないという焦りなど、小学生なりの悩みを抱えています。
また、小学生の不登校は保護者との関係性が大きく影響します。親に心配をかけたくない、叱られるのが怖いという思いから、本当の気持ちを言えず、朝になると体調不良を訴えるという形でSOSを出します。夏休みの宿題が終わっていないことへの罪悪感も、休み明けの登校渋りの一因となります。
中学生の不登校の特徴
中学生の不登校は、人間関係の悩みと進路への不安が複雑に絡み合うのが特徴です。「いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題の情報や相談があった」が14.4%(*7)と、小学生よりも高い割合となっています。
(*7) https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
思春期特有の自我の目覚めにより、友人からどう見られているか、自分の居場所があるかといった悩みが深刻化します。SNSでのやり取りが24時間続く現代では、夏休み中も人間関係から完全に離れることが難しく、休み明けへの不安が増幅されます。
また、受験や内申点への焦り、成績への プレッシャーも大きくなります。1学期の成績が思わしくなかった場合、「2学期こそ頑張らなければ」という気持ちと「またついていけないかもしれない」という不安が交錯し、無気力状態に陥ることがあります。親や先生からの期待を感じるほど、追い詰められていくケースも少なくありません。
理由5.高校生の不登校の特徴
高校生の不登校では「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった」が32.8%と最も多く、「生活リズムの不調に関する相談があった」が26.7(*8)%と、無気力感と生活リズムの乱れが顕著に表れます。
(*8) https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
高校生は義務教育ではないため、「学校を辞めればいい」という選択肢が視野に入ります。しかし、実際には進路や将来への不安から簡単に中退を決断できず、「行きたくないけど行かなければならない」という葛藤を抱えています。昼夜逆転の生活リズムになりやすく、夏休み中の夜更かしや依存的な過ごし方が、休み明けの登校をさらに困難にします。
通信制高校や定時制高校という選択肢もありますが、「普通の高校生活を送れなかった」という挫折感を持つこともあります。保護者も「せめて高校だけは卒業してほしい」と焦りを感じ、親子関係がぎくしゃくするケースも見られます。大人への移行期にある高校生にとって、自己肯定感の低下は深刻な影響を及ぼすため、長期的な視点での支援が必要です。
なぜ、夏休み明けに不登校になるのか?主な理由と心理
心身のエネルギー枯渇と学校負担の自覚
夏休み明けの不登校を理解する上で、最も重要な視点の一つが「頑張りの反動」です。1学期を通して、子どもたちは知らず知らずのうちに無理や緊張、疲れを溜め込んでいます。毎日登校し、授業を受け、友人や先生との人間関係を維持し、宿題をこなす——。これらの日常が、実は大きな心身の負担となっているのです。
1学期の間、子どもたちは「学校に行かなければならない」というプレッシャーの中で必死に頑張っています。特に、人間関係に悩みを抱えている子ども、授業についていけず焦りを感じている子どもにとって、学校生活は想像以上に過酷です。しかし、「休むわけにはいかない」という思いから、無理を重ねてしまいます。
そして夏休みを迎えると、プレッシャーから解放され、気が緩んだ途端、それまで抑え込んでいた疲労が一気に表面化します。ゆっくり過ごす中で、子ども自身が「学校生活がこんなにつらかったんだ」と自覚するようになるのです。
この自覚は、決して怠けや甘えではありません。むしろ、1学期を通して頑張り続けた結果、心身が限界を訴えているサインです。夏休み明けの不登校は、単なる「休み癖」ではなく、1学期の頑張りの反動として起こる現象なのです。
崩れた生活リズムの立て直しが困難
夏休み中、多くの子どもたちは夜更かしや朝寝坊といった生活パターンに陥ります。学校がないという解放感から、ゲームや動画視聴に没頭して深夜まで起きていたり、朝はゆっくり過ごしたりする生活が続きます。このような生活リズムの乱れは、一見すると些細なことのように思えますが、実は夏休み明けの不登校の大きな要因となります。
約1か月にわたって崩れた生活リズムを、学校再開と同時に急に元に戻すことは、子どもの心身にとって大きな負担です。特に昼夜逆転に近い状態になっている場合、朝起きられないという身体的な困難が生じます。無理に起こそうとしても本人は眠気と戦うことになり、登校する気力を失ってしまいます。
また、生活リズムの乱れは単なる身体の問題だけでなく、精神的な影響も大きいものです。不規則な生活は自律神経のバランスを崩し、やる気が出ない、気持ちが億劫になるといった無気力状態を生み出します。朝型の生活に戻せないことで、子ども自身も「自分はダメだ」と自己肯定感を失い、登校への意欲がさらに低下する悪循環に陥ります。
宿題や学習への不安
夏休みの宿題が終わっていないことは、子どもにとって夏休み明けの登校を大きくためらう原因となります。宿題が未完成のまま学校に行くことへの罪悪感や、先生に叱られるのではないかという不安が、登校を渋る要因となります。
また、1学期の授業についていけず学習の遅れを感じていた子どもにとって、2学期はさらに深刻です。「また授業についていけないのではないか」という不安が募ります。特に中学生や高校生は、成績や内申点、受験へのプレッシャーも加わり、学力への自信喪失が登校意欲を削いでしまいます。
2学期から始まる新しい学習内容やテストへのプレッシャーも見逃せません。難易度が上がる授業、定期テストの結果が進路に影響するという焦りが、子どもを追い詰めます。塾に通っている子どもでも、周囲との学力差を感じて自己肯定感を失うことがあります。
保護者が「宿題をやりなさい」「勉強しなさい」と躍起になって問い詰めると、かえって子どもを追い詰める結果となります。学習への不安は、単なる怠けではなく、学校生活全体への恐怖心と結びついているのです。
人間関係の再構築への恐れと不安
夏休みという長期の休みの間に、学校での友人関係がどう変化しているかという不安は、子どもにとって大きな心理的負担となります。「自分がいない間にグループの関係性が変わっているのではないか」「仲の良かった友達が他の子と親しくなっているかもしれない」といった漠然とした不安が、登校への足を重くさせます。
特に1学期に人間関係のトラブルを抱えていた子どもにとって、この不安はより深刻です。いじめやからかいを受けていた場合、夏休み明けに再びその状況に戻ることへの恐怖が強く、学校に行きたくないという気持ちを生み出します。
また、集団行動が苦手な子どもや、会話が得意でない子どもは、クラスの輪に入ることに大きなプレッシャーを感じます。夏休み中にSNSでのやり取りに参加できていなかった場合、「話題についていけない」「自分だけ浮いてしまう」という不安を抱えます。
こうした人間関係への不安は、本人にとって非常につらいものです。保護者が「友達に会えるよ」と声をかけても、子ども自身は友人関係に居場所を見出せず、むしろそれが苦痛の源となっているのです。
将来への漠然とした憂鬱
特に中学3年生や高校3年生といった卒業学年の子どもたちにとって、夏休み明けは進路選択や受験準備が本格化する時期です。2学期が始まると、担任や保護者から「そろそろ志望校を決めないと」「受験勉強を本気でやらないと」というプレッシャーが強まります。しかし、自分の将来が具体的にイメージできない子どもにとって、この圧力は大きな心理的負担となります。
成績や内申点への不安、「自分は受験についていけるのだろうか」という焦りが、学校に行きたくないという気持ちを生み出します。志望校選びに迷い、進路が定まらないまま夏休みを過ごした子どもは、現実と向き合うことが億劫になり、登校を渋るようになるのです。
また、高校生の場合、通信制高校や定時制高校という選択肢があることを知りながらも、「今の学校を辞めたら負けだ」という思いと、「このまま無理を続けられない」という葛藤を抱えます。将来への不安と現在のつらさが交錯し、無気力状態に陥りやすくなります。
こうした将来への憂鬱は、単なる怠けではなく、子ども自身が抱える深刻な悩みです。保護者や教師が躍起になって進路を問い詰めると、かえって子どもを追い詰める結果となります。
不登校の予兆を把握する:子どもが発する「SOS」のサインを見逃さないために
身体症状に表れる心の不調
子どもの心の不調は、しばしば身体症状として表れます。特に登校時間が近づくと、頭痛や腹痛、吐き気などを訴えるケースが多く見られます。朝になると「お腹が痛い」「頭が痛い」と言い出し、学校を休むと症状が治まるというパターンは、心理的なストレスが身体に表れているSOSのサインです。
これは単なる仮病ではなく、本人が本当につらい症状を感じています。学校に行くことへの不安や恐怖が、無意識のうちに身体症状を引き起こしているのです。保護者が「また仮病か」と責めたり叱ったりすると、子どもはさらに追い詰められてしまいます。
また、食欲不振や慢性的な疲労感も見逃せないサインです。元気がなく、好きだった食事も進まない、常に疲れている様子が続く場合は要注意です。これらは起立性調節障害など、自律神経の乱れが原因である可能性もあります。
こうした身体症状が続く場合は、心身の健康状態を専門家に相談することが重要です。精神科医やメンタルクリニック、スクールカウンセラーなどに早めに相談し、適切な対応を取ることが子どもの回復への第一歩となります。
行動や言動の変化
外出や人との交流を避ける傾向
夏休み前後の期間に、子どもが疲労や不安から外出を嫌がったり、家族以外の人に会うことを避けたりするようになることがあります。以前は友人と遊ぶことを楽しみにしていたのに、誘いを断るようになったり、家に引きこもりがちになったりする場合は要注意です。
特にゲームや動画視聴など、自宅でできる活動に没頭し、現実逃避するような様子が見られることもあります。これは学校生活への不安から目を背け、安心できる環境に留まろうとする心理の表れです。依存的な過ごし方が続く場合は、子どもが抱える不安やストレスのサインとして捉える必要があります。
口数が減る、会話を避ける
元々よく話していた子どもが急に無口になったり、学校の話題になると表情が曇ったりする変化は、心に不安や葛藤を抱えているサインです。「学校どうだった?」と聞いても「別に」「普通」としか答えなくなり、会話を避けるようになります。
保護者や先生が心配して問い詰めたり、無理に聞き出そうとしたりすると、かえって子どもは心を閉ざしてしまいます。口数が減っているときは、無理に話させるのではなく、安心できる関わりを重ねることが大切です。一緒に過ごす時間を持ち、子どもが自分から話したくなるまで待つ姿勢が求められます。
ひとりで抱え込む
宿題を全くやろうとしない、あるいは締め切り間際になっても手につかないといった様子は、単なる勉強の面倒臭さだけでなく、学校そのものへの抵抗感が宿題に表れている場合があります。夏休みの宿題が終わっていないことへの罪悪感や、やらなければならないというプレッシャーが、かえって子どもを動けなくさせてしまうのです。
保護者が「宿題やりなさい」と叱ったり、躍起になって責めたりすると、親子関係が悪化し、子どもはさらに追い詰められます。宿題への抵抗は、学校に行きたくないという気持ちの表れであることを理解し、無理強いしないことが重要です。
睡眠・起床の困難
夜なかなか寝付けなかったり、夜中に何度も目が覚めたりする、あるいは朝起きられないなど、睡眠リズムの乱れが顕著になることも不登校の予兆です。夜更かしや昼夜逆転の生活パターンに陥り、朝型の生活リズムを取り戻せなくなります。
学校への不安や緊張が強いと、夜になっても気持ちが落ち着かず、眠れなくなることがあります。また、朝起きる時間が近づくと無意識に体が拒否反応を示し、起きられなくなるケースもあります。これらは心身が発するSOSであり、生活リズムの問題だけでなく、根本的な不安やストレスに対処する必要があります。
保護者がすべき実践的対応:焦らないことが回復への第一歩
強制的な登校を避け、子どもの気持ちを受け止める
無理に登校を迫ったり叱ったりしますと、本人を追い詰めてしまい、学校生活そのものへの不安や無気力を強めます。まずは「行きたくないんだね」と受け止め、休む選択もあり得ると伝えます。不登校は問題行動ではなく、誰一人取り残さない学びを保障する対象と示されていますので、在籍校や教育相談センター、スクールカウンセラーと連携しながら、保護者が一人で抱え込まない体制を整えることが回復への近道になります。出席扱いの仕組みや学校外の学びも含め、早めに情報を集めます。
家庭を「安心できる居場所」にすることの重要性
外の人間関係や授業のプレッシャーで心身がつらいとき、家庭が責められない、ありのままの自分でいられる居場所になることが重要です。休み明けや2学期の不安が強い時期ほど、「休む=悪い」ではなく、安心して気持ちを話せる場を用意します。自己肯定感が崩れると登校再開の意欲が下がりやすいため、できたことを具体的に言葉で評価し、小さな成功体験を積み上げます。学校側にも「家庭では落ち着いて過ごせている」など様子を共有し、チームで支援する体制をつくります。
親子間の建設的なコミュニケーション
会話が学校一色になると、子どもは「問い詰められている」と感じやすくなります。好きなゲームや文化祭、日常の小さな出来事など、学校以外の話題も織り交ぜて口数を取り戻せる場をつくります。事実確認→気持ちの反射→共感→選択肢の提案、の順で対話し、「いつから行ける?」ではなく「今つらい要因は何?」と焦点化します。担任やスクールカウンセラーとも面談の目的を共有し、本人のペースを尊重するスタンスを家庭・学校でそろえます。
生活リズムの段階的な再構築
夏休みの夜更かしや昼夜逆転で乱れた生活リズムは、一気に戻そうとすると反発や体調不良を生みます。まずは「起床を15分ずつ前倒し」「朝の光を浴びる」「朝食を一口でも摂る」など、段階的に整えます。朝起きられない背景に起立性調節障害など自律神経の不調が潜む場合もありますので、腹痛・頭痛・倦怠感が続くときは医療や学校の保健室に相談し、出席扱いの調整や保健室登校などの柔軟な登校形態も検討します。
学習サポートは「無理なく、できる範囲で」
学力や宿題の遅れは焦りを生み、登校を渋る要因になりがちです。短時間×毎日(例:10分×3回)を基本に、達成できたら一緒に喜びます。家庭教師や個別指導、オンライン学習など、本人に合う学びの選択肢を柔軟に組み合わせます。学校外の学びを在籍校の出席扱いにできる制度や、教育支援センター、フリースクールとの連携も確認し、負担を下げながら「学び続けている実感」を育てます。
保護者自身のメンタルケアと社会とのつながり
不登校は親御さんにも大きな不安と孤独を生みます。睡眠・食事・休養の基本を守り、信頼できる大人同士の会話や支援団体の情報交換で視野を保ちます。自治体の教育相談、精神保健福祉センター、メンタルクリニックなど専門家への相談は「弱さ」ではなく、子どもを守る具体策です。学校・家庭・地域が「チーム」で動く方針は国の施策でも示されていますので、遠慮なく相談先を増やします。
長期的な視点で見守る姿勢
回復は波を伴います。登校再開→欠席→保健室登校→部分的参加→また欠席、という揺り戻しは珍しくありません。短期の成績や内申点だけに囚われず、心身の回復と居場所の維持、学びの継続を中長期で見通します。COCOLOプランが示すように、学校の風土改善やいじめ対応、授業改善といった環境側の要因にも目を向け、本人を責めるのではなく仕組みで支える発想を持ち続けます。学期の区切りや進路の節目は支援を厚くし、再発予防の計画を共有します。
学校・教育委員会が取り組んでいる不登校支援の例
学校内の「居場所」の多様化と安心できる環境整備
文部科学省は「COCOLOプラン」に基づき、校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム)の設置促進と機能強化を進めています。従来の教室だけでなく、保健室登校や別室登校など、子どもが安心して過ごせる多様な居場所を学校内に公式に認め、活用しやすい環境を整備することが重要です。
教室に入ることが難しい児童生徒にとって、保健室や相談室、図書室などは心理的な安全が確保された居場所となります。また、学校に来られなくてもオンライン等で授業や支援につながることができるよう環境の整備も進められています。
こうした取り組みにより、子どもたちは自分のペースで学校生活に関わることができ、徐々に教室への復帰を目指すことが可能になります。スクールカウンセラーや養護教諭、担任が連携して、一人ひとりの状況に応じた支援を提供することで、不登校からの回復を支えています。
学校外の「学びの場」と「居場所」の活用
フリースクール、教育支援センター(適応指導教室)
フリースクールは、学校とは異なる環境で、子どものペースに合わせた学習や人との関わりを経験できる居場所です。民間の支援団体が運営し、不登校の子どもたちが安心して過ごせる環境を提供しています。集団行動が苦手な子どもや、学校の授業についていけない子どもにとって、プレッシャーを感じずに学びを続けられる選択肢となります。
教育支援センター(適応指導教室)は自治体が運営する公的な支援機関で、2023年時点で全国に1743カ所設置されています。教育支援センターでは、在籍校との連携により、通所日数が出席扱いになる場合があります。スクールカウンセラーや教育相談の専門家が配置され、学習支援だけでなく、心理的なサポートも受けられる点が特徴です。
ただし、2023年度で教育支援センターを活用できている割合は、不登校児童生徒の8.8%(*1)にとどまっており、ニーズに答え切れていない現状があります。保護者は、子どもに合った環境を見つけるために、複数の選択肢を検討することが大切です。
(*9) https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
令和5年の全不登校児童生徒数346,482人と教育支援センターの利用者数30,365人より算出
個別指導塾やオンライン学習サービス
個別指導塾は、子どもの学力やペースに合わせて柔軟に学習を進められる場です。集団授業が苦手な子どもでも、マンツーマンや少人数での指導により、自分のペースで勉強できます。学習の遅れに対する焦りや不安を抱える子どもにとって、無理なく学力を取り戻す手段となります。
また、自宅におけるICT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数は10,467人(*10)となっており、オンライン学習サービスの活用も広がっています。自宅で学習しつつ、出席扱い制度に繋がるオンライン教材を活用することで、学校に行けない期間も学びを継続できます。
(*10) https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_1_2.pdf
家庭教師も同様に、子どもの状況に合わせた個別サポートを提供できる選択肢です。本人の様子を見ながら、無理のない範囲で学習を進めることができ、保護者の不安も軽減されます。
通信制高校や定時制高校(高校生の場合)
高校生の不登校の場合、通信制高校や定時制高校という選択肢があります。これらは不登校経験がある生徒も受け入れやすく、柔軟な学習スタイルを提供しています。
通信制高校は、登校日数が少なく、自宅での学習を中心に高校卒業資格を取得できます。生活リズムが乱れている生徒や、人間関係に不安を抱える生徒にとって、自分のペースで学べる環境は大きなメリットです。オンライン授業を活用する通信制高校も増えており、全国どこからでも受講できます。
定時制高校は、夜間や午後からの授業が中心で、昼夜逆転の生活リズムを抱える生徒でも通いやすい選択肢です。少人数制で、一人ひとりに寄り添った教育支援が行われており、進路や受験についても丁寧にサポートを受けられます。
これらの選択肢を知ることで、保護者も子どもも「学校に行けない=将来がない」という思い込みから解放され、自分に合った学びの道を見つけることができます。
メタバース空間が提供する「新たな居場所」
外出負担なく交流できるバーチャル教育空間
夏休み明けに不登校になった子どもの多くは、外出すること自体に大きな心理的負担を感じています。文部科学省の実証事業では、不登校児童生徒の約6割が引きこもり状態にあり、従来の教育支援センターのように児童生徒が実際に足を運ぶことを前提とした支援では届きにくい実情があります。
こうした子どもたちに対して、メタバース空間を活用した教育支援が新たな選択肢として注目されています。FAMcampus(https://famcampus.jp/)のような教育メタバースでは、自宅にいながらアバターを通じて他の児童生徒や先生と交流し、授業を受けることが可能です。FAMcampusは教育用に設計された仮想空間内で学習活動を展開でき、仲間や先生の存在が身近に感じられる環境を提供しています。
2023年の実証事業では、利用した子どもの65%に変化が見られ、「興味の幅が広がった」「自信がついた」「学校へ行きたいと思うようになった」といった自発性の高まりが報告されています。メタバース空間には自宅にいながらでもアクセスでき、登校に不安を感じる子どもや体調不良で学校に通えない子どもでも無理なく参加できることが特徴です。
「メタバースって不登校支援で使えるの?」
文部科学省実証で検証されたFAMcampusの成果をご紹介します。
通信環境とパソコンやタブレットがあれば参加でき、アバターを通じて授業に参加したり、休憩スペースで友だちと会話したりと、学校生活に近い体験ができます。朝型の生活リズムを整えるきっかけにもなり、昼夜逆転や生活の乱れに悩む子どもにとって、外出せずとも社会とつながる居場所となっています。
まとめ:子どもと向き合い、未来を拓くためのメッセージ
不登校は「通過点」であり「甘えではない」
夏休み明けに子どもが学校に行けなくなったとき、「怠けているのではないか」と不安になるかもしれません。しかし、文部科学省が「不登校を問題行動と判断してはならない」という通知を出しているように、不登校であること自体は決して「問題」ではありません。
子どもは「学校に行かなければならない」ことを理解しており、欠席するのは気軽な気持ちからではなく、今の生活の何かに限界を感じているということです。不登校は心身のエネルギー枯渇によるSOSであり、決して甘えではないのです。文部科学省の通知でも、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがあると示されています。この時期を子どもの成長の「通過点」と捉え、焦らず長期的な視点で見守ることが回復への第一歩となります。
早期の行動と専門家への相談の重要性
子どもがSOSのサインを見せ始めたら、親だけで抱え込まず、早期に専門機関に相談することが重要です。まずは在籍校と十分に連絡を取ることが重要です。担任や養護教諭、スクールカウンセラーに相談することで、保健室登校などの個別対応を検討できます。
また、教育委員会が設置する教育相談センターや教育支援センターでは、専門家による無料相談を受けられます。必要に応じて精神科医やメンタルクリニック、民間の支援団体も活用しながら、子どもに合った支援を見つけていくことが大切です。早期に適切な支援につながることで、子どもも保護者も心のエネルギーを取り戻しやすくなります。
学校に行かなくても、子どもが自信を持って成長できる社会へ
現代社会では、学校という枠を超えて多様な学びの場が存在しています。フリースクール、教育支援センター、オンライン学習、通信制高校や定時制高校など、子どもが自分のペースで学べる選択肢が広がっています。メタバースを活用したバーチャル教育空間など、新しい教育の形も生まれています。
不登校は個人と環境のミスマッチに過ぎず、学ぶことそのものに不適合なわけでは決してありません。子どもは自分の特性にマッチした環境に置かれると、いきいきと輝き出します。夏休み明けに学校に行けなくなっても、子どもの未来が閉ざされるわけではありません。一人ひとりに合った居場所と学びの形を見つけることで、子どもたちは自己肯定感を取り戻し、自信を持って成長していけるのです。
夏休み明け不登校に関するよくある質問(FAQ)
Q1. なぜ夏休み明けに不登校が増えるの?
長期休暇で崩れた生活リズム、宿題や学習遅れへの不安、人間関係の再構築ストレスが重なりやすい「9月1日問題」により、心理負荷がピーク化するためです。
Q2. これは“甘え”ではないの?
いいえ。心身のエネルギー枯渇が出すSOSです。「学校に行けない日があってもよい」という前提で回復を支えます。
Q3. 不登校の定義は?
病気や経済的理由以外の要因で、登校しない/したくてもできない状態。年間30日以上の欠席が基準ですが、定義未満の「隠れ不登校」も実在します。
Q4. 学年別の特徴は?
小学生:腹痛・頭痛など身体症状や生活リズム乱れが目立つ。
中学生:友人関係・SNS・内申や受験への不安が増幅。
高校生:無気力化と昼夜逆転が顕著、進路葛藤が強い。
それ以外の要因も考えられるため、あくまでよくある兆候として参考にしてください。
Q5. 小1プロブレムって?
遊び中心→学習中心への急変に適応できず、行動・情緒が不安定化。夏明けに再燃しやすい要注意時期です。
Q6. 見逃しやすい“予兆”は?
登校前の腹痛・頭痛、食欲低下、慢性疲労/外出回避、口数減少、宿題への強い抵抗、睡眠障害(夜更かし・早朝覚醒・起床困難)など、病気や機嫌の問題としてみてしまい見逃しやすいです。
Q7. 保護者が最初にすべきことは?
登校強要をやめ、「行きたくない気持ち」を受け止める。学校(担任・養護教諭・SC)へ早期連絡し、家庭だけで抱え込まない体制を作ります。
Q8. NG対応は?
「なぜ行けない?」の詰問、根性論・励まし一辺倒、即登校の強制、宿題の叱責のみ、放置・無関心などは避けましょう。
Q9. 家庭での環境づくりは?
“責めない・急かさない”安心の居場所に。小さな達成を具体語で承認し、自己肯定感を回復させます。
Q10. 生活リズムはどう戻す?
一気に戻さず段階的に:起床を15分ずつ前倒し+朝光を浴びる+朝食一口から。症状が続くなら医療や保健室に相談し、保健室登校なども検討するとよいでしょう。
Q11. 学習フォローのコツは?
「短時間×毎日(例:10分×3)」で可視化し、達成の共有。個別指導・オンライン学習・教育支援センターやフリースクールの併用も有効です。
Q12. 相談先はどこ?
在籍校(担任・養護教諭・スクールカウンセラー)、教育相談センター/教育支援センター、医療機関、地域NPOや親の会。早めに相談し、併走してもらうのが解決への近道です。
Q13. 学校・教育委員会は何をしている?
COCOLOプラン等で保健室・別室・校内支援センターの整備、オンライン併用、専門職(SC/SSW)活用を推進。多職種連携で個別支援を強化中。
Q14. 学校外の選択肢は?
フリースクール、教育支援センター、個別塾・オンライン学習、(高校生は)通信制・定時制など。出席扱い制度の活用余地もあります。
Q15. メタバース支援は役立つ?
外出が難しい子でも、アバターで安全に交流・学習へ参加可能。匿名性・非対面性が心理的安全を高め、生活リズム再建の足がかりにもなります。
Q16. 回復の見通しは?
「進む→戻る」を繰り返す波状回復が普通。短期の成績に固執せず、中長期の心身回復・居場所維持・学び継続を軸に支えましょう。
他の教育メタバースコラム
-
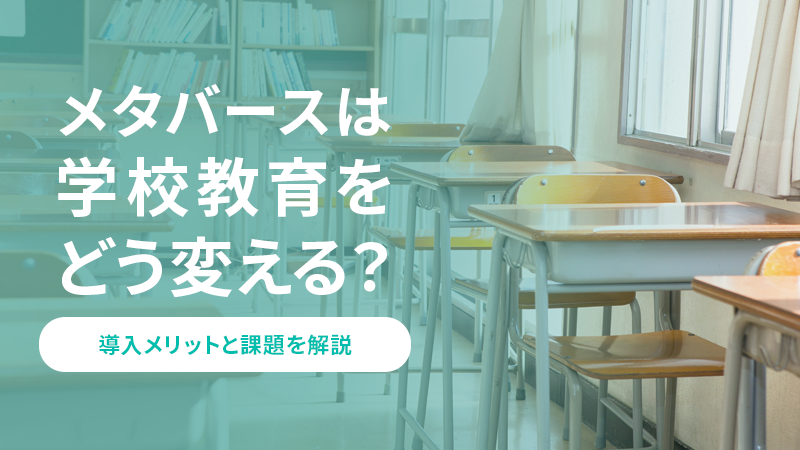
メタバースは学校教育をどう変える?
導入メリットと課題を解説2025年12月23日
-

自治体のメタバース活用事例11選
地方創生や教育支援での動向を解説2025年12月23日
-
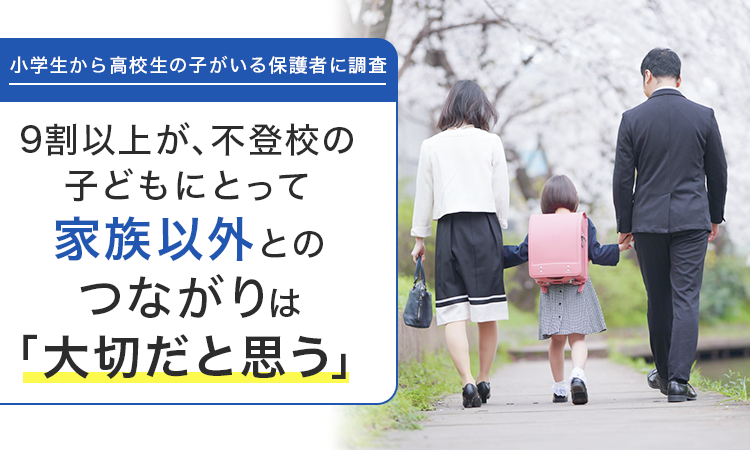
【小学生から高校生の子どもがいる保護者に調査】
9割以上が、不登校の子どもにとって家族以外とのつながりは「大切だと思う」2025年12月9日
-

メタバースとは?
VRとの違いや活用方法・課題まで分かりやすく解説2025年11月21日
-
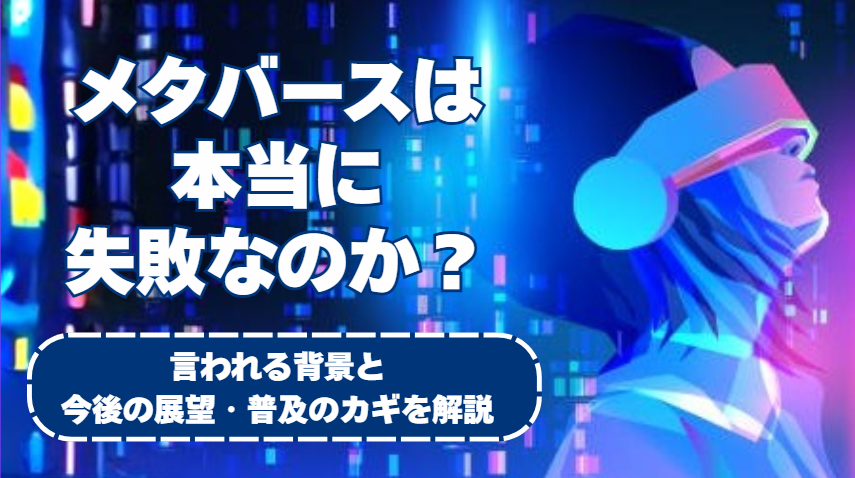
メタバースは本当に失敗なのか?
言われる背景と今後の展望・普及のカギを解説2025年11月21日
-

メタバースが「意味ない」と誤解されているのはなぜ?
その将来性を解説2025年11月21日
-

教育DXとは?教員・生徒・保護者それぞれのメリットと導入の進め方
2025年11月7日
-

【小学生から高校生の子がいる保護者に調査】
約2割の子どもが、「学校に行きづらさを感じている」
オンラインの活用に期待も2025年10月29日
-
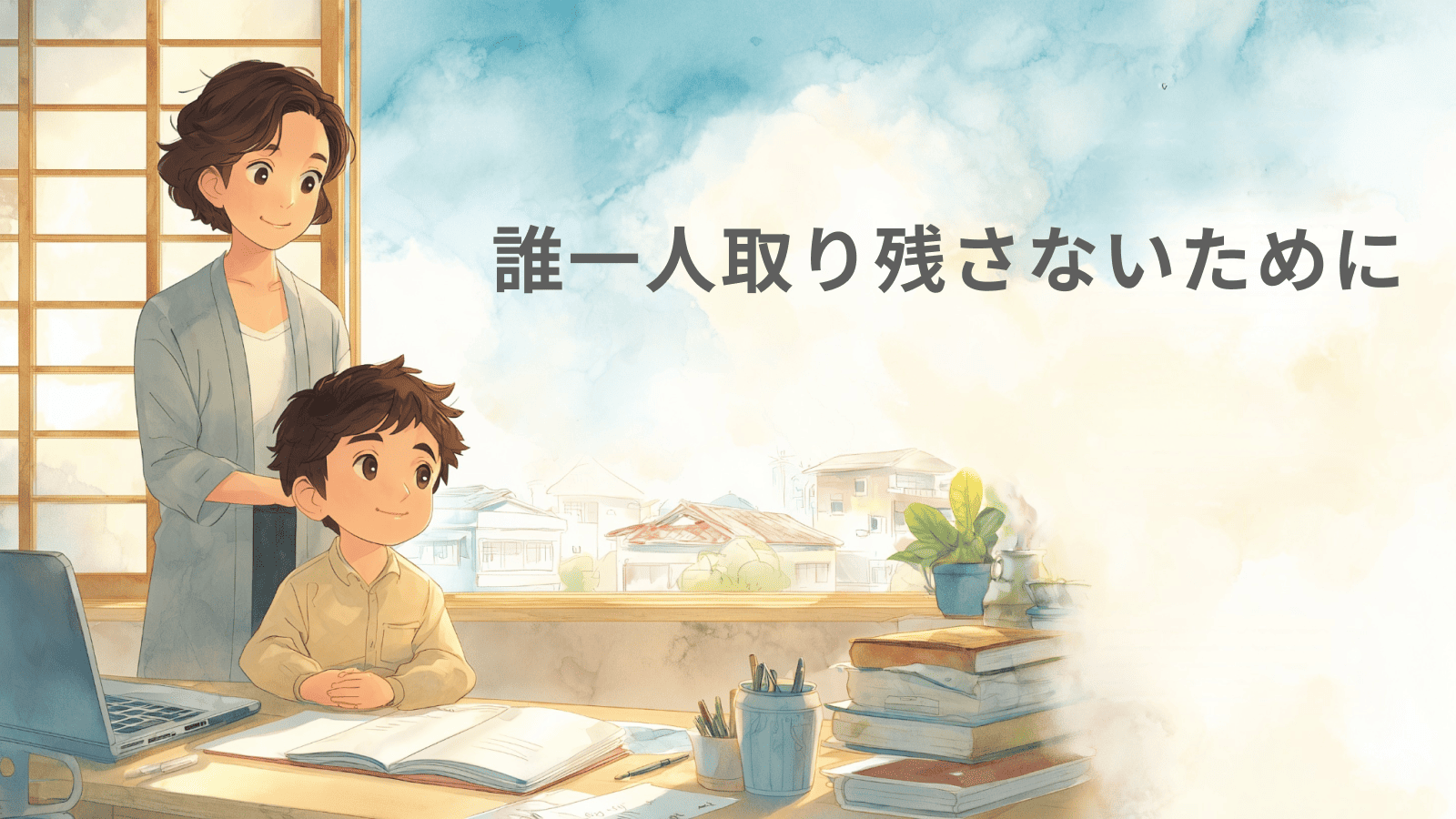
登校拒否とは?
不登校との違い、子どもへの効果的な対応・支援策を解説2025年10月24日
FAMcampusにご興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください




富士ソフトのFAMシリーズ
FAM(Fujisoft Augmented Meetup)とは、
コミュニケーションを拡張し新たなつながりを
創出するサービスです。




