Column
登校拒否とは?
不登校との違い、子どもへの効果的な対応・支援策を解説
2025年10月24日
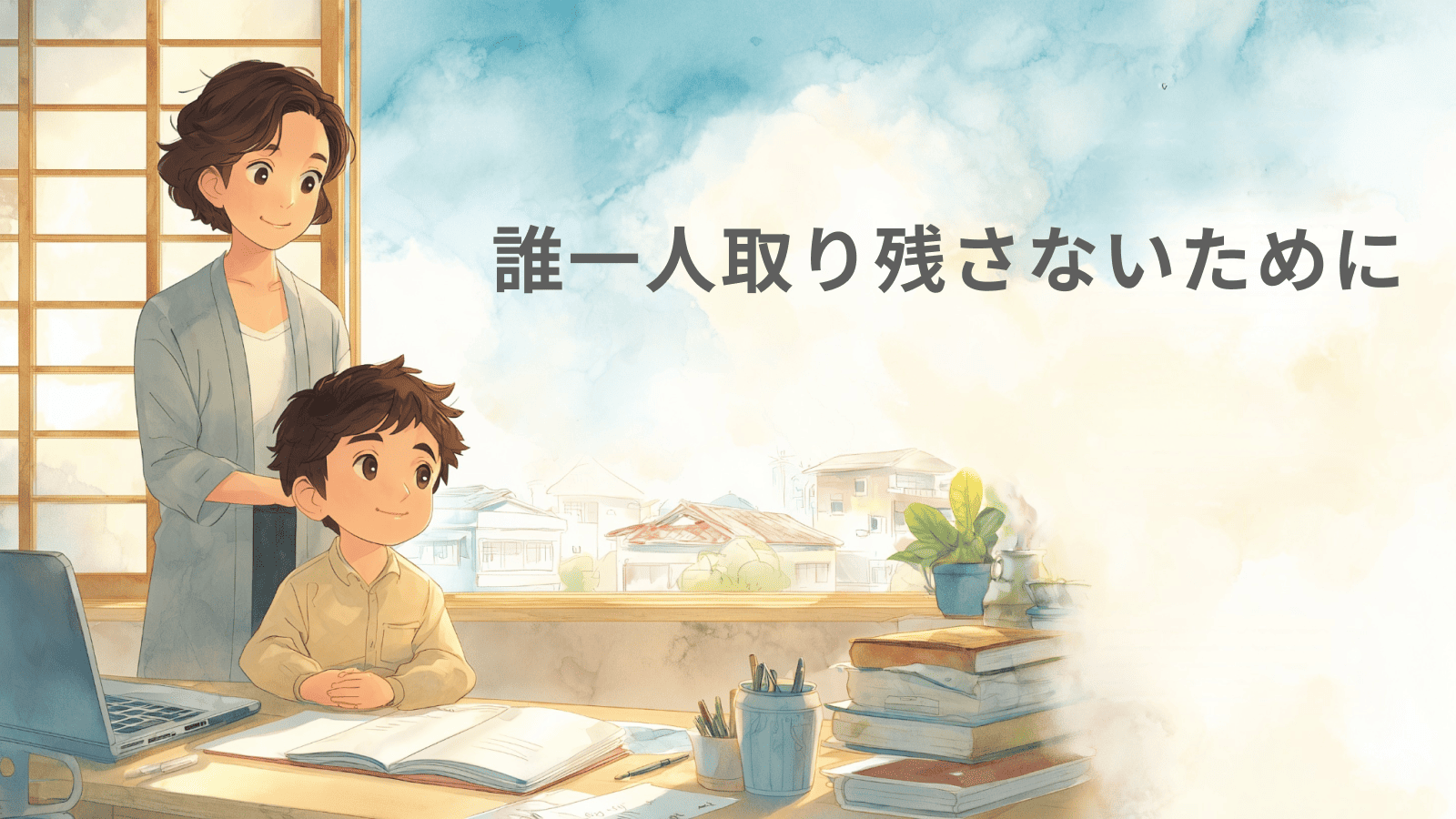
34万人を超えた不登校児童生徒への対応は、すべての教育関係者にとって喫緊の課題です。本記事では、登校拒否・不登校の最新実態と背景要因から、効果的な対応の原則、学校と外部機関の連携、多様な進路選択まで徹底解説。現場で活かせる実践的な知識を、データと事例に基づいて包括的にお届けします
目次
登校拒否と不登校の基本理解:用語の変遷と現在の定義
教育現場で「登校拒否」と「不登校」という言葉を耳にすることは多いでしょう。この二つの用語は、現在ではほぼ同じ意味で使われていますが、実は時代とともに変遷してきた歴史があります。ここでは、「登校拒否」という言葉の歴史的な位置づけと、「不登校」への変遷、そして現在の公的な定義を明確にし、基本的な理解を深めます。
歴史的背景と用語の変遷
学校に通わない児童生徒を指す用語は、時代の教育観や社会認識を反映しながら変化してきました。
明治後期や大正期など古い時期には「怠学」という言葉が使われ、学校を休む行為そのものを怠けや非行として捉える風潮がありました。その後、1941年にアメリカの研究者A.M.ジョンソンが「学校恐怖症(School phobia)」という概念を提唱し、日本でも1960年頃からこの用語が使われるようになりました。この時期、学校に行けない状態は「大きな不安で学校へ行けない症状」として精神医学的な観点から理解され始めたのです。
1970年代から1990年代初頭にかけては、「登校拒否」という言葉が主流となりました。しかし、「拒否」という言葉には「学校に行くことを意図的に拒んでいる」「反学校的」といったニュアンスが含まれており、子どもに烙印を押す効果や、本人の意志とは異なる誤解を招くという問題が指摘されるようになりました。
そして1990年代以降、教育現場の意識変化とともに「不登校」という用語が積極的に使用されるようになります。1992年に文部省(当時)が「特別な子どもが不登校になるわけではなく、どの子でも不登校になりうる」という通達を発表したことは、不登校理解の大きな転換点となりました。1998年には文部科学省の統計において、それまで使われていた「学校嫌い」という分類が正式に「不登校」に変更されています。
厳密には「登校拒否」と「不登校」は異なる概念として議論されることもありますが、日常的にはほぼ同じ意味で使われているのが現状です。「不登校」という用語は、「登校しない」だけでなく「登校したいけどできない」という状況も包含しており、より中立的で包括的な表現として定着しました。
文部科学省における現在の定義
現在、文部科学省は「不登校児童生徒」を明確に定義しています。同省の調査における定義は以下の通りです。
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」
この定義における重要なポイントは、年間30日以上の欠席という具体的な基準です。これは連続した30日ではなく、年度内の累積欠席日数を指します。つまり、たとえ時々登校できる日があっても、合計で30日以上欠席していれば不登校に該当することになります。
また、厚生労働省のe-ヘルスネットでは、登校拒否/不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く)」と定義しており、文部科学省の定義とほぼ同様の認識が共有されています。
この定義から読み取れるのは、不登校は単なる「怠け」や「わがまま」ではなく、複合的な要因によって生じる状態であるという理解です。心理的要因には無気力や不安が、情緒的要因には対人関係のストレスが、身体的要因には起立性調節障害などが、社会的要因には家庭環境や学校の体制が含まれます。これらが複雑に絡み合って、児童生徒が登校できない状況を生み出しているのです。
教育関係者として押さえておくべきは、2025年現在、不登校児童生徒数は小中学校で34万人を超え、過去最多を更新し続けているという事実です。もはや「特別な子ども」の問題ではなく、どのクラスにも起こりうる現象として捉え、適切な理解と支援体制を整えることが求められています。
【参考文献】
https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/yougo/1267642.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/不登校
https://new-schoooool.jp/futoukoutoha/
https://www.hikipos.info/entry/2023/03/30/070000
https://medical.jiji.com/column5/255
https://kohoken.chobi.net/cgi-bin/folio.cgi?index=sch&query=/notice/19920924.txt
登校拒否・不登校の最新実態と背景要因
最新のデータに基づき、登校拒否・不登校の現状を把握し、その多様な原因を年齢層別に深く掘り下げて解説します。特に、現場での見極めが難しいとされる要因にも焦点を当てます。
全国統計と増加傾向
文部科学省が2024年10月に公表した令和5年度(2023年度)の調査結果によると、小中学校における不登校児童生徒数は34万6482人に達し、過去最多を更新しました。これは前年度の29万9048人から47,434人(15.9%)の増加となり、11年連続の増加です。初めて30万人を突破し、35万人に迫る深刻な状況が続いています。
学校種別で見ると、小学校では13万370人(前年度比2万5258人増)、中学校では21万6112人(前年度比2万2176人増)となっています。在籍児童生徒に占める割合は、小学校で2.1%、中学校で6.7%です。これを1,000人あたりの不登校児童生徒数で表すと、小学校では21.4人、中学校では67.1人となり、全体では37.2人という結果です。つまり、小学校では約47人に1人、中学校では約15人に1人が不登校という計算になり、30人クラスであれば中学校では1クラスに2〜3人程度の不登校生徒が存在することになります。
高等学校においても不登校生徒数は68,770人(前年度比8,195人・13.5%増)と過去最多を更新しており、在籍生徒に占める割合は2.4%となっています。小学生の不登校は10年前と比較して約5.4倍、中学生は約2.2倍に増加しており、もはや不登校は特定の児童生徒だけの問題ではなく、誰にでも起こりうる状況として教育現場全体で捉える必要があります。
年齢・学年別の主な原因と特徴
文部科学省の令和5年度調査結果によると、小中学校の不登校児童生徒について把握した事実として、「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった」が32.2%と最も多く、続いて「不安・抑うつの相談があった」が23.1%、「生活リズムの不調に関する相談があった」が23.0%となっています。このように、「無気力・不安」が最も多い原因ですが、その背景には学年や発達段階によって異なる要因が潜んでいます。ここでは、小学生、中学生、高校生で異なる上位原因について詳細に解説します。
小学校低学年における特有の要因と心理
小学校低学年、特に1〜2年生における登校拒否の最大の特徴は、母子分離不安です。親から離れることに言葉では説明できないような強い不安が生じ、登校できなくなります。母親以外の人との接触に抵抗を示すようになりますが、母親と一緒であれば元気に過ごすことができるという特徴があります。
また、小学校入学は環境の大きな変化を伴います。幼稚園や保育園とは異なり、集団行動への適応、授業への集中、時間割に沿った行動など、求められることが格段に増えます。この環境変化に適応できず、漠然とした不安を抱える児童が少なくありません。 身体症状として現れることも低学年の特徴です。登校前になると頭痛や腹痛を訴え、実際に体調不良の症状が出現します。これは心理的ストレスが身体化したもので、決して仮病ではありません。このような身体症状は、子ども自身も原因を言語化できない心のSOSとして理解する必要があります。
中学生・高校生に顕著な社会的・心理的要因
中学生・高校生になると、思春期特有の複雑な要因が絡み合います。最も顕著なのは人間関係の複雑化です。友人関係は小学生時代よりも深く、グループ内の力関係や立場の変化に敏感になります。いじめを除く友人関係をめぐる問題の相談が13.3%を占めており、部活動における先輩後輩関係のストレスも無視できません。
学業レベルの急激な変化も大きな要因です。中学校では学習内容が抽象的になり、定期テストの重要性も増します。高等学校では、進学やクラス替え等に伴う不適応の増加が指摘されており、学業不振や頻繁な宿題の未提出が15.2%に上ります。
さらに、進路不安と自己肯定感の低下が顕著です。高校生では特に、将来への漠然とした不安や、自分の存在価値に対する疑問が登校意欲の低下につながります。思春期は自己アイデンティティを形成する時期であり、「自分は何者なのか」「将来どう生きるのか」という問いに答えられないことが、無気力状態を引き起こすのです。
見過ごされがちな潜在的要因:発達特性と心身の不調
登校拒否や不登校の背景には、見過ごされがちな心身の不調や発達特性が隠れているケースが少なくありません。不登校児童生徒の57%にASD(自閉症スペクトラム障害)やADHDなどの発達障害が見られるという調査結果もあり、発達特性が登校困難の重要な要因となっています。
文部科学省の令和4年調査では、通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態が明らかにされ、ADHDや自閉症スペクトラム障害、学習障害などの特性が、集団生活への適応困難につながる可能性が示されています。
また、起立性調節障害が中学生の約10%に見られ、不登校の約3-4割に併存していることが報告されています。朝起きられない、立ちくらみといった症状は、思春期特有の自律神経の不調が原因であり、医療的支援が必要だと考えられます。
さらに、令和5年度調査では、不登校児童生徒からの相談内容として「不安・抑うつ」が23.1%を占め、うつ病や不安障害といった心理的問題も見逃せません。
教育現場では、これらの発達特性や心身の不調を早期に見極め、医療機関やスクールカウンセラーなどの専門職と連携した支援体制の構築が不可欠です。
家庭環境が不登校に与える影響
文部科学省の調査によると、不登校の原因として「家庭に係る状況」が10%を超えています。しかし、直接的な家庭要因以外のケースにも、家庭環境が間接的に影響している可能性が指摘されています。
親の養育態度は、子どもの登校意欲に大きく影響します。過保護な接し方は子どもの自己肯定感や自立心を育む機会を奪い、成長を阻害する可能性があります。また、過度な期待やプレッシャー、逆に関心の低さやコミュニケーション不足も、子どもが孤立感を深める要因となります。
家庭内の不和も見過ごせません。夫婦間の対立や離婚といった環境は、子どもの心理的安定を損ない、登校困難につながることがあります。
経済的困窮も重要な要因です。就学援助の利用率は2022年度で13.90%と高い水準にあり、経済的状況が子どもの学びの機会に影響を与えていることが明らかです。さらに、児童虐待相談対応件数は2024年度に約243,000件と推定され、虐待環境が不登校の背景にあるケースも存在します。
教育現場では、家庭環境の課題を早期に把握し、スクールソーシャルワーカーや児童相談所などの関係機関と連携した包括的な支援が求められます。
【参考文献】
https://www.inochimusubu-ie.or.jp/post/20241001
https://www.mext.go.jp/content/20231004-mxt_jidou01-100002753_1.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ojjscn/49/4/49_255/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/40/7/40_KJ00002387470/_article/-char/ja/
https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_1_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
https://megaphone.school-voice-pj.org/2025/05/post-2265/
https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
https://kizuki.or.jp/blog/others/sad/
https://tokyo-yagaku.jp/futoukou/approach/schoolchild/
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2022/1421569_00005.htm
https://www.jisinsin.jp/general/typical_diseases/起立性調節障害/
https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ojjscn/49/4/49_255/_article/-char/ja/ https://zento.work/gtn/family-problems/
https://www.u-master.net/column/refusal/1037/
https://gooddo.jp/magazine/poverty/children_proverty/75/
登校拒否に対する効果的な対応の原則
登校拒否や不登校に直面した子どもへの対応において、親や教員の関わり方は回復の鍵を握ります。ここでは、子どもが安心して自己を再構築できるよう、親や教員が実践すべき対応の原則と、避けるべき行動を具体的に解説します。
親・教員が避けるべきNG行動
子どもが「学校行きたくない」と言ってきた時、これは親から見れば「問題が始まった」時かもしれませんが、子どもにとっては最終段階です。多くの子どもは、親に言いづらいとモヤモヤを抱えながら、決心して伝えています。
この段階で無理な登校の強要や、「なぜ行けないの?」といった過度な問い詰めは、子どもの精神状態を悪化させます。原因が解決していないのに学校へ登校させたり、甘やかしすぎたりすることも避けるべきです。また、「頑張れば大丈夫」といった一方的な励ましや、過剰な期待も子どもを追い詰める要因となります。
逆に、子どもとの距離を置きすぎることも問題です。無関心な態度は、子どもに「自分は見捨てられた」という孤立感を与えます。適切な距離感を保ちながら、子どもの状態を見守る姿勢が求められます。
心の休息を優先する環境作り
子どもの心の声に耳を傾け、ストレスを乗り越えられる考え方や、安全地帯としての環境を整えることが重要です。子どもが安心して休める「居場所」の提供が最優先事項となります。
具体的には、子どもの感情を否定せず、「つらかったね」「よく話してくれたね」と肯定的に受け止めることが大切です。子どもが達成しようとする姿勢を見てあげること、たとえ決めたことができなかったとしても、取り組もうとした意欲を褒めてあげることで、自己肯定感を育むことができます。
また、学校のイベントの話、友達の話、定期テストの話など、学校関係の話題は子どもが聞いてくるまで親から伝えるのはやめておくことが推奨されます。これらの話題は聞くだけでストレス要因となり、不登校を悪化させる恐れがあります。頑張った過程を認め、子どもの感情を受け止める声かけが、心の安定につながります。
生活リズムの再構築と活動の促進
令和5年度の文部科学省調査では、小中学校で「生活リズムの不調に関する相談があった」が23.0%、高等学校では26.7%となっています。また、2024年3月公表の調査では「昼夜逆転など生活リズムが大きく乱れた」が23.9%と報告されており、昼夜逆転は心身の健康を損ない、社会復帰のハードルを高めます。
生活リズムの改善には、朝は太陽の光を浴び、夜は暖かみのある照明を使用するなど、適切な光の管理を心がけることが効果的です。体内時計は光の影響を強く受けるため、朝の太陽光は生活リズムを整える上で重要な役割を果たします。また、日中の活動を増やし、適度な運動を取り入れることも心身の健康維持に不可欠です。
ゲームや遊びといった趣味活動は、ストレス発散の手段として認めつつも、いきなり「スマホもゲームもダメ!」と言わず、徐々に使う時間を短くするなど、子どもが自分で納得してルールを守れるようになることが大切です。昼夜逆転は無理に直そうとするとかえって悪化する場合があるため、焦らず子どものペースに合わせた対応が求められます。
子どもが「話せるタイミング」を待つ対話の工夫
子どもに無理に理由を聞き出そうとせず、子どもが自ら話したくなるような安心できる環境を整えることが重要です。子どもとざっくばらんに会話をし、昼夜逆転の問題について一緒に考えていく、子どもの気持ちに寄り添い共に解決策を探っていく姿勢が求められるとされています。
具体的な方法として、一緒に料理をする、散歩をする、趣味の活動を共有するなど、共同作業中の自然な会話の機会を設けることが効果的です。こうした場面では、子どもも心理的な壁が低くなり、自分の気持ちを話しやすくなります。対面で向き合うよりも、同じ作業をしながら横並びで会話する方が、子どもにとって話しやすい環境となります。
また、スクールカウンセラーは子どもだけでなく保護者のカウンセリングも行っており、まずは親としてカウンセリングを受けて気持ちを安定させ、子どもとの関わり方を工夫できるようにすることが大切です。専門家の支援を積極的に活用することで、親自身の不安も軽減され、より適切な対応が可能となります。
【参考文献】
- https://megaphone.school-voice-pj.org/2025/05/post-2265/
- https://toco.mom/current-state-of-school-absence-in-japan-mext-2024-data/
- https://branchkids.jp/articles/b327
- https://www.seisekiup.net/column/refusal/1703/
- https://zento.work/gtn/nighthawk/
- https://sanyokai-clinic.com/kokoro/futoko-navi/?p=198
- https://kokoro-soudan.jp/column/day-night-reversal/
- https://www.willschool.net/column/column000019-html
- https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
- https://www.mext.go.jp/content/20240322-mxt_jidou02-000028870_02.pdf
登校拒否に対する学校現場と外部機関との連携体制強化
文部科学省は「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」を策定し、学校内での支援体制に加え、専門的な外部機関との連携強化を推進しています。2023年度の調査では、不登校児童生徒の約4割が学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない状況であり、多角的な連携体制の構築が急務となっています。
学校教職員による初期対応とチーム支援
登校拒否への対応では、担任教諭だけでなく、学年主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、管理職が連携した組織的な対応が不可欠です。文部科学省は「チーム学校」での素早い支援を推奨しており、定期的なケース会議を通じて児童生徒の現状、家庭状況、支援方針を共有します。養護教諭は保健室登校の支援や医療機関との連携において中心的役割を果たし、特別支援教育コーディネーターは発達障害など特別な支援が必要な児童生徒の個別支援計画作成を担当します。家庭訪問では複数の教職員で訪問し、登校を強要せず、学校とのつながりを維持することを主眼とします。
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用
2025年度から、スクールカウンセラーを全公立小中学校へ配置、スクールソーシャルワーカーは全中学校区への配置体制を整備する方針が示されています。スクールカウンセラーは心理の専門家として、不安障害やうつ病などの精神的問題を抱える児童生徒へのカウンセリングを行います。一方、スクールソーシャルワーカーは社会福祉の専門家として環境調整を担い、支援内容では不登校が26.0%、家庭環境が21.8%と合計で半数近くを占めています。児童相談所や福祉事務所などとの連絡調整を行い、家庭の経済的困窮や虐待が疑われるケースでの多機関連携において中核的役割を果たします。
教育支援センター(適応指導教室)の役割と活用
2023年時点で全国に1,743カ所設置されている教育支援センターは、個別指導による学習支援と社会的自立を目的とした公的機関です。教員免許保持者が学校の教科書を用いて児童生徒のペースに合わせた学習を進め、小集団でのスポーツやレクリエーションを通じてコミュニケーション能力を養います。在籍する児童のほとんどが元の在籍校で出席扱いになっているため、学習機会と出席日数の確保が可能です。校内教育支援センターは2024年時点で全国の46.1%の公立小・中学校に設置されており、今後も拡大していく見込みです。
医療機関との適切な連携
登校拒否の背景には身体的・精神的疾患が関与するケースがあります。起立性調節障害、機能性消化管障害などの身体疾患、ADHD、自閉スペクトラム症などの神経発達症、不安症、強迫性障害、うつなどの精神疾患が挙げられます。児童精神科では不安障害、うつ病、摂食障害、発達障害などを対象としており、最近は不登校でひきこもっている児童の受診が目立っています。養護教諭や管理職から適切なタイミングで受診を勧め、保護者の同意を得て診断結果や治療方針を共有し、医療機関からの指示に基づいた教育的配慮を行うことが重要です。
地域・民間の支援団体・親の会との協働
不登校児童生徒の約4割にあたる13万人超は何の相談・指導も受けていない状況であり、フリースクール、NPO、親の会などとの協働が不可欠です。東京都では、フリースクール等の利用料に月額最大2万円の助成金を支給する制度を2024年から実施しています。親の会は全国に400団体以上あり、保護者同士が悩みを共有し、思いを分かち合える場となっています。文部科学省は2024年に全国200自治体を対象に、相談窓口の強化や保護者への情報提供といった取り組みへのサポートを開始しており、地域の支援資源マップの作成と定期的な更新、支援機関との顔の見える関係構築が求められています。
【参考文献】
- https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00005.htm
- https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1397802_00005.htm
- https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm
- https://www.mext.go.jp/content/20250711-mxt_jidou02-000008592_2.pdf
- https://megaphone.school-voice-pj.org/2025/05/post-2265/
- https://junior.litalico.jp/column/article/104/
- https://note.com/mirimiri111_/n/nce5c3305c541
- https://www.mext.go.jp/content/20250711-mxt_jidou02-000008592_2.pdf
- https://job-medley.com/tips/detail/896/
- https://kizuki.or.jp/blog/others/educational-support-center/
- https://kokoro-soudan.jp/column/kyoikusiencenter/
- https://korokoro-nisshi.com/about-education-support-center/
- https://kohnodai.jihs.go.jp/subject/100/010/jidouseisin.html
- https://www.jisinsin.jp/general/typical_diseases/不登校/
- https://hmhc.jp/diagnosis/hikarinomori/children_heart/
- https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2025/20251006-116119.html
- https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/about/gaiyou/0000002459
- https://futoko-net.org/
- https://miraitizu.com/parent-meeting
- https://www.kyobun.co.jp/article/2024120302
将来を見据えた学びと進路の多様な選択肢
登校拒否や不登校の児童生徒が将来の選択肢を狭めないよう、学力維持、進学、キャリア形成に向けた具体的な道筋と、既存の枠にとらわれない学びの場の可能性を提示します。従来の学校教育の枠組みだけでなく、通信制高校やオンライン学習など多様な教育機会を活用することで、すべての児童生徒に社会的自立への道が開かれています。
出席日数・学力評価の現状と柔軟な対応
小中学校では進級や卒業を認定する上で出席日数は絶対に必要な条件ではなく、校長先生の裁量で卒業が認められます。一方、高校の進級には年間授業日数の3分の2以上の出席が必要とされ、60~70日以上の欠席があると進級は困難です。ただし、フリースクール、教育支援センター、オンライン学習、家庭学習などが出席扱いの対象となり、学校側の承認により出席日数を確保できます。2024年8月には学校教育法施行規則が改正され、一定の要件の下で不登校児童生徒の学習の成果を成績評価できることを法令上明確化されました。不登校期間中の学力維持・向上策としては、自宅学習、学習塾、家庭教師の活用が有効です。
不登校特例校・単位制高校・通信制高校の活用
学びの多様化学校(不登校特例校)の全国展開の動き、単位制高校や通信制高校といった柔軟な教育課程を持つ学校のメリット、そして高卒認定試験を活用した進路選択について、教育現場の実態を踏まえながら詳述します。登校拒否や不登校の児童生徒にとって、多様な学びの選択肢が広がっています。
不登校特例校の役割と全国展開の動き
学びの多様化学校(不登校特例校)は、2025年4月現在、全国に58校が設置されており、将来的には300校の設置が目指されています。2004年に東京都八王子市立高尾山学園に初めて設置され、2005年には学校教育法施行規則の一部改訂により全国で設置の動きが進み、2023年に現在の名称に変更されました。
学びの多様化学校では、不登校児童生徒の実態に配慮した特別な教育課程を編成し、授業時間数の削減、登校時間の調整、少人数制、ICT活用など、個々の児童生徒に合わせた柔軟な学びを提供します。文部科学省は2027年度までに全ての都道府県と政令市に少なくとも1校以上設置する目標を掲げていますが、財政面や制度運用の知識不足などがネックとなっています。
通信制高校・オンライン学習のメリットと課題
通信制高校の生徒数は2024年度で290,087人と過去5年で1.5倍に増加し、2025年度には30万5221人と初めて30万人を超え、全国の高校生の約10人に1人が通信制課程の生徒となっています。
通信制高校は、通学負担の軽減、自分のペースでの学習、多様なカリキュラムの選択など、登校拒否や不登校の生徒にとって大きなメリットがあります。オンライン授業やレポート提出により、自宅学習がメインとなるため、体調や心理状態に合わせた柔軟な学びが可能です。高等教育においても、2024年4月から、不登校となっている高校生の卒業支援を目指し、オンライン授業による単位認定制度が導入されました。
一方で課題も存在します。通信制高校の中退率は5.8%と全体の1.4%に比べて高く、特に公立の通信制高校では学習サポートが手厚くないため、卒業率が50%を切る学校もあります。自律的な学習にはモチベーションが必要であり、サポート校の活用が重要となります。また、生徒数や学校数が増えるなか、教職員配置や施設・設備の水準が、制度で定められた基準を十分に満たしていないケースや、サテライト施設・協力校等の運用実態が把握しづらい形態も報告されており、文部科学省は2023年に認可基準を新たに作成し、教育の質の確保に取り組んでいます。
「社会的自立」に向けた包括的な支援
平成28年に教育機会確保法が成立し、平成29年に国が策定した基本指針では、学校への登校という結果のみを目標にせず、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的自立をめざすとの方針を明確化しています。登校拒否や不登校への対応において、単に学校復帰を目指すだけでなく、児童生徒の将来の社会的自立を視野に入れた長期的な支援が不可欠です。
不登校経験者は、その後ひきこもり状態に陥るリスクが高いことが指摘されています。学校に通えない期間が長期化すると、対人関係のスキルや社会性を身につける機会が制限され、進路選択の幅が狭まる可能性があります。
教育委員会や学校現場には、学力維持だけでなく、就労支援、生活支援、心理的サポートを含む包括的な支援体制の構築が求められています。たとえば、横浜市の教育支援センターでは、創作活動やスポーツ体験活動等を通し、自己肯定感と相互の信頼関係を育み、社会的自立に向けた相談・支援を実施しています。児童生徒一人ひとりの特性や状況に応じた個別の支援計画を策定し、学校、家庭、医療機関、福祉機関、民間支援団体が連携して、当事者の社会的自立を継続的に支えることが重要です。
参考文献
https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/soudan/kyoikusoudan/futoukousien.html
https://www.shingaku-fs.jp/tsunaguba/column/attendance_system/syussekiatukai-kiji
https://jyukumado.jp/column/113
https://www.going-100ten.com/column/refusal/study/1946/
https://sudachi.support/blog/futoukou/resolve/definition-30/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00005.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387004.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387008.htm
https://note.com/itbs_unschool/n/n2d6d27ad28bc
https://jp.weforum.org/stories/2025/02/what-japans-inclusive-school-systems-can-teach-us-about-resilience/
https://www.city.setagaya.lg.jp/01300/1395.html
https://www.kyobun.co.jp/article/2025060391
https://megaphone.school-voice-pj.org/2025/05/post-2265/
https://koichigo7.com/school-list-all/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387008_00001.htm
https://id.ikubunkan.ed.jp/blog/refusal/special-school/
https://souken.shingakunet.com/research/2025/04/182024.html
https://www.try-gakuin.com/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD214YQ0R20C25A8000000/
https://www.r-ac.jp/column/tsushin/seitosu/
https://sudachi.support/blog/futoukou/juniorhighschool/cyugaku-futoukou-tusinseikoukou/
・https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2025/109823/education
https://toyokeizai.net/articles/-/810382
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230721000167008.html
https://www.mext.go.jp/content/20231122-mxt_koukou02-100002270_02.pdf
教育メタバースを活用した登校拒否への支援の可能性
登校拒否や不登校に悩む児童生徒への新たな支援策として、教育メタバースを活用した取り組みが2025年現在、全国の自治体で広がりを見せています。富士ソフトの教育メタバース「FAMcampus」は、文部科学省の実証事業に4年連続で採択され、神奈川県、名古屋市、奈良県など25自治体で導入が進んでいます。
FAMcampusの特徴は、通学負担がゼロで、仲間の存在を感じながら学習や交流ができる点です。効果的な運営に不可欠な、「メタバース空間」「子どもの特性に配慮したカリキュラム」「専門性を備えた講師」「不登校支援専門員」の4要素を揃えています。教育メタバースは、外出が困難な状態にある児童生徒に対して、心のエネルギーを回復させる居場所を提供し、社会的自立へとつなぐ重要な選択肢として期待されています。
「メタバースって不登校支援で使えるの?」
文部科学省実証で検証されたFAMcampusの成果をご紹介します。
まとめ:子どもと未来のために、多角的な視点での支援を
2025年現在、小中学校における不登校児童生徒数は34万6482人と過去最多を更新し、11年連続で増加を続けています。もはや登校拒否や不登校は「特別な子ども」の問題ではなく、誰にでも起こりうる状況として、教育現場全体で受け止める必要があります。
本記事で見てきたように、登校拒否・不登校の背景には、無気力や不安といった心理的要因、いじめや友人関係といった社会的要因、ADHDや自閉症スペクトラム障害などの発達障害、起立性調節障害などの身体的要因、さらには家庭環境に至るまで、複雑に絡み合った多様な要因が存在します。文部科学省は「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」を策定し、包括的な支援体制の構築を推進しています。
効果的な支援には、学校教職員によるチーム支援、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといった専門職の活用、教育支援センター(適応指導教室)や医療機関との連携、そしてフリースクールや親の会といった地域・民間支援団体との協働が不可欠です。保護者は子どもの心の休息を優先し、過度な登校強要を避けながら、生活リズムの再構築を支援し、子どもが話せるタイミングを待つ対話の工夫が求められます。
進路の選択肢も多様化しています。学びの多様化学校(不登校特例校)は2025年4月現在58校に拡大し、通信制高校の生徒数は30万5221人と全国の高校生の約10人に1人が通信制課程の生徒となっています。さらに、教育メタバースという新しい支援の形も登場し、外出が困難な児童生徒に対する居場所と学習機会を提供しています。 教育機会確保法では、学校への登校という結果のみを目標にせず、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて社会的自立を目指すとの方針が明確化されています。登校拒否や不登校は、決して子どもの怠けやわがままではありません。当事者である子ども一人ひとりの状況に寄り添い、学校・家庭・地域、そして医療・福祉が連携しながら、柔軟で多角的な支援を提供することで、すべての児童生徒が自分らしい学びと成長の道を見つけることができるのです。
こうした子どもたちに対して、メタバース空間を活用した教育支援が新たな選択肢として注目されています。FAMcampus(https://famcampus.jp/)のような教育メタバースでは、自宅にいながらアバターを通じて他の児童生徒や先生と交流し、授業を受けることが可能です。FAMcampusは教育用に設計された仮想空間内で学習活動を展開でき、仲間や先生の存在が身近に感じられる環境を提供しています。
2023年の実証事業では、利用した子どもの65%に変化が見られ、「興味の幅が広がった」「自信がついた」「学校へ行きたいと思うようになった」といった自発性の高まりが報告されています。メタバース空間には自宅にいながらでもアクセスでき、登校に不安を感じる子どもや体調不良で学校に通えない子どもでも無理なく参加できることが特徴です。
通信環境とパソコンやタブレットがあれば参加でき、アバターを通じて授業に参加したり、休憩スペースで友だちと会話したりと、学校生活に近い体験ができます。朝型の生活リズムを整えるきっかけにもなり、昼夜逆転や生活の乱れに悩む子どもにとって、外出せずとも社会とつながる居場所となっています。
登校拒否・不登校に関するFAQ(要約版)
Q1. 「登校拒否」と「不登校」はどう違うのですか?
A1. 「登校拒否」は1970〜1990年代に使われた表現で、「学校を拒む」という否定的な印象を与えることがありました。現在はより中立的な「不登校」という言葉が主流で、「登校したくてもできない」状況も含む概念です。文部科学省は「心理的・情緒的・身体的・社会的要因により、年間30日以上欠席する児童生徒」と定義しています。
Q2. 不登校の子どもはどのくらいいるのですか?
A2. 令和5年度(2023年度)の調査によると、不登校の小中学生は 34万6,482人(過去最多・11年連続増)に達しています。小学生の約47人に1人、中学生の約15人に1人が不登校であり、もはや「特別な子ども」ではなく一般的な現象になっています。
Q3. 不登校の主な原因は何ですか?
A3. 最も多いのは「無気力・不安(32.2%)」で、次に「不安・抑うつ」「生活リズムの乱れ」が続きます。
背景要因には以下のようなものがあります:
・小学校低学年:母子分離不安・環境変化
・中高生:友人関係・学業不振・進路不安
・発達特性:ASD・ADHDなど
・身体的要因:起立性調節障害など
・家庭要因:過保護、経済的困窮、家庭不和など
Q4. 保護者や教員が避けるべき対応はありますか?
A4. 登校を無理に強要したり、「なぜ行けないの?」と詰問するのは逆効果です。
また、「頑張れば大丈夫」などの励ましや、無関心な態度も避けましょう。
大切なのは「心の休息」と「安心できる居場所」を整え、子どもの気持ちを肯定的に受け止めることです。
Q5. どのような支援体制がありますか?
A5. 文部科学省は「COCOLOプラン」に基づき、学校と外部機関の連携を強化しています。
・学校:チーム学校体制、保健室登校、個別支援計画
・外部機関:スクールカウンセラー(全小中学校配置予定)、スクールソーシャルワーカー(全中学校区配置予定)
・教育支援センター(全国1,743か所):出席扱いの学習支援
・医療機関・児童相談所・NPO・親の会との連携も推進中です。
Q6. 学びや進路にはどんな選択肢がありますか?
出席日数だけで進級・卒業が決まるわけではなく、フリースクールやオンライン学習も出席扱いとなる場合があります。
さらに次のような選択肢が広がっています。
- 不登校特例校(2025年4月時点で58校)
- 通信制高校(生徒数30万人超)
- オンライン学習・高卒認定試験の活用
教育機会確保法により、「学校復帰だけを目的としない社会的自立支援」が重視されています。
Q7. 教育メタバースとは何ですか?
A7. 教育メタバースは、仮想空間で学習・交流を行う新しい教育支援手法です。
富士ソフトの「FAMcampus」は文科省の実証事業に4年連続採択され、全国25自治体で導入されています。
外出が難しい児童生徒にも、安心して学び続けられる「新しい居場所」として注目されています。
Q8. 不登校の子どもにとって大切な支援の考え方は?
A8. 不登校は怠けではなく、複合的なストレス反応です。
学校・家庭・地域・医療・福祉が連携し、子どものペースを尊重しながら支援することが大切です。
目標は「登校」そのものではなく、「社会的自立」と「自分らしい学び」の実現です。
他の教育メタバースコラム
-
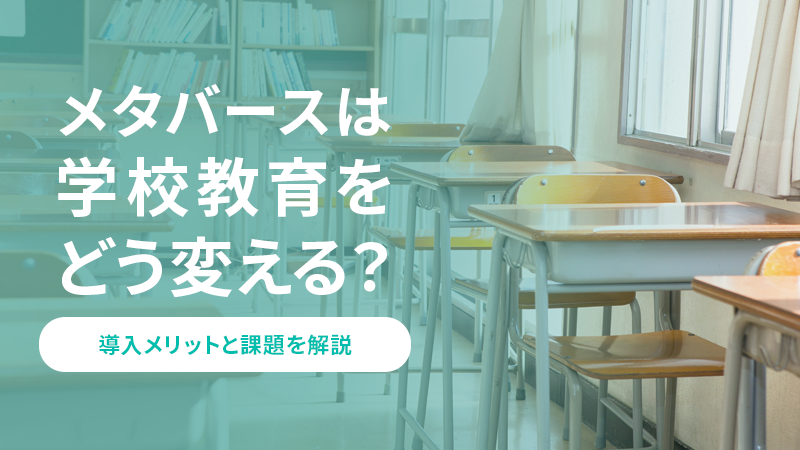
メタバースは学校教育をどう変える?
導入メリットと課題を解説2025年12月23日
-

自治体のメタバース活用事例11選
地方創生や教育支援での動向を解説2025年12月23日
-
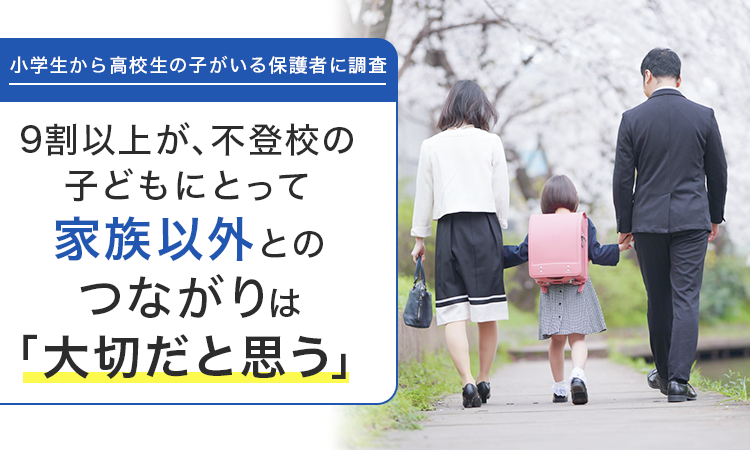
【小学生から高校生の子どもがいる保護者に調査】
9割以上が、不登校の子どもにとって家族以外とのつながりは「大切だと思う」2025年12月9日
-

メタバースとは?
VRとの違いや活用方法・課題まで分かりやすく解説2025年11月21日
-
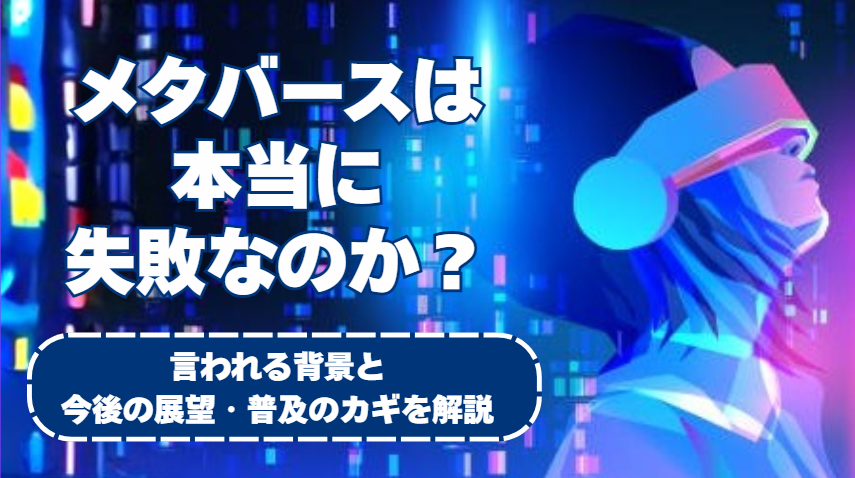
メタバースは本当に失敗なのか?
言われる背景と今後の展望・普及のカギを解説2025年11月21日
-

メタバースが「意味ない」と誤解されているのはなぜ?
その将来性を解説2025年11月21日
-

教育DXとは?教員・生徒・保護者それぞれのメリットと導入の進め方
2025年11月7日
-

【小学生から高校生の子がいる保護者に調査】
約2割の子どもが、「学校に行きづらさを感じている」
オンラインの活用に期待も2025年10月29日
-
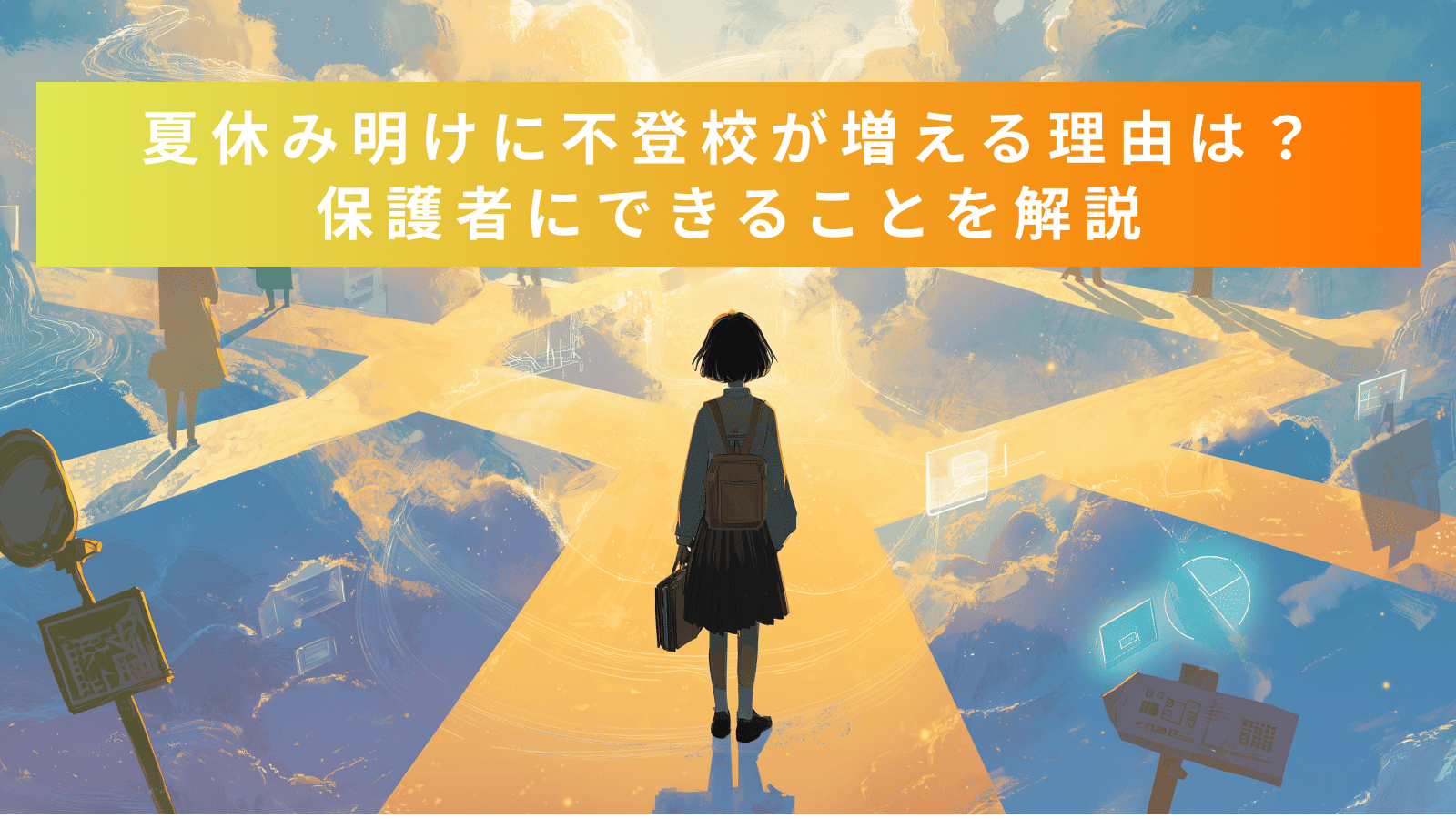
夏休み明け不登校はなぜ増えるのか。
その背景と実践的対応策2025年10月24日
FAMcampusにご興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください




富士ソフトのFAMシリーズ
FAM(Fujisoft Augmented Meetup)とは、
コミュニケーションを拡張し新たなつながりを
創出するサービスです。




