Column
メタバースが「意味ない」と誤解されているのはなぜ?
その将来性を解説
2025年11月21日

メタバースは、仮想空間上で人々が交流し、学び、働くことを可能にする次世代のプラットフォームとして注目を集めています。国内外で企業や自治体による活用が進み、市場規模も年々拡大しています。
メタバースが注目を集める一方で「意味がない」「普及しない」といった否定的な意見も少なくありません。しかし、実際にはメタバースの市場規模は着実に拡大しています。
本記事では、こうした批判がどこから生まれるのかを整理し、誤解されがちなポイントを解き明かします。また、実際の事例やデータを紹介しながら、不登校支援など教育分野における新しい可能性を紹介します。
目次
メタバースは「意味ない」「普及しない」と言われる理由
「メタバースは意味がない」といった批判の背景には、いくつかの誤解や不安が存在します。これらを整理して理解することで、メタバースが本来持つ価値を正しく見極められるようになります。
メタバース=ゲームのイメージがある
メタバースは、初期にゲーム分野で広がったことから「娯楽の場」とみなされることが少なくありません。ですが現在では、教育や医療、行政など幅広い分野で活用が進んでいます。
メタバースは、単なるゲーム空間にとどまりません。アバターを介した自然なコミュニケーション、リアルタイムの共同作業、距離を超えた学習環境の提供など、社会に新しい可能性をもたらすプラットフォームです。
とくに教育分野では、不登校の子どもたちに新しい学びの機会を生み出す事例も増えています。メタバースをゲームだけのものとせず、社会に役立つ基盤として捉える視点が求められています。
そもそもどういう技術か理解されていない
「メタバース」という言葉は広く知られるようになりましたが、その仕組みを正しく理解している人はまだ多くありません。3D仮想空間やアバター、リアルタイムでのコミュニケーションといった要素はイメージしづらく、不安や抵抗感の原因となっています。
総務省はメタバースを以下のように整理しています。
ユーザー間で「コミュニケーション」が可能な、インターネットなどのネットワークを通じてアクセスできる、仮想的なデジタル空間
引用元:総務省「「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」
つまり、メタバースの本質は「表現力の高いオンラインコミュニケーションツール」です。現在ではスマートフォンやPCから手軽に利用でき、特別な知識も必要ありません。すでに身近なアプリと同じ感覚で使える段階にまで発展しています。
仮想空間に対する抵抗感がある
アバターを使った匿名性の高い交流に対し「顔が見えないと信頼できない」「現実逃避につながるのではないか」と懸念する声もあります。とくに対面でのやり取りを重視してきた世代では、この傾向が強いようです。
一方で、不登校支援の現場では匿名性がむしろ利点となります。子どもたちは直接会う不安を軽減しながら、人とのつながりを築くことができるのです。
また、セキュリティやプライバシー保護に関する技術的・制度的な取り組みも進んでおり、安心して利用できる仮想空間の構築が目指されています。
通信の速度や遅延等、技術的制約がある
メタバースを快適に利用するためには、高速かつ大容量の通信環境が必要であり、インフラが十分でない場合、映像のカクつきや音声の途切れが発生し、利用者の離脱につながるといわれています。
しかし近年は、5Gの普及やクラウド技術の進化によって環境は大きく改善しています。地域差は残るものの、技術的な制約は着実に解消に向かいつつあります。
VR機器が必要と思われている
「メタバースには高価なVR機器が必須」と考える人は少なくありません。しかし実際には、多くのサービスがPCやスマートフォンから利用可能です。
とくに教育現場では、文部科学省が推進するGIGAスクール構想において、全国の小中学校で児童生徒に1人1台のPCやタブレットが配布されていますが、それらを活用できるメタバースも提供されています。
なかでも、2Dメタバースは3Dに比べて動作が軽く、学校のWi-Fi環境でも快適に使え、操作も分かりやすいため教育向きです。
NFTや仮想通貨が必要と思われている
メタバース上での取引方法として、NFTや仮想通貨が注目された結果「利用には必須」という誤解が広がりました。
実際には、これらは一部の機能にすぎません。教育や行政サービスにおけるメタバース利用においては不必要な機能といえます。
セカンドライフの失敗のイメージが尾を引いている
2003年に登場した仮想空間「セカンドライフ」は一時的に注目を集めましたが、当時のPCのスペック不足や通信環境の未発達さから急速に人気を失いました。その印象から「メタバースも同じように終わるんじゃないか」と思う人もいます。
しかし、現在は状況が大きく異なります。スマートフォンの普及や高速通信、クラウド技術の進化に加え、コロナ禍でリモートコミュニケーションが一般化しました。こうした環境の変化により、過去の失敗を踏まえた新しい形のメタバースが展開されています。
メタバースをとりまくポジティブな近況5選
誤解や過去の失敗による否定的な見方がある一方で、近年のメタバースには前向きな動きも数多く見られます。ここでは、メタバースを取り巻くポジティブな近況をひとつずつ見ていきましょう。
1.市場の成長性の高さ
矢野経済研究所によると、国内メタバース市場は2021年度の793億円から急拡大し、2028年度には1兆8,700億円に達すると予測されています。これは一時的なブームではなく、持続的な成長を示す数字です。
世界市場も2020年の約68兆円から2024年には約111兆円へと拡大しました。背景には、コロナ禍でのDX加速、参入企業の増加、教育や行政分野での実用価値の認識があります。
市場の伸びは投機ではなく、導入事例と成果に裏打ちされた「実用フェーズ」への移行を物語っています。
出典:矢野経済研究所「メタバースの国内市場動向調査を実施(2024年)」
(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3688?a8=4)
出典:総務省「令和6年度版情報通信白書」
(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd217520.html)
2.大手IT企業の参入
Meta(旧Facebook)は社名変更と同時に年間約1兆円規模の投資を表明し、AppleもVision ProでAR/VR市場への本格参入を示しました。
MicrosoftやGoogleといった大手IT企業も、それぞれの強みを活かし、メタバース関連技術への投資や開発を強化しており、長期的な技術戦略に基づいてこの分野に取り組んでいます。
その結果、標準化や品質向上、コスト削減が進み、一般ユーザーにとっても使いやすい環境が整いつつあります。メタバースはもはや一時的な流行ではなく、次世代のデジタル基盤の一つとして位置づけられています。
3.自治体による活用
地方創生や社会課題の解決に向け、多くの自治体がメタバースを導入しています。教育分野においては、不登校児童に対する学習環境の整備が難しいという課題を克服するためにメタバースを活用するといった、新たな取り組みが次々と生まれています。
株式会社NEXERと富士ソフトの共同調査によると、小学生から高校生の子どもを持つ保護者の約2割が「子どもが学校に行きづらさを感じている」と回答しました。
また、地域の行政による不登校支援の取り組みについては、約7割が「充実していない」と回答しており、とくに「オンライン学習・交流の支援拡充」への期待がもっとも高いことが明らかになっています。
調査データ引用元:https://famcampus.jp/column/344/
こうした背景のなかで注目されているのが、富士ソフトが提供する教育メタバース「FAMcampus」です。「FAMcampus」は、子どもたちが自宅から安心して参加できるオンラインの学習・交流空間として、神奈川県や奈良県の不登校支援事業に採択されています。
「FAMcampus」では、アバターで学習空間に入り、仲間の存在を実感できることで孤立感を和らげる工夫をしています。チャットや音声機能も使いながら、自分のペースで交流できるため、対面が苦手な子どもでも安心して利用できます。
さらに、不登校支援にとどまらず、通信制高校の授業や学校見学、高大連携プログラムなどにも広がっています。
また、観光や防災分野においても三重県志摩市や静岡県焼津市、愛知県碧南市といった自治体が地域の魅力をオンラインで発信したり、住民が仮想空間で避難体験を行える防災訓練を実施したりするなど導入を進めており、メタバースが実際に社会課題解決に役立つ実用的なサービスであることを示しています。
>>こちらでは、埼玉県さいたま市のメタバースによる不登校支援の事例をご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
>>こちらでは、愛知県大府市のメタバースによる子どもたちの居場所づくりの事例をご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
4.Web3との組み合わせの可能性
ブロックチェーンやNFT、仮想通貨といったWeb3技術と組み合わせることで、メタバースは資産の所有や分散型の仕組みを取り込み、新しい経済圏をつくる可能性があります。
実際にマネックスグループは「The Sandbox」上で近未来都市をテーマにした実証実験「OASIS」を展開し、イベントやコラボを通じて新たなビジネスモデルを検証しています。
一方で教育分野では、複雑な技術よりも安全でシンプルな利用環境が重視されます。Web3は魅力的な発展要素ですが、教育においては必要に応じて柔軟に取り入れる姿勢が重要です。
5.若年層ユーザーの増加
デジタルネイティブ世代は、メタバース普及を支える大きな原動力です。若年層にとって、メタバース空間で活動することはもはや特別なことではなく、日常の一部になりつつあります。
たとえば、フォートナイトは約5億人、Robloxは約2億人のユーザーを抱え、単なるゲームにとどまらず交流の場として機能しています。
オンラインゲームやSNSに慣れた若者にとって、アバターを通じた会話は自然な行為であり、VTuberの人気やアバター機能付きアプリの広がりも、仮想世界をより身近で楽しいものにしています。
>>教育メタバースFAMcampusを活用した不登校支援についてはこちらをご覧ください。
メタバースの普及を左右するポイント
メタバースは大きな可能性を秘めていますが、社会に広く浸透していくためには、いくつかの条件が整うことが欠かせません。ここでは、普及のカギとなる要素を整理して見ていきます。
デバイスの性能向上と価格低下
VRやARデバイスの軽量化や価格の低下は、メタバース普及の大きなカギを握っています。
現在の機器は過去に比べて格段に進化していますが、長時間の使用ではまだ負担を感じることがあります。今後さらに小型化や低価格化が進めば、日常的に利用するハードルは大きく下がるでしょう。
加えて、映画鑑賞やビジネス活用など幅広いシーンで利用価値が高まれば、購入への納得感も高まり、普及が一層進むと考えられます。
通信環境の改善
5Gの普及やクラウド技術の進化により、高速かつ大容量の通信環境が整いつつあります。通信技術やコンピュータの処理能力も飛躍的に向上しており、これまで技術的制約で実現が難しかった高品質な仮想空間体験が可能になってきました。
さらに、今後6Gが実現すれば、さらなる高速・低遅延、大規模接続が可能となり、よりリアルで没入感のあるメタバース体験の普及が加速するでしょう。
レンダリング技術の進歩
レンダリング技術とは、コンピューター上で作成された3Dデータを、私たちが見られる形の映像として描き出す技術のことです。メタバースの世界をリアルに体験できるのは、このレンダリング技術によって仮想空間の映像が滑らかに表示されているからです。
リアルタイムレンダリングは、メタバースの普及を支えるうえで欠かせない要素です。従来は高品質な映像を生成するのに長時間を要し、事前にデータを準備する必要がありました。
しかし、リアルタイムレンダリングの登場により、ユーザーの操作に応じて映像を瞬時に生成できるようになり、新しい体験価値を提供しています。
一方で、処理負荷の高さから映像の不自然さや音声の遅延が起こりやすく、高性能な機器や高速通信環境が必要とされる課題も残されています。
今後、技術革新によってこれらの問題が克服されれば、サービス品質はさらに向上し、幅広いユーザー層への浸透と市場拡大が加速すると考えられます。
デジタルツインの実装
デジタルツインは現実の施設や製品を仮想空間に再現する技術で、製造業や都市計画などでシミュレーションや効率化に活用されています。
ウォルマートの研修や川崎重工の「インダストリアルメタバース」では、現実の業務環境を再現し、コストを抑えつつ効果的な研修を実現しています。
教育分野でも、学校施設をデジタルツイン化し、不登校の子どもが安心して段階的に復帰できる仕組みづくりが進められています。
コンテンツの充実
メタバースの普及を左右する大きな要因は、多くの人が「使いたい」と思える魅力的なコンテンツの登場です。スマートフォンの普及を後押ししたLINEやInstagramのように、いわゆる「キラーコンテンツ」の存在が不可欠です。
教育現場においても、単なる学習だけでなく、子どもたちが自然に参加したくなる交流や創作の場を提供することが重要です。教育的価値と楽しさを両立したコンテンツづくりが進められています。
メタバース関連人材の育成
市場の拡大には、エンジニアや3Dクリエイター、UX/UIデザイナー、教育コンテンツ開発者など、多様な人材が欠かせません。
こうした背景から、企業や団体は人材育成プログラムを展開し、エコシステムの拡大に貢献しています。また教育分野では、教師やカウンセラーがメタバースを効果的に活用できるよう、専門的な研修の充実も求められています。
まとめ
「メタバースなんて意味がない」と思われがちですが、それは昔の技術的な制約や誤解によるものです。今は技術の進歩や大手企業の参入、自治体での活用、若者の利用増加など、広がりを裏付ける動きがたくさんあります。
とくに教育現場では、従来の仕組みでは支援が届きにくかった子どもたちに、新しい学習機会と安心できる居場所を提供できることが実証されています。それを実現しているのが、富士ソフトの教育メタバース「FAMcampus」です。
「FAMcampus」は、教育特化型のメタバースプラットフォームで、仮想空間でのコミュニケーションを通じ、不登校児や学校に行けない子ども達の学びと交流を支援します。高額なVRゴーグルや専用機器を必要とせず、学校や家庭で普及しているPCやタブレットからすぐに利用できます。
すでに全国の自治体で導入され、不登校支援の現場では「登校への一歩を踏み出せた」「家庭内の会話が増えた」といった成果が数多く寄せられています。
また、FAMcampusはあえて3Dではなく2Dを採用しています。3D空間には没入感という利点がある一方で、動作の重さや操作の複雑さ、利用者同士の位置関係が分かりにくいといった課題があります。
それに対し、2D空間は全体を見渡しやすく、誰がどこにいるのかを一目で把握できる安心感を提供しています。操作もシンプルで直感的なため、機械に不慣れな子どもでもすぐに使い始めることができます。
さらに、余計なゲーム要素を取り除き教育に特化している点も、自治体から高く評価される理由のひとつです。
FAMcampusは、子どもが「自分らしく安心して学びを始められる場所」として機能する新しい選択肢です。お子さまの状況や個性に合わせて、活用を前向きに検討してみてください。
>>参加したい方はお住まいの地域の教育委員会にお問い合わせください。
他の教育メタバースコラム
-
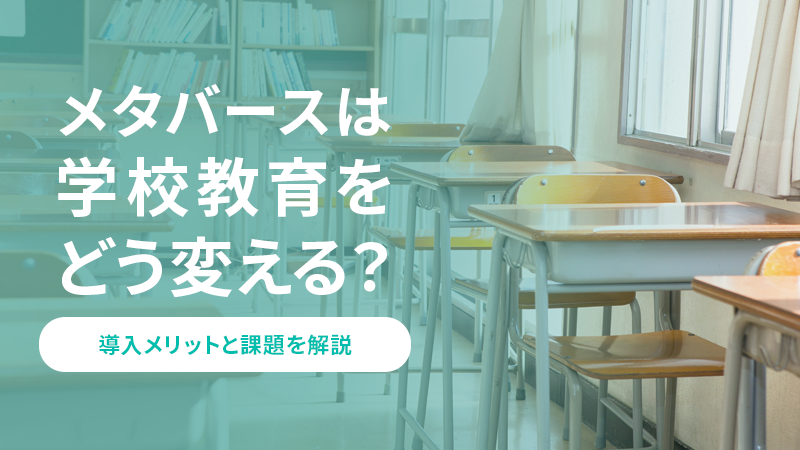
メタバースは学校教育をどう変える?
導入メリットと課題を解説2025年12月23日
-

自治体のメタバース活用事例11選
地方創生や教育支援での動向を解説2025年12月23日
-
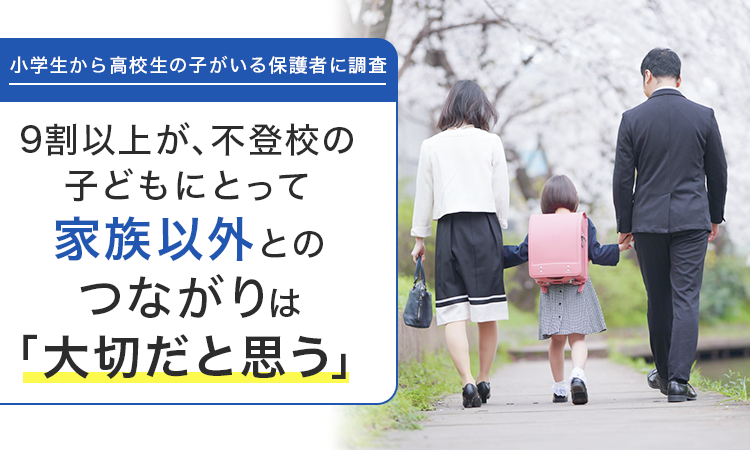
【小学生から高校生の子どもがいる保護者に調査】
9割以上が、不登校の子どもにとって家族以外とのつながりは「大切だと思う」2025年12月9日
-

メタバースとは?
VRとの違いや活用方法・課題まで分かりやすく解説2025年11月21日
-
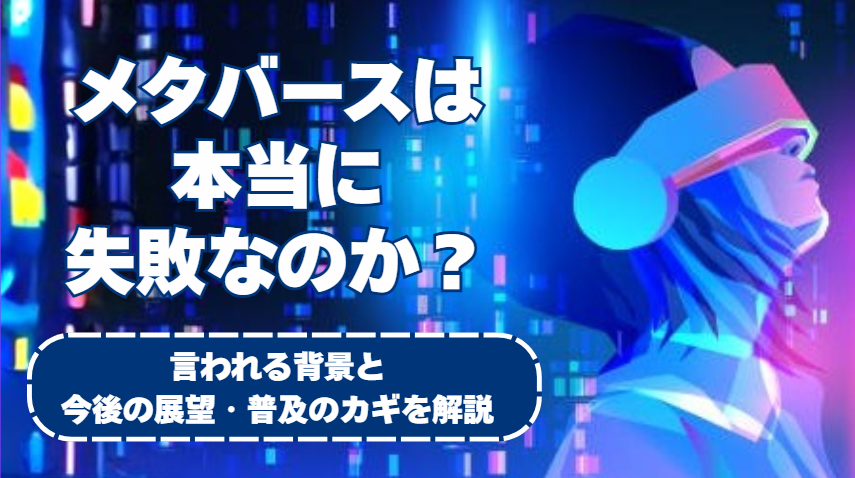
メタバースは本当に失敗なのか?
言われる背景と今後の展望・普及のカギを解説2025年11月21日
-

教育DXとは?教員・生徒・保護者それぞれのメリットと導入の進め方
2025年11月7日
-

【小学生から高校生の子がいる保護者に調査】
約2割の子どもが、「学校に行きづらさを感じている」
オンラインの活用に期待も2025年10月29日
-
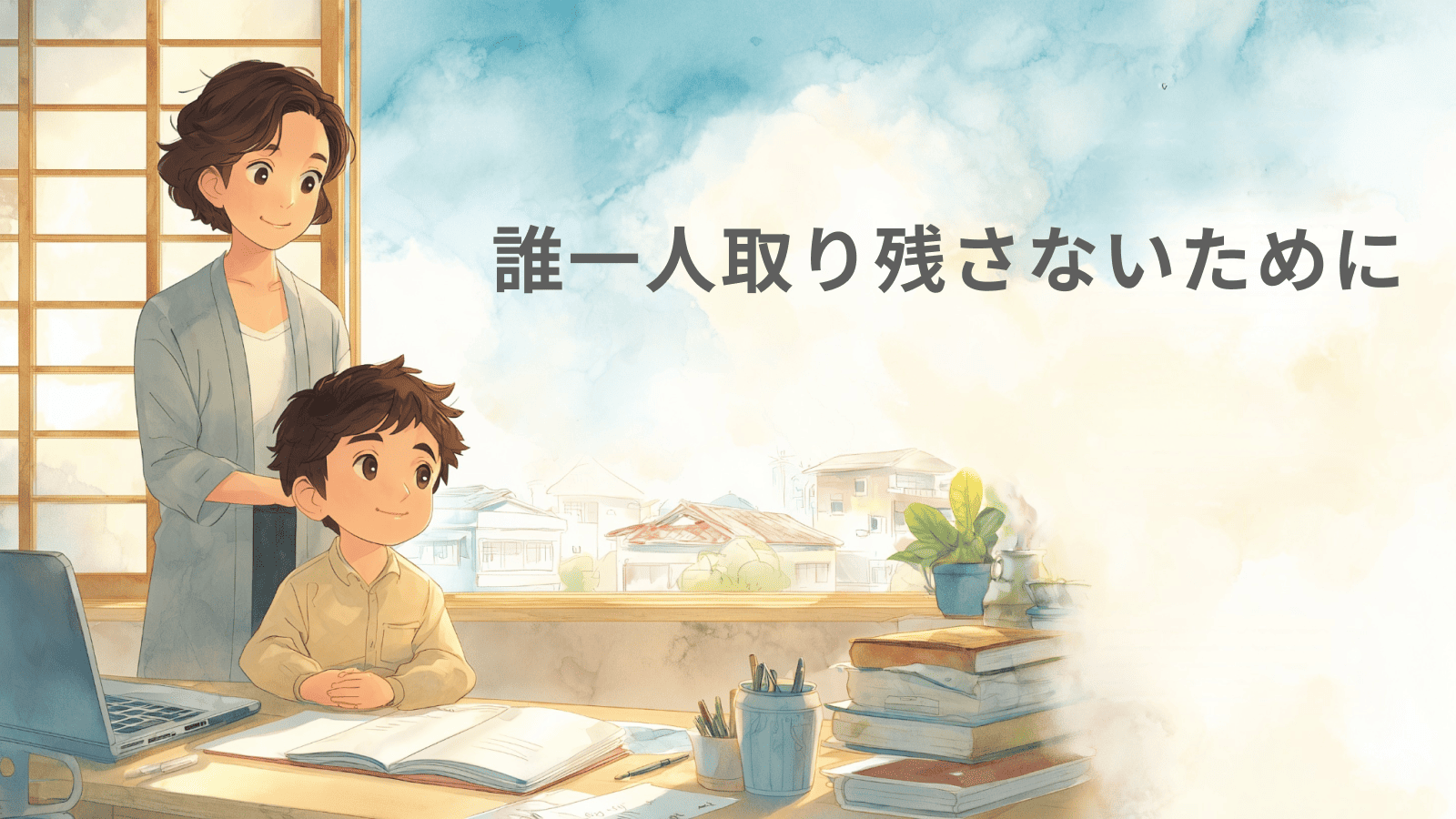
登校拒否とは?
不登校との違い、子どもへの効果的な対応・支援策を解説2025年10月24日
-
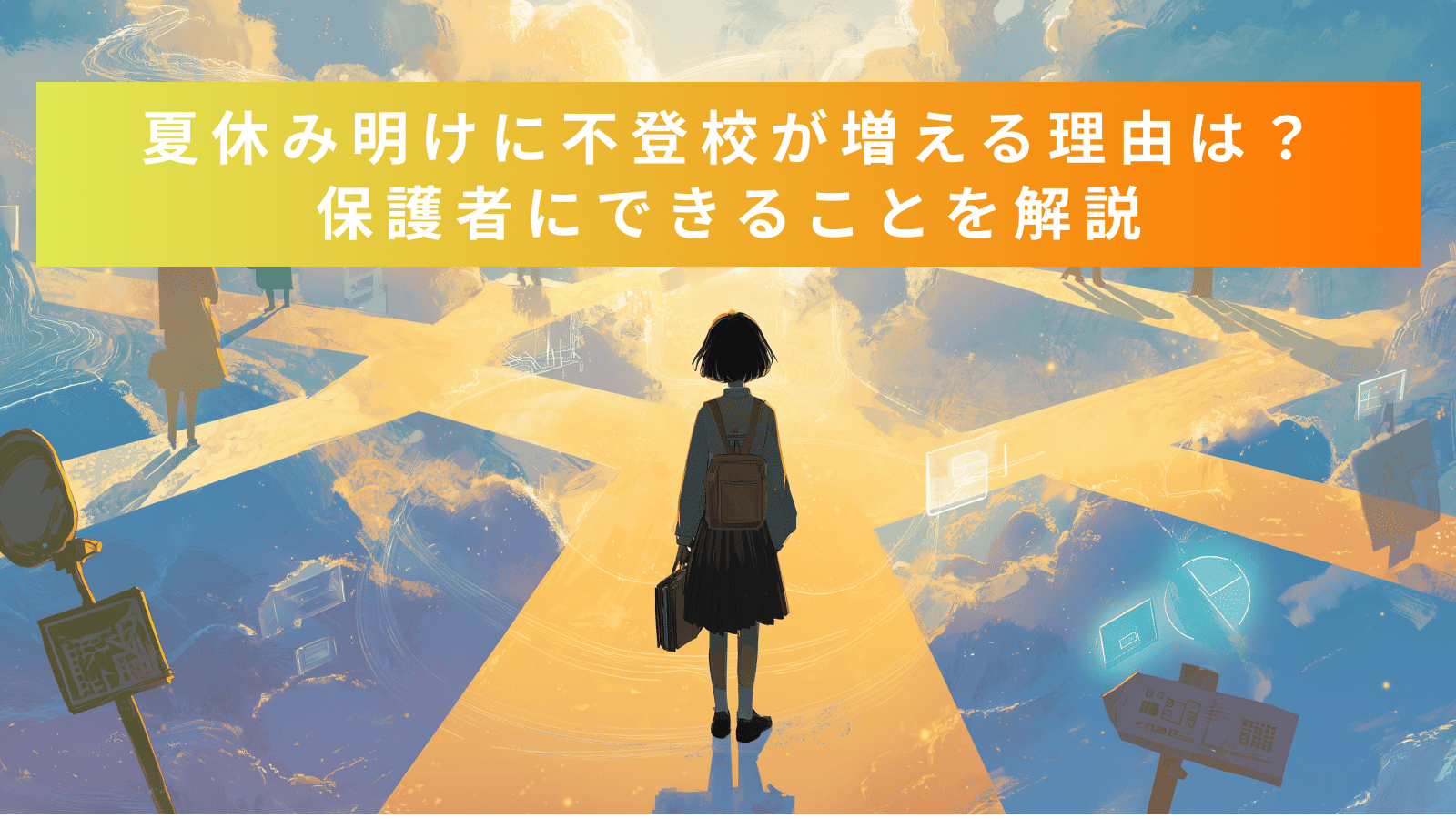
夏休み明け不登校はなぜ増えるのか。
その背景と実践的対応策2025年10月24日
FAMcampusにご興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください




富士ソフトのFAMシリーズ
FAM(Fujisoft Augmented Meetup)とは、
コミュニケーションを拡張し新たなつながりを
創出するサービスです。




