Column
メタバースは本当に失敗なのか?
言われる背景と今後の展望・普及のカギを解説
2025年11月21日
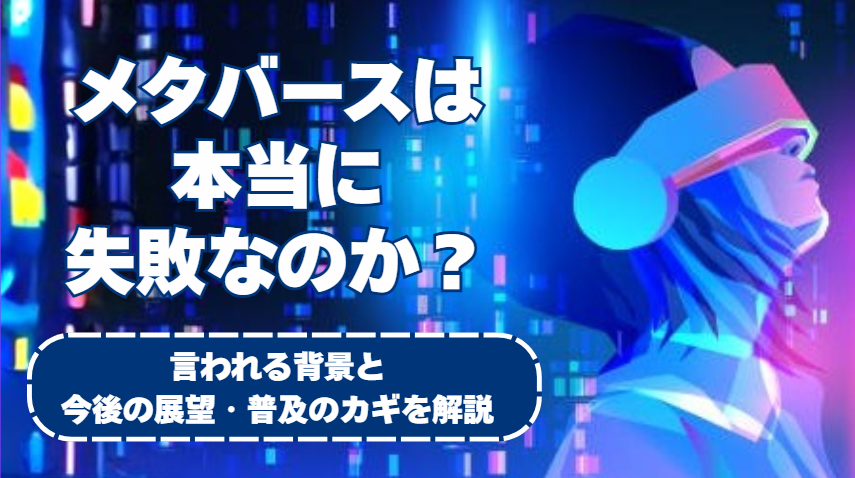
近年、Meta社(旧Facebook)の社名変更やAppleVisionProの発表など、メタバースへの注目が高まる一方で「メタバースは失敗」といった声を聞くこともあります。しかし、事実としてメタバースの市場規模は拡大していることをご存知でしょうか?
本記事では、メタバースが失敗と言われる背景から市場の現在、そして教育分野での可能性まで、データと事例にもとづいて詳しく解説します。
目次
メタバースの91.9%は事業化に失敗?
メタバースに対する厳しい現実を示すデータがあります。株式会社クニエ(QUNIE)が実施した「メタバースビジネス調査レポート」では、国内のメタバースビジネスにおいて事業化の成否が判明している取り組みのうち、91.9%が事業化に失敗しているという衝撃的な事実が明らかになりました。
この調査は、メタバースビジネスの事業化検討に関わったことがある企業担当者1,803人を対象に実施されたものです。事業化の停滞や中止に追い込まれた企業が9割を超えるという結果は、メタバース業界に大きな衝撃を与えました。
しかし、この数字だけを見て「メタバースは失敗」と結論づけるのは早計です。実際、この高い失敗率には明確な理由があります。
出典:QUNIE「メタバースビジネス調査レポート」(https://www.qunie.com/pdf/service/QUNIE_NewBiz_report_summary_20230523.pdf)
メタバースが「失敗」と言われる理由
91.9%という高い失敗率を受けて、メタバースが「失敗」と言われる理由を詳しく見てみましょう。その背景には、技術的な課題から社会的な認識不足まで、複数の要因があります。
メタバース自体が理解されていない
最も大きな課題は「メタバース」という概念そのものが正しく理解されていないことです。多くの人がメタバースを単なる「3Dのオンラインゲーム」と同一視しており、ビジネスや教育における新たなプラットフォームとしての可能性が十分に認識されていません。
とくに教育分野では、この誤解が顕著に現れます。メタバースを「ゲームのような娯楽」として捉える教育関係者も多く、学習支援という真剣な取り組みにゲーム要素を持ち込むことへの抵抗感が根強く存在するのです。
しかし実際のメタバースは、単なるゲーム空間ではありません。アバターを通じた自然なコミュニケーション、リアルタイムでの共同作業、距離の制約を超えた学習環境の提供など、教育における革新的な可能性を秘めたプラットフォームなのです。
ITの知識がある程度は必要になる
メタバースの利用には、一定のITスキルが求められることも普及の障壁となっています。アバターの操作、仮想空間での移動、コミュニケーション機能の使い方など、初心者には複雑に感じられる操作が存在します。
とくに教育現場では、生徒だけでなく指導者側にも技術的な理解が必要となり、導入への心理的ハードルが高くなりがちです。「設定が難しそう」「操作を覚えるのが大変」といった先入観が、メタバース活用の検討段階で足踏みを生む要因となっています。
とはいえ、近年は初心者が扱いやすい工夫が進んでおり、ユーザーインターフェースの改善や技術サポートの充実、さらにはPCやスマートフォンなど身近なデバイスから利用できるサービスが増えています。
こうした環境の整備により、必要な知識や技術の習得もしやすくなり、技術的なハードルは以前に比べて着実に下がってきています。
VR機器が普及していない
メタバースを最大限に活用するためには高性能なVR機器が推奨されることが多く、その高価な初期投資が普及の妨げとなっています。教育現場においても、予算の制約からVR機器の導入は現実的ではないケースが大部分です。
しかし重要な点は、VR機器が必須ではないメタバースサービスが数多く存在することです。実際、多くの教育向けメタバースプラットフォームは、PCやタブレット、スマートフォンからもアクセス可能に設計されており、特別な機器を必要としません。
とくに教育現場では、文部科学省が推進するGIGAスクール構想の端末(1人1台のコンピューター)に対応しており、全国の小中学校で児童生徒一人ひとりに配布されたパソコンやタブレットをそのまま活用できます。
失敗と言われつつ...メタバースの市場規模は拡大している
このような課題がある一方で、メタバース市場は着実な成長を続けています。矢野経済研究所の最新調査(2024年)によると、国内メタバース市場規模は2023年度1,863億円から2024年度2,750億円へと大幅な拡大を見せ、2028年度には1兆8,700億円に達すると予測されています。
この数字は、個別企業の事業化における課題と、市場全体の成長ポテンシャルが別次元の話であることを示しています。失敗事例が多いということは、まさに黎明期にある新市場の特徴そのものであり、試行錯誤の中から価値あるサービスが生まれてくる過程なのです。
世界規模で見ても、メタバース市場は2020年の約68兆円から2024年には約111兆円への成長が予想されており、この拡大基調は継続すると考えられています。とくに注目すべきは、教育分野でのメタバース活用が急速に広がっていることです。
出典:矢野経済研究所「メタバースの国内市場動向調査を実施(2024年)」
(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3688?a8=4)
メタバース市場が成長すると予想される背景
メタバース市場の継続的な成長を支える要因は多岐にわたります。技術革新、社会情勢の変化、そして新世代の価値観の変化が複合的に作用し、メタバースの社会実装を後押ししています。
ビッグテック企業の参入と巨額投資
Meta社(旧Facebook)の年間約1兆円規模の投資発表を皮切りに、Apple等の世界的テクノロジー企業がメタバース分野に本格参入しています。2023年6月にAppleが発表した「AppleVisionPro」は、その技術的完成度の高さで業界に大きな衝撃を与えました。
これらの巨額投資は、単なる一過性のブームではなく、次世代のコンピューティングプラットフォームとしてメタバースを位置づけた長期戦略にもとづくものです。
スマートフォンに続く次のメジャーデバイスとして、メタバース対応機器の開発競争が激化していることが、市場の将来性を表しています。
関連技術の急速な進化
通信技術やコンピュータの処理能力の向上など、メタバースを支える基盤技術が飛躍的に発展しています。これにより、従来は技術的制約で実現困難だった高品質な仮想空間体験が可能になってきました。
セカンドライフが登場した2000年代前半と比較すると、現在のメタバースは遥かに滑らかで没入感のある体験を提供できるようになりました。通信速度の遅さや処理能力の不足という技術的制約は、もはや決定的な障壁ではなくなったのです。
デバイスの価格低下
VR機器の価格は確実に下がっています。たとえば、MetaQuest2の発売当初価格と現在価格を比較しても、性能向上と価格低下が同時に進んでいることがわかります。
また、AppleVisionProは現在約51万円と高価ですが、新技術の導入初期としては妥当な価格帯であり、今後の量産効果により価格下降が見込まれます。
リモートコミュニケーションの普及
新型コロナウイルスの感染拡大により、リモートワークやオンライン教育が急速に普及しました。この変化は人々の働き方や学び方に対する価値観を根本的に変え、デジタルを介したコミュニケーションへの抵抗感を大幅に軽減しました。
ZoomやTeams、Slackなどのツールが日常的に使われるようになった結果、さらに一歩進んだコミュニケーション手段として、メタバースへの需要が高まっています。
とくに教育分野では、画面越しの一方向的なオンライン授業の限界が明らかになり、より双方向的で没入感のあるメタバース空間での学習に対する期待が高まっているのです。
不登校児童にとって、自宅から安心して参加でき、ほかの生徒や教員との自然な交流が可能なメタバース教育環境は、従来のオンライン学習では実現できなかった価値を提供します。
若年層を中心とした利用者数の増加
現在のメタバースブームを支えているのは、デジタルネイティブ世代の若年層です。重要な点は、これらの若年層にとってメタバース空間での活動が「当たり前」になっていることです。
若年層は、ゲーム型メタバースを通じて、アバターでのコミュニケーション、仮想空間での協働作業、デジタルアイテムの取引などに慣れ親しんでいます。
教育現場においても、この世代の特性を活かすことで、より効果的な学習環境を構築できる可能性があります。生徒のなかにも、すでにこうしたデジタル環境に親しんでいる子どもが多く、メタバース学習環境への適応はむしろ従来の教室環境よりもスムーズかもしれません。
また、教育向けメタバースの可能性として注目されているのが、不登校の児童生徒が仮想空間であれば積極的に参加できるケースが多いことです。アバターを通すことで心理的負担が軽減され、より自然なコミュニケーションが可能になる効果が報告されています。
仮想世界に対する認識の変化
かつては仮想空間での活動に対してネガティブな印象を持つ人が多くいましたが、コロナ禍を経て、この認識は大きく変化しました。リモートワークやオンライン授業が当たり前になる中で、デジタル空間での活動に対する偏見は大幅に軽減されています。
とくに教育分野では、オンライン学習の普及により「デジタル環境での学び」に対する抵抗感が薄れています。保護者や教育関係者も、デジタル技術を活用した新しい学習形態の価値を認識するようになってきました。
こうした流れのなかで、メタバースを活用した教育サービスも注目されています。教育メタバースの中でもFAMcampusは、「みんなを感じられる学習空間」として、孤立しがちな不登校児童にとって、新しい学びと成長の機会を提供する可能性を秘めています。
仮想空間だからこそ実現できる安心できる居場所、そこでのつながりが、子どもたちの学習意欲や社会性の回復に大きく寄与することが期待されています。
メタバースの現在地と今後のシナリオ
ガートナーの「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル:2024年」によると、メタバースは現在「幻滅期」から「啓発期」への移行段階にあるとされています。
これは技術の終焉を意味するものではなく、過度な期待が収束し、実用的な応用に向けた現実的な取り組みが始まる重要な転換点です。
大和総研の分析でも「メタバースが幻滅期で終わったと結論付けるのは時期尚早」とされており、むしろこの段階こそが真の価値創造が始まる時期として位置づけられています。実際、教育分野ではすでに実証実験から実用段階に移行しているサービスが複数存在します。
メタバース市場は今後、黎明期(~2025年)、普及期(2025年~2030年)、定着期(2030年以降)の3つの段階を経て発展すると予測されています。現在の黎明期から普及期への移行において、教育分野は最も重要な応用領域のひとつとして注目されており、不登校支援を含む多様な学習ニーズへの対応が急速に進んでいます。
とくに注目すべきは、2030年以降の定着期では、メタバースを活用した教育や研修が「当たり前」の選択肢となり、多くの自治体で不登校児童への学習機会提供の標準的な手段として採用される可能性が高いことです。
出典:Gartner、「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル:2024年」を発表(https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20240807-future-oriented-infra-tech-hc)
出典:メタバースは本当に幻滅期で終わったか?(大和総研)(https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20250611_025151.html)
失敗ばかりじゃない!メタバースの活用例
メタバースには課題や失敗事例も指摘されていますが、一方で効果的に活用されている成功事例も着実に増えています。とくに教育分野では、従来の学習環境では対応が難しかった課題を解決する革新的な取り組みが次々と生まれています。
その代表例のひとつが、富士ソフトが提供する教育メタバース「FAMcampus」です。FAMcampusは奈良県や神奈川県の不登校支援事業に正式採択され、子どもたちが家から安心して参加できるオンラインの学習・交流空間として活用されています。
アバターを使って学習空間へ入ることができ、"仲間の存在を感じられる空間"として、孤立感を軽減します。また、チャットやボイス機能を通じて、自分のペースでコミュニケーションを始められるため、対面が苦手な子どもでも安心して参加できます。
メタバース内で授業や面談、交流イベントなどを実施していく中で、子どもたちは「家庭以外の人とのつながり」を自然に取り戻すきっかけを得られます。これらの特性は、単なるオンライン授業ツールにはないFAMcampusならではの強みです。
さらに、不登校支援にとどまらず、通信制高校の授業や学校見学、高大連携プログラムなど幅広い教育現場で導入が進んでいます。
また、鹿児島県の離島や過疎地では、小規模校同士が合同授業を行うための教育基盤としても活用されており、地域の教育格差解消にも寄与しています。
ビジネス・研修分野では、ウォルマートが17,000台のVRデバイスを全米約4,700店舗に配備し、ブラックフライデーなどの繁忙期を想定した研修を実施しています。現実では再現困難な状況をメタバース空間でシミュレーションし、従業員の対応力向上に成功しています。
観光・プロモーション分野では、埼玉県の「バーチャル埼玉」や大阪府・大阪市の「バーチャル大阪」が、自治体の魅力発信の新たな手段として注目されています。
これらの成功事例に共通するのは、メタバースの技術的特性を活かして、従来では解決困難だった具体的課題に取り組んでいることです。
とくに教育分野においては、不登校児童の学習機会確保という社会的課題に対する革新的なソリューションとして、メタバースの真価が発揮されています。
>>こちらでは、埼玉県さいたま市のメタバースによる不登校支援の事例をご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
>>こちらでは、愛知県大府市のメタバースによる子どもたちの居場所づくりの事例をご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
まとめ
メタバースは91.9%の高い失敗率が報告されています。しかし、それは普及に向けた試行錯誤の段階です。重要なのは、失敗の裏で進む「確かな成功」に注目することです。
教育分野では「メタバース」が子どもたちの学びや居場所を支える有効な手段として成果を上げています。
これまで外出が困難で支援を受けることができなかった不登校の児童生徒がアバターを通して安心して学習に参加したり、家族以外の人と関わるきっかけを作り、孤独感を和らげるなど、従来の教育環境では難しかった課題を解決しています。
富士ソフトが提供する教育メタバース「FAMcampus」は教育専用のメタバース環境を提供し、全国の自治体で導入実績を重ねています。
不登校支援での活用では利用家庭から「外に出られるようになった」「親子の会話が増えた」「学校に戻れた」といった前向きな変化が数多く寄せられています。
さらにFAMcampusは、3Dではなくあえて「2D形式」を採用しています。3D空間は没入感に優れていますが、動作の重さや複雑な操作、参加者の位置把握の難しさといった課題があります。その点、2Dであれば「全体を見渡せる」「誰がどこにいるか一目でわかる」といった安心感があり、操作もシンプルで直感的で機械に不慣れな子どもでもストレスなく利用できます。
FAMcampusは、子どもが自分らしく安心して一歩を踏み出せる新しい学びの場を提供しています。
>>参加したい方はお住まいの地域の教育委員会にお問い合わせください。
他の教育メタバースコラム
-
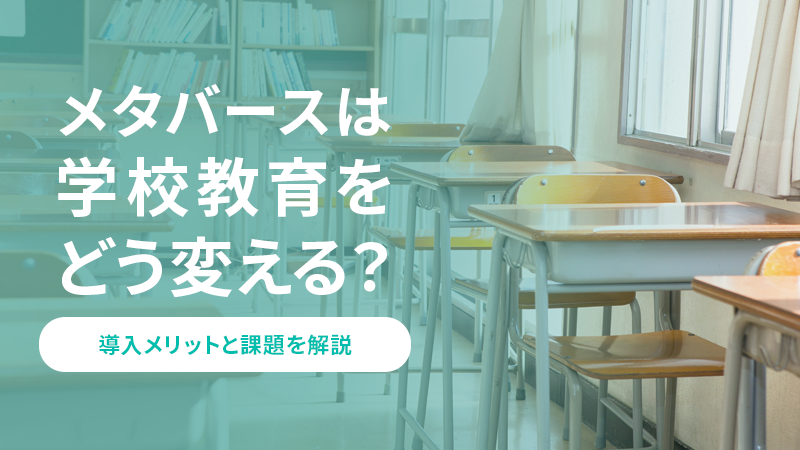
メタバースは学校教育をどう変える?
導入メリットと課題を解説2025年12月23日
-

自治体のメタバース活用事例11選
地方創生や教育支援での動向を解説2025年12月23日
-
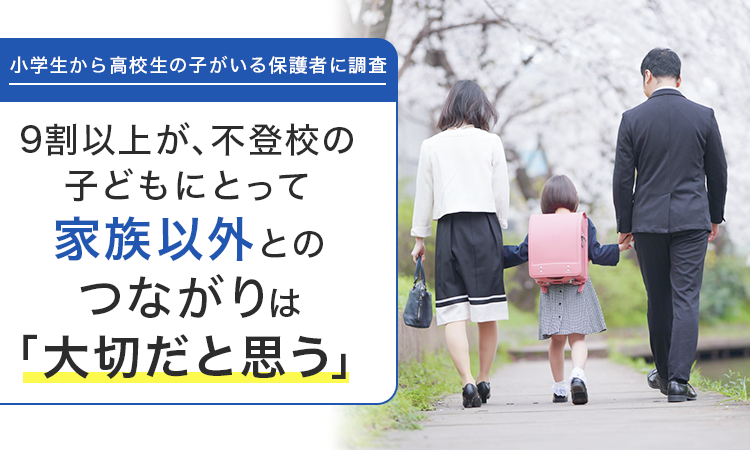
【小学生から高校生の子どもがいる保護者に調査】
9割以上が、不登校の子どもにとって家族以外とのつながりは「大切だと思う」2025年12月9日
-

メタバースとは?
VRとの違いや活用方法・課題まで分かりやすく解説2025年11月21日
-

メタバースが「意味ない」と誤解されているのはなぜ?
その将来性を解説2025年11月21日
-

教育DXとは?教員・生徒・保護者それぞれのメリットと導入の進め方
2025年11月7日
-

【小学生から高校生の子がいる保護者に調査】
約2割の子どもが、「学校に行きづらさを感じている」
オンラインの活用に期待も2025年10月29日
-
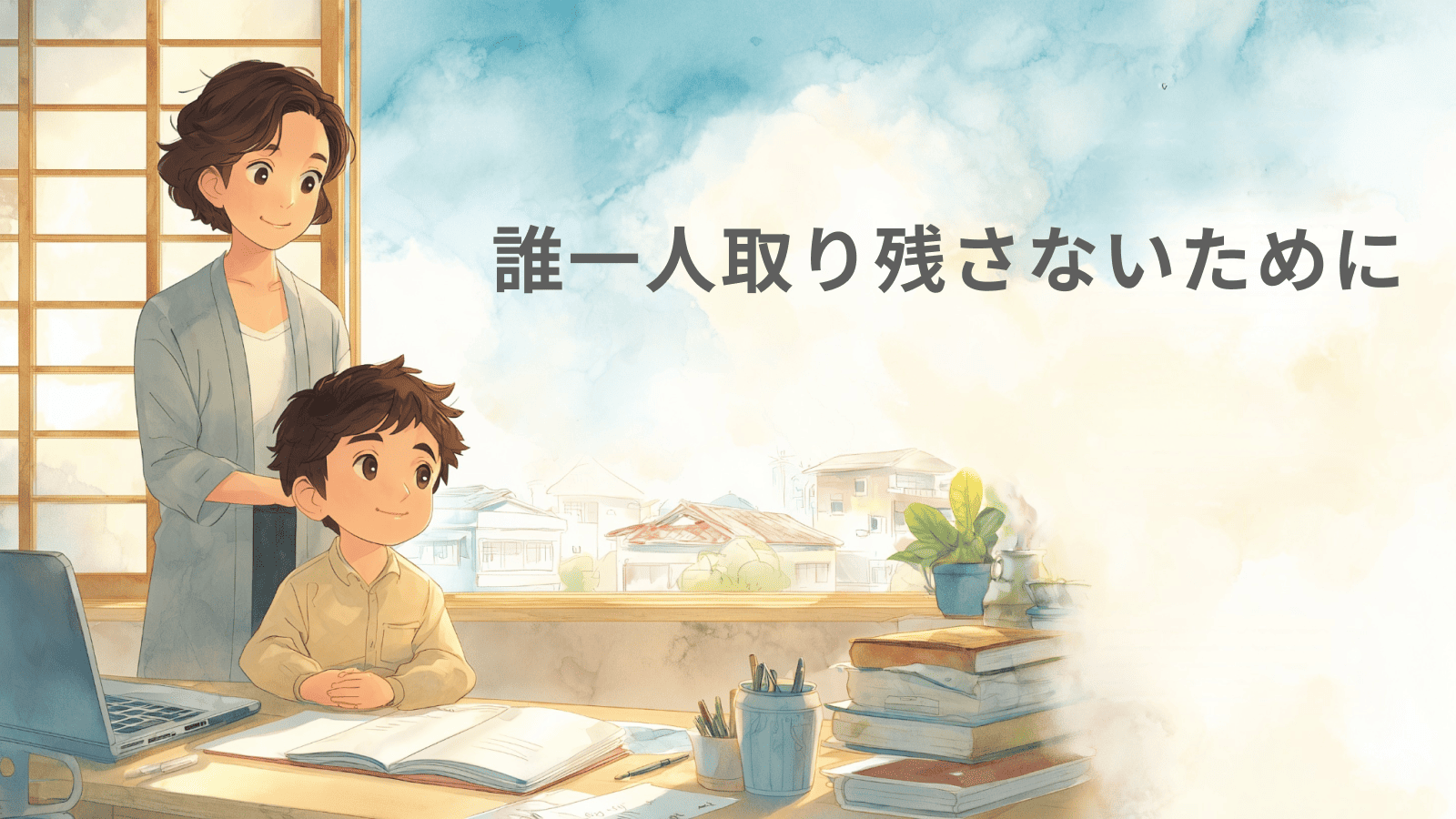
登校拒否とは?
不登校との違い、子どもへの効果的な対応・支援策を解説2025年10月24日
-
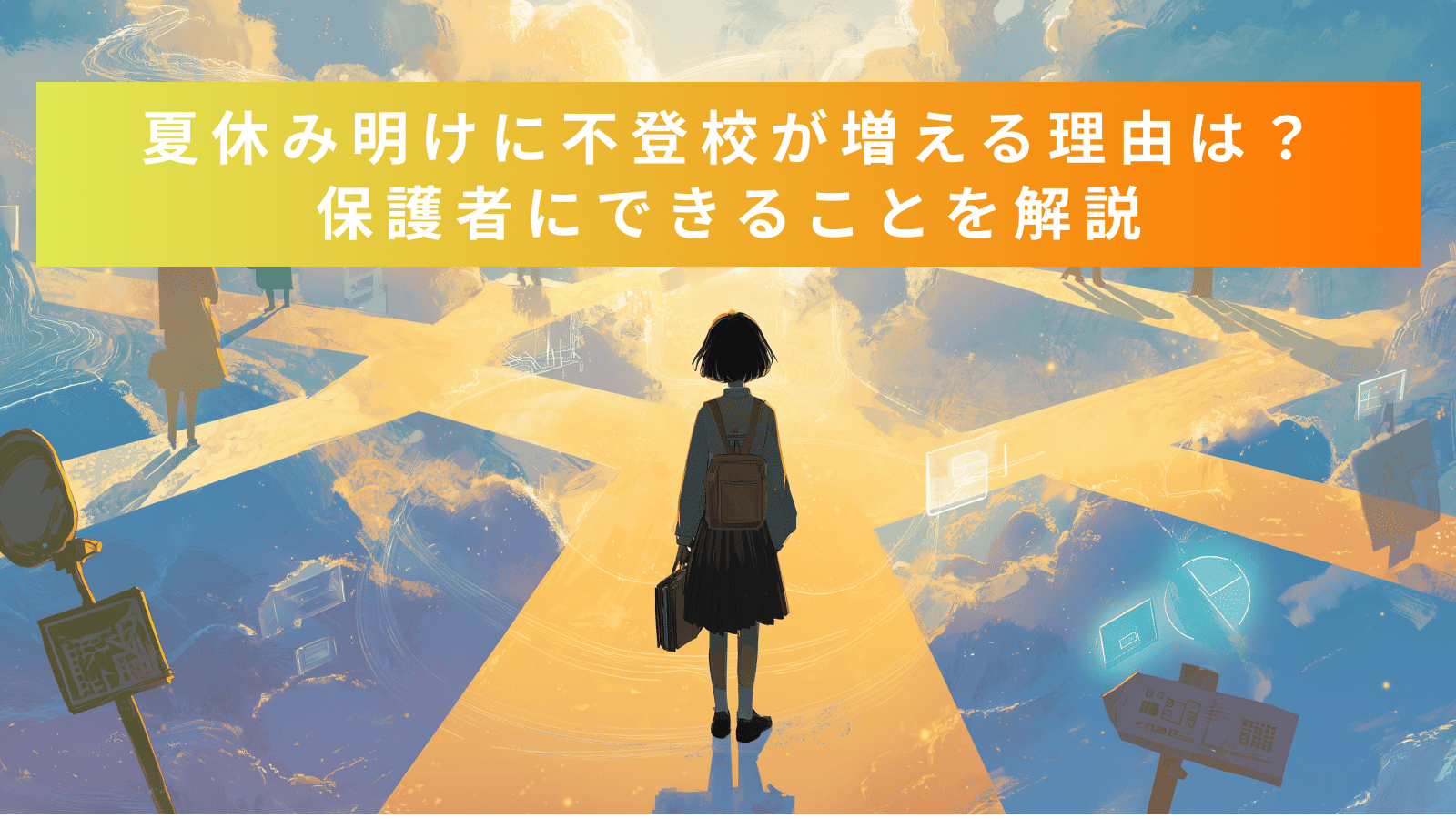
夏休み明け不登校はなぜ増えるのか。
その背景と実践的対応策2025年10月24日
FAMcampusにご興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください




富士ソフトのFAMシリーズ
FAM(Fujisoft Augmented Meetup)とは、
コミュニケーションを拡張し新たなつながりを
創出するサービスです。




